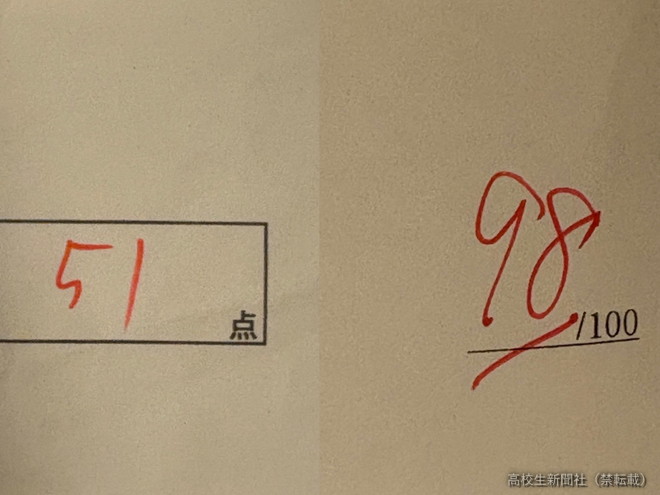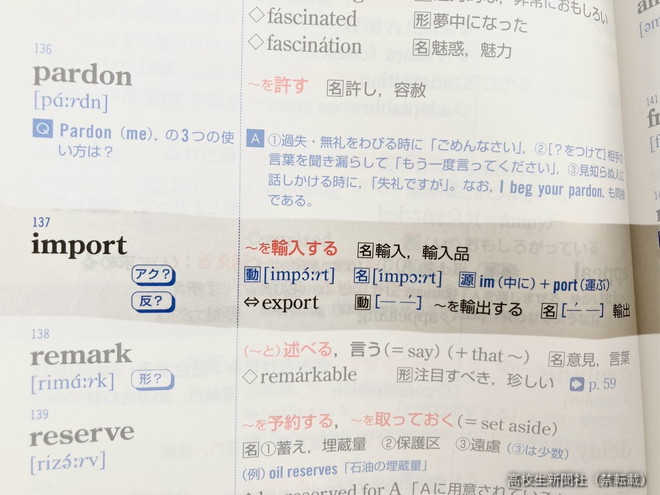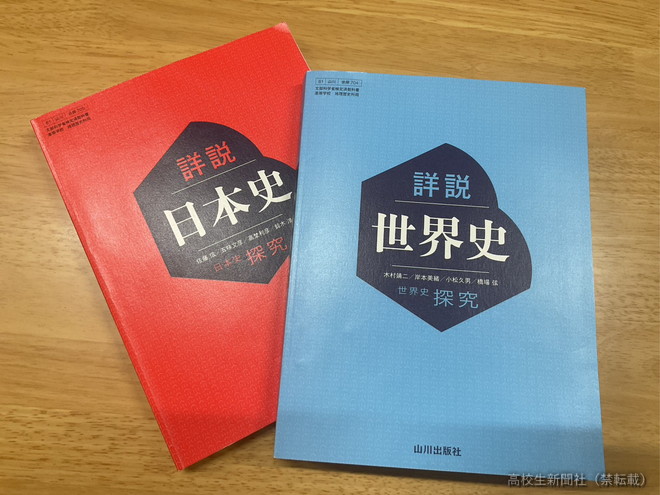篠山東雲高校(兵庫)自然科学部は、自然豊かな丹波篠山市で生き物の調査や飼育に力を注いでいる。小学生向けの観察会を企画するなど、地域貢献にも一役買っています。生き物と全力で向き合い奮闘する日々を、部長の三木大志さん(3年)に紹介してもらった。
30種類の生き物を5人で世話
―自然科学部の活動内容を教えてください。
自然科学部は1年生2人、2年生2人、3年生1人の計5人で活動しています。
平日は、理科室で飼育しているカワムツやモツゴなどの魚類、カエルやイモリなどの両生類の水槽掃除や水替え、エサやりなどをしています。生き物は約30種類を飼育しています。冬は、校内にあるビオトープの整備をしています。

休日は、篠山城堀の外来生物の駆除活動や、地域の小学生に向けた生き物観察会での指導、ささやまの森公園での生物調査などをしています。
生き物観察会は、地域の子ども会などから依頼を受けて講師としてイベントを開催します。近くの川に行って、参加者と一緒に約1時間で生き物を捕まえ、30分ほど生き物の生態や特徴の解説をしています。
ささやまの森公園では、オオルリ、サンコウチョウといった野鳥やヤゴなどの水生生物、ネズミなどの哺乳類を調査。昨年から始めた活動で、今はどんな生物が暮らしているのか調べています。
そして、発表会やフォーラムがあるとエントリーし、発表のためのスライドや資料を作成したりしています。兵庫県生物学会が開催している高校生向けの発表会や、「総合文化祭自然科学部門発表会」「全国ユース環境活動発表大会」などに出場しています。
平日は教室、休日は学校外で活動
―活動の流れを教えてください。
平日は週2日、休日は月2、3日活動しています。
-
【平日】
15:30~17:00 発表用のスライドの作成、発表要旨の作成
17:00~18:00 水槽の掃除、水替え
【休日・外来種捕獲をする日】
9:00~11:30 篠山城堀での外来生物の捕獲
11:30~12:30 捕獲道具の片付け
12:30~13:00 学校へ移動
13:00~14:00 捕獲した外来生物の個体数等の計測
14:00~15:00 捕獲したウシガエルの調理と試食
15:00~16:00 捕獲したウシガエルの胃内容物の調査
16:00~16:30 後片付け
【休日・生き物観察会を開催する日】
9:30~10:00 観察会をする川に到着。川の安全確認や、観察会で使う水槽の用意
10:00~11:00 生き物観察会開始。参加者に注意事項を説明したのち、川の生き物を捕まえる
11:00~11:30 捕まえた生き物の生態や特徴を解説。解説後は、捕まえた場所に生き物を逃がして観察会終了
11:30~11:45 片付けをして解散
―楽しいと感じる活動は?
篠山城の堀の外来生物を駆除するとき、定置網にウシガエルの成体が多く入って捕獲できると楽しいです。堀の近くの住人の方からはお礼の言葉をかけられることがあります。
捕まえたウシガエルやアメリカザリガニを食べる活動が珍しいと思いますし、楽しみながら地域の自然環境の保全にも貢献できていると思います。

「新しい発見」にあふれている
―活動の魅力ややりがいは?
地元である丹波篠山市は、自然が豊かで多種多様な生き物に触れられます。僕は昔、都心に住んでいたので、入部したときは初めて見る生き物ばかりでした。「こんな魚もいるんだ!」と、新しい発見がたくさんあって面白いです。
地域の小学生に向けた生き物観察会では、小学生から「楽しかった」「新しい発見があった」と言ってもらえてうれしいです。小学生に生き物のおもしろさを伝えられるのも、この部活の魅力です。