物価高が止まらない。生活が苦しくなり、「値下げ」を求める声も多く寄せられる。しかし経済コラムニストの高井宏章さんは、物価が上がること自体は「悪いことではない」という 。どういうことなのか解説してもらった。(木和田志乃)
前編:「【早わかり解説】値上げが止まらない理由は? 「仕方ない」意識の変化が後押し」はこちらから
物価が上がっても賃金も上がれば問題なし
―今のように物価高が続くと生活が苦しくなり、欲しいものも買えなくなってしまいます。
物価が上がるのは嫌ですよね。ただ、物価が2%上がっても、社会人なら給料、学生ならお小遣いが3%上がっていれば、経済的には豊かになっています。あくまで物価は「賃金とのバランス」で考えるべきで、物価自体が上がる、下がることだけに注目するのはあまり意味がありません。
現在の様子を見ると、物価全体は年率2%程度しか上がっていませんが、食品など購入頻度が高いものは10%程度上がっています。
対して賃上げは大抵の場合年に1回しか行われないので、物価上昇に賃金が追いついていないのが現状です。そのため生活が苦しくなったと感じるんです。
―賃金が追いつくような動きはあるのでしょうか?
今、多くの企業が初任給を上げたり、数年前から連続して5~6%ずつ基本給を上げたりなどの賃上げを実施しています。最低賃金は大幅に上がっていますので、生活に余裕が出てきたと感じる時が来るはずです。
「少しインフレ」の状態が経済を活発に
―そもそも「物価高」自体は悪いことではないのでしょうか?
実は経済学者の中でもきちんと結論が出ている話ではありませんが、私は、「少しインフレ」の状態が理想だと考えています。日本もアメリカもヨーロッパも、インフレ率の目標値は年率2%。要するに、「年に2%程度物価を上昇させること」を目標にしています。インフレ率が2%の場合、モノの値段は5年後に10%強程度上がり、35年後には2倍になります。
将来必ず値上がりすると分かっていると、人間は買いたいものを先延ばしにせずに購入します。結果、消費が増え、企業の利益が増え、給料も増え……と、経済活動が活発になるといえます。

―インフレの方が経済が活発になるんですね。
加えて、景気は良くなったり悪くなったりします。物価が下がっている「デフレ」の状況で、貸したお金に対して発生する利息の割合「金利」が低ければ、それ以上金利を下げられず、景気を刺激する政策を打ち出せません。インフレが進むと金利は上がる傾向にあるので、「いざというときに金利を下げる余裕があった方がいい」という意味では、少しインフレの状態の方がいいと思います。
物価が低いと経済も回らない?
―物価が低いことによるデメリットはありますか?
物価が下がったり、上がらなかったりしない「デフレ」の状態では、欲しいものがあってもすぐには買わなくなり、消費が減ります。すると企業の業績が悪化し、従業員の給料が減ります。「我慢して現状維持しておいた方がいい」という考えになりがちです。
さらに、業績不振で経営が破綻しているにも関わらず、金融機関や政府などの支援により存続しているような企業、いわゆる「ゾンビ企業」があります。物価が下がり、金利が0%など極めて低い水準になると、こういった企業が生き延び、経済の効率性が下がると言われています。
―物価高の現在、「ゾンビ企業」はどうなっていますか?
最近は「ゾンビ企業」の中で、金利がつくようになって利払いができなくなり倒産する例が増えています。その企業の従業員たちは働く場所がなくなって困窮するかというと、そうではありません。世の中のニーズに応えている労働条件のよい会社に移ったり、起業したりしています。
輸入品の価格上昇は落ち着く見込み
―これからも物価上昇は続きますか?
ロシアとウクライナの戦争や円安の影響で上がった輸入品価格の上昇は、今後、沈静化していくと考えられます。1年前と比べると、円安はそれほど進んでおらず、輸入品のインフレ率は0%に近づいています。
ただし、トランプ大統領が再就任し、その政策次第ではさらなる物価上昇も予想されるため、先行きは不透明です。
インフレは「若い人の味方」
―物価高と付き合っていくために、高校生は何をしたらいいでしょうか。
高校生にとっての物価高の影響は、お小遣いと結びついていると思いますが、お小遣いの原資はおそらく保護者の給料ですよね。保護者の給料が上がっているか確認して、お小遣いアップを頼むのがいいと思います。
もう一つは大学の学費です。学費値上げの動きを見ておいてください。奨学金の額、親の負担額を増やす必要があるかもしれません。下宿するつもりであれば、家賃、食費の上昇も考えに入れておいてください。
―学費など、直近の暮らしに影響してくるんですね。
ただし極端なことを言うと、社会人になったら物価高について考える必要はありません。初任給は上がっていますし、「若い人材を確保するには賃金を上げる必要がある」時代です。しっかりと勉強に取り組み社会の役に立つ人間になるように努力してください。そうすればインフレに負けることはありません。インフレは若い人の味方です。













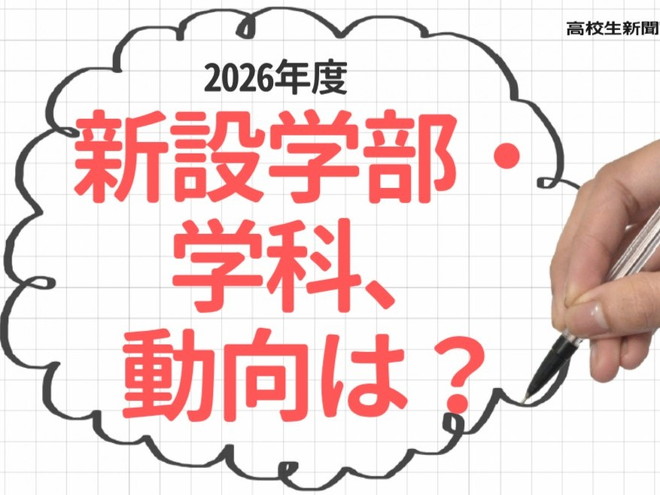





たかい・ひろあき
経済コラムニスト。元日本経済新聞編集委員。YouTubeチャンネル「高井宏章のおカネの教室」を始め、Xやnoteでも、経済にとどまらず書評や教育論など幅広い情報を発信している。4月から千葉商科大学付属高校の校長に就任予定。