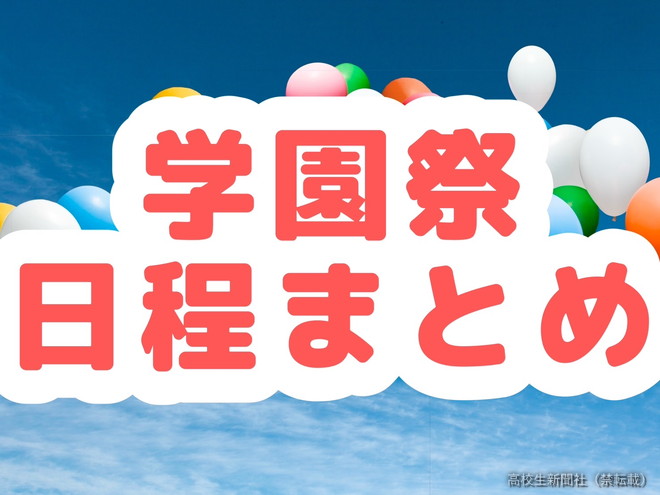武部貴則さん(38歳)は、iPS細胞から「ミニ肝臓」を創り出すなど再生医療研究で数々の功績をあげている医科学者だ。東京科学大と大阪大で教授を務め、海外にも研究拠点を持っている。武部さんの「今」を作り上げたのは、中高時代に青春の全てを捧げて熱中した吹奏楽部の経験にあるという。(文・黒澤真紀、写真・本人提供)
父が病に倒れ、医学を志すきっかけに
武部貴則さんは、iPS細胞やES細胞を使って体内の臓器をどう育てるか研究している。26歳の若さでiPS細胞から「ミニ肝臓」を作成し英科学誌『ネイチャー』に論文が掲載され、世界的にも注目された。ドイツの伝統ある医学賞「ベルツ賞」の受賞、横浜市立大や東京医科歯科大(現・東京科学大)の教授に最年少の31歳で就任するなど、日本の再生医療をリードする。多くの哺乳類にお尻から呼吸する能力があることを発見し、2024年のイグ・ノーベル賞を受賞した。いつから医学の道を志したのか。
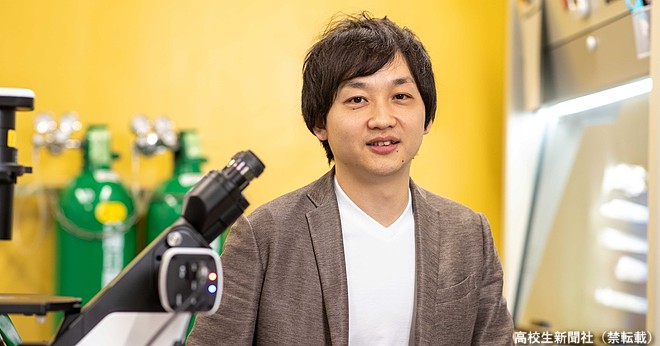
―医学に興味を持つようになったきっかけはありますか?
僕が小学3年生の時、当時39歳だった父が入院したんです。半年間、面会謝絶で、母はたまに帰宅してもすぐ病院に戻り、泊まり込みで父の看病をしていました。祖母が僕の面倒を見てくれましたが、割と多感な時期に両親がそばにいない状態が続きました。
―両親が不在の間、どんな思いを抱いていましたか?
父が死んでしまうかもしれない、そうしたら僕は高校にも行けずに働かなければならないのだろうか……子どもながらに不安な日々を過ごす中で、一人の人間の死は、自分の人生だけでなく、その人の家族や友人、同僚など、多くの人に大きなインパクトを与えるんだと実感しました。
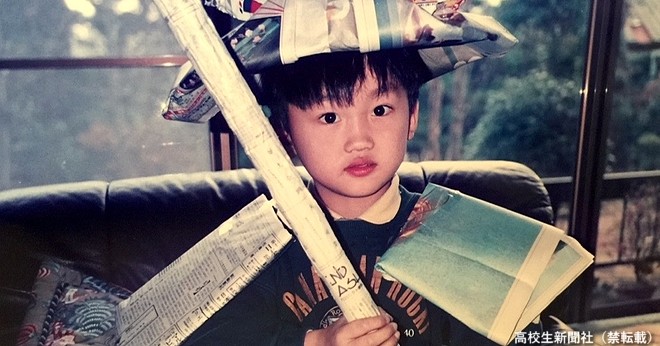
だからこそ、逆に、一人の命を助けられたときの影響も非常に大きい。命は決して一人だけのものではない。命を救う仕事は、ものすごく大きなインパクトを持つのだと、当時からひしひしと感じました。医療の仕事は本当に素敵だと思う気持ちが今につながっています。
幸い父が回復したことが、僕が医学部を目指したポジティブな要因です。医療に対しての捉え方が前向きになったと思います。
友人の父が肝臓移植、医療の現状を目の当たりに
―高校時代、すでに臓器移植へ興味を持っていたそうですね。
近しい友人の父が肝臓を患い、移植が必要な状況だったんです。その頃、僕は音大か医学部に進むかを考えていて、医療について調べる中で、友人からもよく相談を受けていました。
健康な人から肝臓の一部の提供を受ける生体肝臓移植を検討されていて、友人自身もドナー候補でした。親族の方から移植を受けたのですが、数カ月後に亡くなってしまったんです。肝臓移植や医療の現状を目の当たりにして、改めて深く考えさせられました。医療の現場に携われたらと。
吹奏楽部でサックスに熱中、365日ストイックに練習
桐蔭学園中学・高校で青春を過ごした。すべての時間を「吹奏楽部」の活動に捧げ、音大進学も視野に入れるほどだった。関東大会出場を目指していたが、結果は2年連続上の大会に進めない「ダメ金」。武部さんの心に大きなショックを与えた。
―どんな高校生でしたか?
先ほど音大進学も視野に入れていたと言いましたが、吹奏楽部でバリバリ頑張っていたんです。アルトサックスを吹いてました。割とストイックなタイプで、練習日は週4日でしたが、それ以外の時間も自主練に使ってました。朝6時半くらいから朝練をして、昼練もして。部活の後、カラオケボックスや地区センターの部屋を借りて練習……365日ですね。「部活はバリバリやるもんだ!」みたいな空気を出していたので、周りから見れば「突っ走ってる感じ」の人だったと思います(笑)

高校2年、3年になると、キャラクターが変わったかな。もともと30人程度の部員数を、僕たちの代で100人くらいまで増やしたんです。僕は副部長や木管楽器のまとめ役をしていたので、後輩も増えて、リーダーシップを発揮しなきゃいけない、チームを取りまとめないといけない意識が強くなっていきました。
バリバリやっている姿勢を押しつけると、みんなついてこれないんですよね。いろんな人の受け止め方や考え方に寄り添わないと、チームとしてはうまくいかないと意識するようになりました。バランスを大事にする姿勢が出てきて、周りからも「あいつ、変わったな」と見られていたのではないでしょうか。
あと1点だったのに…「ダメ金」で関東大会に進めず
―高校時代、一番頑張ったエピソードを教えてください。
部活以外何もないくらい、全てを捧げていました。僕の高校は、文武両道を掲げた男女別学の学校。吹奏楽部は特に学業との両立が重視される部活で、高校2年生で引退する雰囲気があったんです。だからこそ、高校2年は大事な時期でした。

吹奏楽のコンクールは地区大会から始まって、横浜市大会、神奈川県大会、関東大会、全国大会と、いわばはしごを登っていく感じ。僕たちは県大会を超えられるかどうかのレベルでしたが、チームはどんどん良くなっていく実感がありました。
高校2年の時の県大会は手応えを感じたのですが、結果は450点満点にあと1点足りなかった。いわゆる「ダメ金」です。金賞を取ったにもかかわらず、あと1点で関東大会に進めなかったんです。……もう、その心残りと言ったらありませんよ。
―悔しいですね。
煮え切れないので、「高校3年でもやろう!」と決め、部活を継続したんです。でも、結局うまくいかなかった。
最後の夏の大会は、本当に満を持して臨みました。指導してくれていた先生が、事務の仕事を兼務していたのですが、大会の時期に仕事が入ってしまいました。ですが、先生は「あなたたちとの夏の方が大事だから」と、僕らに付き合ってくれたんですよね。
先生もそこまで協力してくださったんですが、450点満点に2点差で関東大会にいけなかった。
「不条理な世の中だ」今も当時の記憶がフラッシュバック
―2年連続、僅差で関東行きの切符を逃したのは、やり切れません……。
「もう何なんだ、この不条理な世の中は」とショックでつらくて。人生のどん底と言っていいほどの心境でした。先生に対しての申し訳なさもありました。ですが、先生は「全く後悔していません。一生懸命取り組める道を選んだこの夏は、自分にとって一番豊かな時間でした。人生の中で、今目の前にある選択や行動を大切に過ごしてほしいです」とおっしゃってくれました。当時の感情や感覚が今でもフラッシュバックするほど、一番残っている思い出です。
―吹奏楽部の経験に対して、どんな思いが一番強いんでしょうか。
シンプルに一つの感情だけで片付けられません。「頑張ってもうまくいかないこともある」「でも次につながる学びもある」……いろいろな感情や考えが入り混じっている感覚です。全部うまくいくなんてあり得ない中で、できるだけ頑張った。でも結果は結果。
良いこともあれば悪いこともある。繰り返しながら生きる。うちのじいちゃんがよく言っていた「栄枯盛衰は世の習い」がしっくりきます。
「部活のために」勉強を頑張る
部活を引退し、受験勉強を始めたのは高3の9月だった。センター試験(現・大学入学共通テスト)まで約4カ月しかない。横浜市立大学合格までの受験生生活は、「順調とは言えない日々」だったという。
―高3の夏で部活を引退し、受験生モードに切り替えられましたか?
高校3年まで部活を続けたのに大会の結果がダメで、そのまま受験もダメだったら、これから同じように頑張る後輩がいなくなると思ったんです。なので、逆に「受験はマジで失敗できない」と、すぐに切り替えてスイッチが入りました。塾には行かず、ほぼ独学です。
―普段の成績はいかがでしたか?
普段から最低限の勉強はしていました。授業中に理解しきるスタンスでいたんです。中間・期末テストは成績上位でした。部活で後輩に偉そうな発言をしても、成績が悪いと説得力がないんですよね。「いやいや、お前勉強犠牲にしてるじゃん」「お前全然授業聞いてないでしょ」って思われてしまう。「僕は勉強も頑張りながら部活をやりたいです」と人に何も言えなくなってしまうので、話を聞いてもらえる存在になりたい。部活本位な視点です(笑)
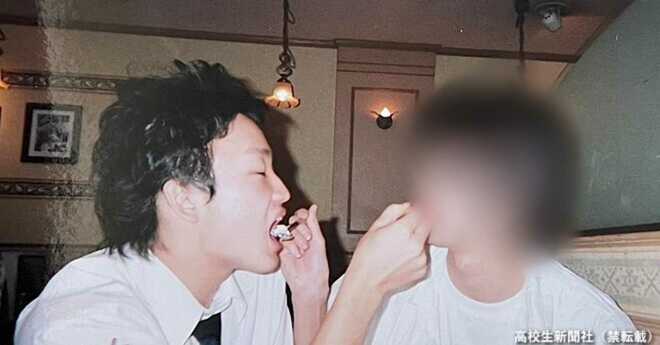
「入試は範囲が広すぎる…」ひたすら勉強漬けの日々
―受験勉強は順調でしたか?
定期テストと比べ、入試だとカバーする範囲がブワーッと広くなった。テスト範囲を短期間勉強する「瞬間風速」で生きてきたので、もう、全然通用しない(笑)。急に勉強ができなくなって、順位もどんどん下がっていきました。「受かるだろう」と言われてた大学が10月、11月の模擬試験でE判定でした。
―本番まで時間がない中、どう勉強していきましたか?
移動中やお風呂タイムなど、あらゆる時間を使って勉強しました。寝ないと僕は頭が回らないので絶対に睡眠時間は確保しました。高校に大学付属の大きな図書館があったので、開館時間の9時に行き、近くのミスドも使ってひたすら勉強し続けましたね。
ただ、間に合わなかった……(苦笑)。大丈夫だろうと思っていたセンター試験の結果は振るわず、英語が微妙。9割取るつもりが、リスニングがイマイチで8割に届かなくて。
慶応義塾大学医学部を志望していましたが、諦めました。僕の中では行けると思ってたレベルの私大医学部さえも不合格。補欠にもかかりませんでした。普段、僕よりも学力テストの点数が高くない人が普通に合格していて、友達からは「マジ? 武部、落ちたの?」みたいな反応で……。これはやばいな、と。
横浜市立大学に照準を当ててからは、めちゃくちゃ過去問をやりました。1日12時間以上は勉強して、一番自分を追い込み合格しました。

―受験勉強で得たものはありますか?
僕は国語が全然できなかったんですが、霜栄さんの参考書『現代文読解力の開発講座』 (駿台受験シリーズ)で勉強したらできるようになったんです。もともと活字が苦手で、本を読むのもつらく、現代文や小説は情報量が多くて理解不能。でも、この問題集はシンプルで、ひたすら要約をするトレーニングを通じて文章を分解しながら、早く論理的に構造を読み解く力を身につけられました。
文章の構造化やパラグラフリーディングの考え方は、今、論文を書いたり理解したりするときにものすごく役に立っていると強く実感しています。
「部員をまとめた」経験が研究者の「今」に生きる
現在は、日本とアメリカに6つもの研究室を持ち、行き来しながら研究。東京科学大学総合研究院教授、大阪大学大学院医学研究科教授など複数の要職に就いている。数々の研究チームをまとめ上げるリーダーシップには「吹奏楽部時代の経験が生きている」という。
―部活も受験もストイックに取り組んだ武部さん。高校時代の経験は、今にどう生きていますか?
部活でストイックに努力を積んだ経験は、今でも自分のレジリエンス(回復力。困難な問題やストレスなどにあっても立ち直る力)や、多様性の受け入れ方につながっているのは間違いありません。部活では、「純粋に音を楽しみたい」「お客さんを喜ばせたい」など、いろいろなモチベーションを持った部員たちを「同じ方向」に向け、共通の目標に寄り添いながら頑張ってもらわないといけない。モチベーションをどうマネジメントするかを常に考えていました。
当時使っていたスキルセットは、今、複数の研究室で研究をする上でのマネジメントやオーガナイズ(組織化)することにめちゃくちゃ効いています。大学以降ではなかなか学べないスキルなので、高校時代の経験が生きているところが大きいです。

―研究を進める上での組織運営に部活の経験がつながっているのは、おもしろいです。メンバーをまとめる上で何を意識していますか?
組織のおのおのが「頑張っている」「頑張りたい」と思えるのが何より大事。その人が何にワクワクし、何をエキサイティングだと感じるのかを考え、それをできる限り増幅してあげるのが基本形です。
例えば、研究者も、医師も、病院のお掃除をしている人も……それぞれ違うフィールドであっても、「社会を良くしたい」「患者を助けたい」はず。自分がどんな役割を担えているのかを実感し、楽しいと思えたり、モチベーションにできたりできているかを日々意識しながら接するようにしています。
他人任せにせず「自分自身」が決断しよう
―高校時代だからこそやっておくべきことはありますか?
「自分が」やっている、選んでいる、取り組んでいる。主語は「人」ではなく「自分」であってほしい。「○○ちゃんがやっているから」などと理由をつけるのは、絶対に良くない。何事も、自分ごととして、自分が当事者意識を持つ「オーナーシップ」を発揮するのが必須だと思います。自分が決めたのであれば、失敗しても成功しても全く問題ないし、むしろ失敗した方がいいと思います。自分の決断としてやるのが一番大切です。
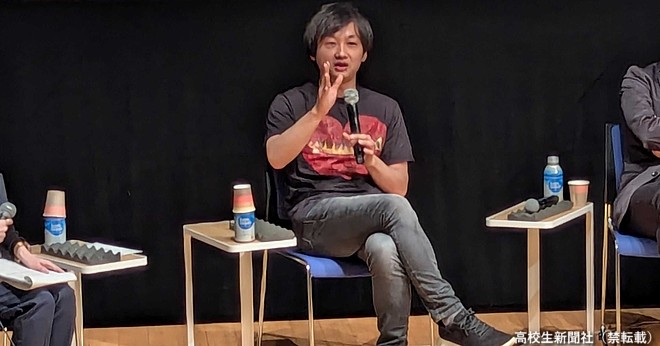
―高校生へメッセージをお願いします。
自分でリミットを決めないでください。そして、人に頼ってください。自分で「やる」と決めて何かを始めると、「自分にはできない部分」も多くあると気づきます。だからこそ、人に頼る力が必要なのです。「頼る力」は、成長していく中でとても大事な能力です。
先生に頼るのも一つの方法。自分ができる部分とできない部分を、意識的に緩急をつけて、自分がやる部分と人に頼る部分をよく考えながら進めていくと、本当にいろんな可能性が広がります。高校生は、これから何をしてもいい。エキサイティングな時間を楽しく過ごしていただけたらなと思います。
- たけべ ・たかのり 大阪大学大学院医学系研究科教授。東京科学大学総合研究院教授。桐蔭学園中学校・高校(理数科)を経て横浜市立大学医学部医学科卒業。博士(医学)。iPS細胞から「ミニ肝臓」を作ることに成功し、2013年、26歳で論文を英科学誌「ネイチャー」に発表。18年、31歳で東京医科歯科大学(現・東京科学大学)、横浜市立大学の「最年少教授」に就任。ベルツ賞など受賞歴多数。海外にも研究拠点を持つ。
「哺乳類がおしりから呼吸ができる」能力を発見、イグ・ノーベル賞受賞
関連記事:「なんか変」を見つけるって楽しい イグ・ノーベル賞研究者らが語った科学の魅力
 腸換気法の概要図。ブタは一定条件のもとで呼吸不全の症状が改善すると確認した(東京科学大学提供)
腸換気法の概要図。ブタは一定条件のもとで呼吸不全の症状が改善すると確認した(東京科学大学提供)
武部先生たちの研究グループは「多くの哺乳類にお尻から呼吸する能力があることを発見」し、2024年、イグ・ノーベル賞生理学賞を受賞した。呼吸不全の治療法開発のために生き物の呼吸法を調べていた際に、腸呼吸するドジョウからヒントを得た。イグ・ノーベル賞はアメリカの科学雑誌が始めたノーベル賞のパロディで、人々を思わず笑わせ考えさせてくれる研究に贈られる。日本人の受賞は18年連続となる。
【高校生記者の取材後記】
取材には高校生記者たちも同席した。武部さんの話を聞いて何を感じたか。
■自分からやる大切さを感じた
高校生時代を大人になった視点から俯瞰されていて、共感するところが多かったです。特に、吹奏楽の経験を元に「一人で突っ走らず他人のことをしっかり考える」視点を得られたのは、とても重要だと思いました。同時に、だからといって萎縮せず、「自分からやること」の大切さを知りました。誰かがやっているからではなく、自分がオーナーシップをとって実行することが大事だと感じました。高校生のうちに武部さんのお話を聞けてよかったです。(ゆお=1年)
■ポジティブに捉えなおす考え方をしてみたい
武部さんの「研究を楽しむ」精神のお話が特に心に残りました。私は、研究論文を書く際は正直「面倒くさいな」と思ってしまいます。ですが、武部さんは「論文は自分の研究の成果をほかの人に発表できる機会」とおっしゃっていて、このような考えの転換がとても大切だと思いました。一見ネガティブに思えてしまうことでも考えを反転させ、ポジティブに「リフレーミング」していこうと思いました。(Sowa=2年)
■私たちと重なる部分が案外あった
研究活動を多く行っている高校に通っています。イグ・ノーベル賞を受賞するような、成果を上げている研究者のかたと自分は「全く異なる存在」のように感じていました。ですが、高校時代の武部さんは部活に熱心だったり、苦手な科目があったり、私たちと重なる部分が案外あるんだなと気づき、特に心に残っています。(犬田=2年)