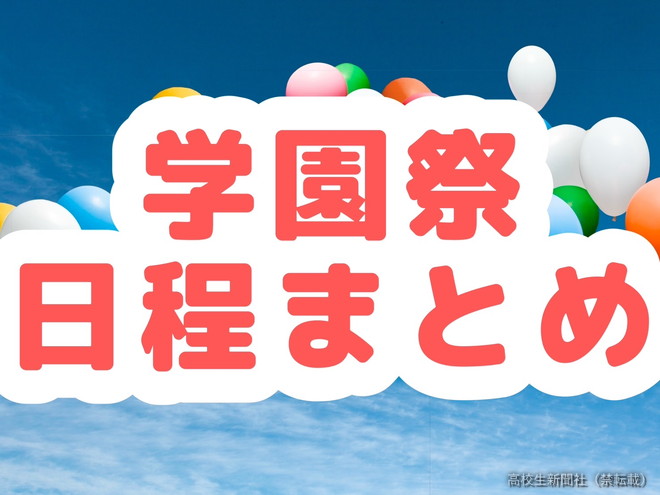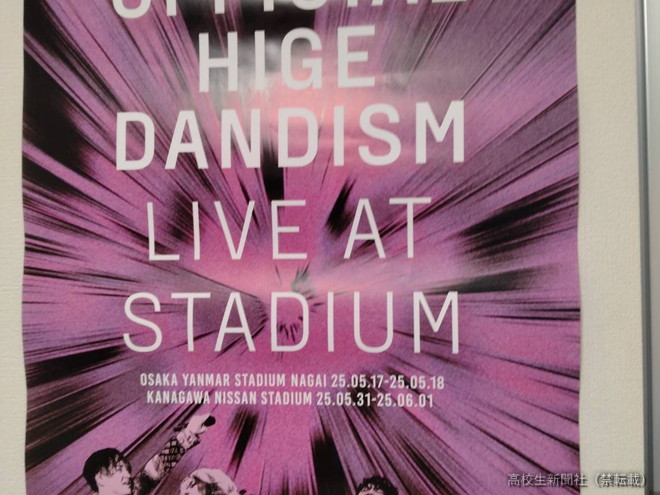石川県に暮らす松本心和さん(石川・穴水高校3年)は、2024年1月、能登半島地震に襲われた。少しでも情報を集めようとXを開いたとき、画面にあふれていたのは「インプレゾンビ」。偽の情報にだまされないために、ネットリテラシーを高める重要性を、第49回全国高校総合文化祭(かがわ総文祭2025)の弁論部門で訴えた。(文・写真 椎木里咲)
車内で被災、家に戻れず
2024年1月1日。松本さんは母親と一緒に、足をけがして入院している父におせち料理を持って行こうと、車で内灘町の病院に向かっていた。病院近くのインターを降りた直後、能登半島地震が発生した。車内はグルングルンと揺れたという。「車の外を見ると、電柱も大きく揺れていました」
車のテレビをつけるとすぐにニュースが入ってきて、かなり大きな地震が起きたと知った。父が入院する病院に行くと、大きな揺れによって病室のベッドが壁に張り付いていた。
つい先ほどまで車を走らせていた、のと里山海道は一部が崩落。能登半島にある家には戻れず、石川県庁近くの駐車場に車を泊めて、夜を明かした。

Xは「インプレゾンビ」だらけ
家には祖母と叔母が残っていた。電話をしても、能登半島方面は地震によって電波が途絶えているのか、なかなかつながらない。「なかなか無事を確認できず、不安でどきどきした」が、家族や友人の安否を確認するため、夜通しXやLINE、インスタグラムで情報を集めた。
Xを見ていると、不思議な投稿が目に入るようになった。「おばあちゃんが家の下敷きになって出られない」「土砂崩れで車に閉じ込められている」……切実な訴えのはずなのに、絵文字がついていたり、明らかに不自然な言葉が並んだりする投稿に、違和感を覚えた。のちにこれらの投稿は、閲覧数を稼ぐために「にせ投稿」を拡散する「インプレゾンビ」の仕業だと知った。
「信じてしまうから怖い」
「中には東日本大震災の津波の映像を使い、うその住所を載せて救助を要請する投稿もありました。当時は焦っているので、本当だと思ってしまうんです。信じてしまうから怖いし、インプレ稼ぎのために不安をあおる投稿は気持ち悪いです」
結局、祖母や叔母と連絡が取れたのは地震の翌日だった。

SNSは「1回疑って」
松本さんは、SNSの使い方に警鐘を鳴らす。「インプレゾンビの『エサ』は閲覧数。私たちが不用意に『いいね』を押したり、リポストなどの拡散に手を貸したりするのを避けなければなりません」
SNSを見るときは「1回疑ってみる」ことを心掛けているという。「引用ポストを見て投稿の真偽を調べたり、見たものを安易に周りに言ったりしないようにしています。若者を中心に、メディアリテラシーを確立させていかなければいけないと思います」