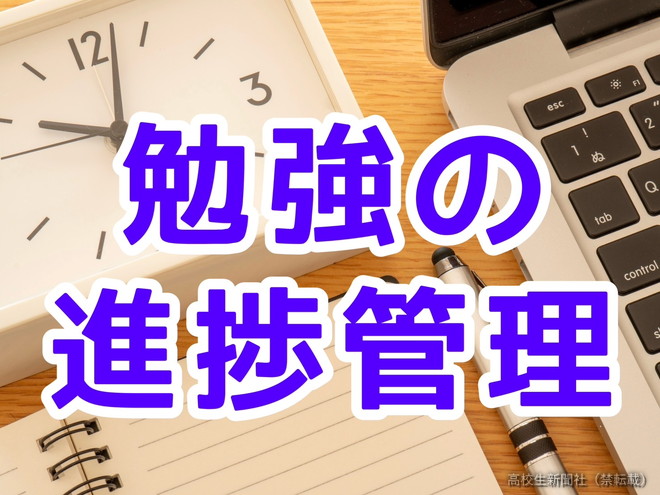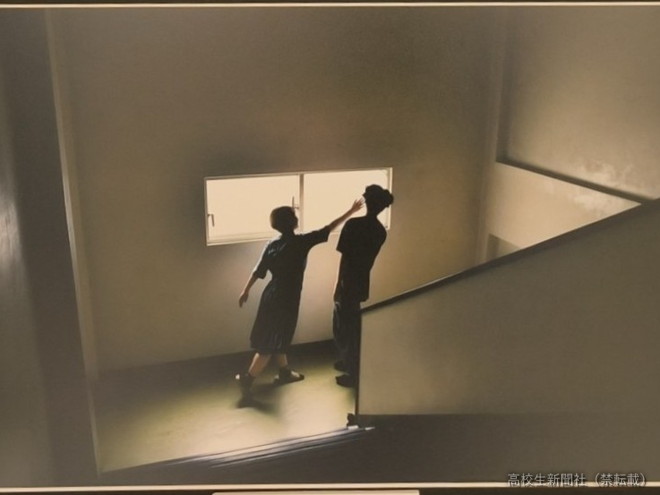さいたま市立浦和高校(埼玉)インターアクト部は、全国高校生英語ディベート大会(全国高校英語ディベート連盟主催)で7回の優勝歴がある強豪校だ。全国優勝までどんな努力を重ねたのか、部長の山川こころさん(3年)に聞いた。
英語ディベートを中心に活動
部員は47人で、発音練習や基礎トレーニングのほか、リサーチや試合形式の練習などを日常的に行う。「パソコンの発音練習ソフトを使って自分の発音を採点してもらったり、2人1組になってその場で出されたお題についてスピーチしたりして練習しています」(山川さん)
英語ディベートは、インターアクト部の目的である「円滑な国際交流」を達成するための手段の一つだ。

部員全員で徹底リサーチ
昨年12月、「第19回全国高校生英語ディベート大会」で優勝を果たした。同大会では事前にテーマが出され、準備を重ねて臨む。1チーム4~6人で登録でき、試合には4人がスピーカーとして出場する。
「日本政府は、原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か」をテーマに、新聞や論文などから徹底的に情報を収集。テーマに沿った資料を集める人や、模擬試合の準備をする人など、全部員が役割を担い、勝利に向けて準備を重ねた。「全員で網羅的に情報を集めて共有し、論の方向性を決めていきます。圧倒的な実力の差を出せるよう、とにかく量をこなす準備を大切にしました。私は新聞を取っている祖母にお願いして、原子力発電に関連する記事の切り抜きをもらいました。30~40記事くらい読み込みました」

ライバル校の論を分析
登録選手6人は、英語ネーティブの教員との会話試験や、顧問の浜野清澄先生との面接などの「部内選考」、後輩部員による投票によって決定。山川さんはスピーカーに選ばれた。6人以外の部員はリサーチャーとしての役割を担い、部員全員で論を練っていく「団体戦」だ。
「例えば、大会1日目、スピーカー以外の部員は他の高校の試合を見て情報収集し、次の日に当たる高校の論を徹底的に分析。自分たちの論の弱点も洗い出して、改善しました」
県大会は4位「合宿で意見を交換」
全国大会直前の11月、県大会では4位と、思うような結果が出ず議論の方向性に悩んだ時期もあった。だが、大会1週間前に校内の施設で2泊3日の合宿を行い、率直な意見交換を重ねた。「それぞれの論の弱点を話し合い、議論を練り直しました」
本番では、チームが一丸となれた。「みんなで最後まであきらめなかったから、全国優勝に届いたと思います」。困難な局面をチームで乗り越えた経験は、かけがえのないものとなった。
ディベートは「舞台裏」に支えられている
ディベートはスピーカーだけの競技ではない。資料を集める人、原稿を書く人、反論を考える人など、それぞれが支え合うことで強いチームが生まれる。「演劇と同じで、舞台裏の力があってこそ成立します」。互いを認め合い、補い合うチームワークが、全国制覇の原動力となった。
浜野先生は「今回のチームは団結力がとても強かった」と語る。「山川さんの学年は人数が多く、試合に出られない子がほとんど。それでも『チームのために』と、資料を集めたり、他校の分析をしたり……、全員が一丸となって優勝を目指していました」。
国際大会でも2勝
全国大会で優勝し、アジアを中心とした世界の高校生が出場する「アジア世界高校生国際ディベート大会2025(AWSDC)」への挑戦権を得た。7月に開催された同大会は、その場で出されたお題に臨む「即興型ディベート」だ。「通学中にBBCニュースのポッドキャストを聞いたり、家で英字新聞を読んだりして英語力を上げてきました」
世界の強豪チームと対戦し、圧倒される場面もあったが、着実に力を発揮。入賞は逃したものの、2勝を上げた。

「伝える勇気」が身についた
ディベートを通して身につけたのは、英語力だけではない。論理的に話す力、即興で意見を構築する柔軟さ、多様な価値観への共感力。そして何より、「伝える勇気」だ。
「英語ディベートは、挑戦するたびに自分を成長させてくれる舞台です」(山川さん)
-
市立浦和高校(埼玉)インターアクト部
1981年創部。部員数47人(1年生13人、2年生12人、3年生22人)。活動日は平日3日・放課後2時間、土曜日3時間。街頭募金、韓国の高校生との交流、海外の日本語教師との対話、OECDの専門家や駐日米国大使との意見交換、スタンフォード大主催のプログラム参加など、多岐にわたる国際活動に積極的に取り組む。社会問題への理解や国際感覚の養成にも重きを置き、全国模擬国連やSDGs子どもフォーラム、青年の主張大会などでも発表を重ねる。