私立大学では早ければ12月下旬から一般選抜の出願が始まる。第一志望校合格を目指すには、併願も含めた戦略的な出願計画が欠かせない。河合塾教育研究開発本部で主席研究員を務める近藤治さんに、出願時の注意点を聞いた。(野村麻里子)
併願先選びは「隔年現象」を意識して
受験校を選ぶうえで、併願校のセレクトは重要だ。「繰り返し説明しても、隔年現象を考慮せず出願する受験生が多いです」と近藤さんは指摘する。
隔年現象とは、前年に志願者数が少なく低倍率ならば翌年は倍率が上がるなど、志願者数が1年おきに増減を繰り返す傾向を指す。例えば、島根大生物資源科学部(前期日程)の場合、23年度は1.1倍だったが24年で4.2倍と急上昇。25年は1.9倍と低下した。典型的な隔年現象だ。
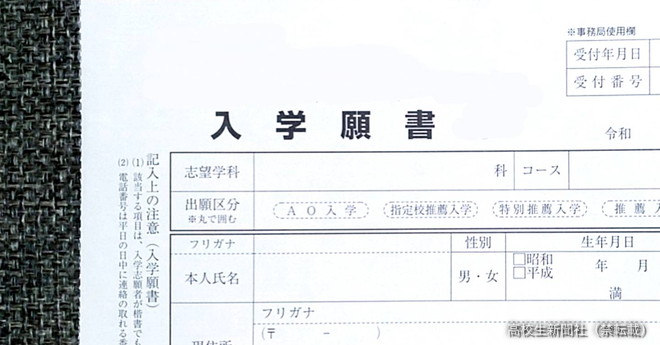
「高倍率になると口を酸っぱくしてアドバイスしても、前年で低倍率の大学・学部に受験したがる。反対に、前年に高倍率ならこぞって出願を避けます」
行きたい大学であれば、高倍率を避ける必要はない。だが、第一志望校以外の併願先として「A学部とB学部、どちらにするか?」と作戦を立てる上で「隔年現象を意識したほうが良い」という。
合格より「入学したい」大学か?
出願は、「合格するため」ではない。そう聞くと戸惑う受験生もいるのでは。忘れがちだが「真の目的は、志望する大学に入学すること」だ。「合格したい大学を選ぶのでなく、その先に入学したい大学なのかどうかを考えて出願作戦を立ててほしい」と強調する
河合塾の高卒生コースでは、合格を得ても手続きせず浪人する「合格浪人」が増えているという。「理由は人それぞれですが、合格しても入学しないのは、そもそも入学する気がない大学を受験してしまっているのです」
合格を手にしたい気持ちは自然だが、その上位に「入学したいか」という視点を持つことが欠かせない。「合格を目指して頑張ろうとはよく言いますが、入学を目指して頑張ろうとはあまり聞かない。でも、入学したいかどうか、自分の大学生活がイメージできるかが肝心です」と話す。










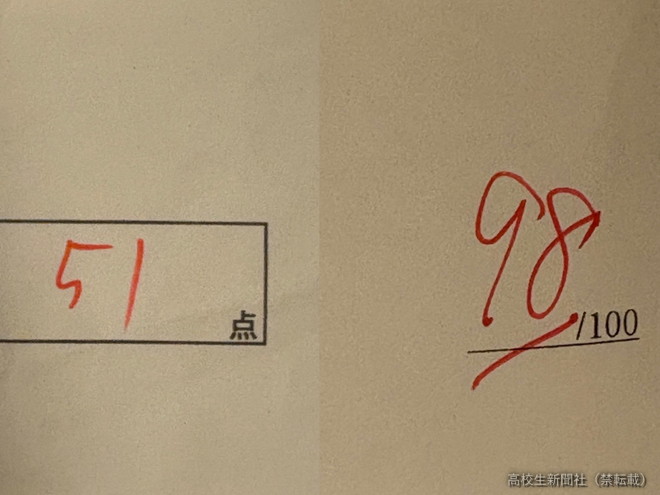








こんどう・おさむ
学校法人河合塾 教育研究開発本部主席研究員。河合塾入塾後、教育情報分析部門で大学入試動向分析や進学情報誌の編集に携わる。教育情報部部長、中部本部長などを経て、2021年4月から現職。情報発信や講演も多数実施。