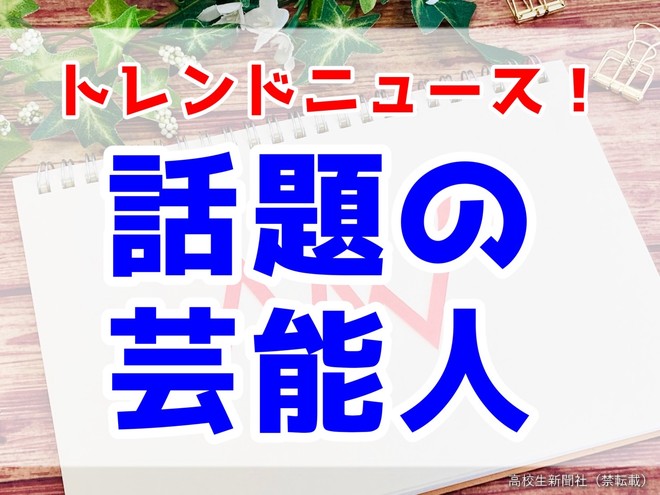西山拓斗さん(群馬・高崎高校3年)は、日本語、英語、手話……どんな言語でもコミュニケーションがとれる眼鏡を開発した。現実世界にデジタル技術を投影する「AR技術」を活用し、「誰もが自分の使いたい言語でコミュニケーションを取れる」世界を目指している。
「ほんやくコンニャク」が現実に
西山さんは、物理部での活動でARグラス「Bridglass(ブリッドグラス)」の開発に取り組んでいる。
Bridglassは、言語の違いや障がいの壁を越え、自然な対話を可能にする新しいコミュニケーションツールだ。メガネに搭載されたカメラによる顔認証で、相手を識別。使う言語や手話を自動で読み取り、音声やテロップで相手の会話が翻訳される。「専用のアプリで顔写真を登録し、アプリ上で『フレンド』になっている人を認識できます」

「ドラえもんの『ほんやくコンニャク』(食べればどんな言語でもわかるようになる道具)のように、誰もが自分の話したい言語を使ってコミュニケーションをとれる世界を作りたいと考えたんです」
言語も障がいも越えるメガネ
例えば、日本語話者と英語話者の場合、日本語話者の話した言葉をBridglassが認識すると、英語話者側には英語に翻訳された音声が流れたり、字幕のようにテキストが表示されたりする。「音声で聴くかテキストで読むかは自分で選べます」
手話にも対応している。「手話を音声やテロップにできる機能もあります。視覚障がい者向けに『目の前に誰がいるのか』を伝える技術も搭載。どんな言語の人でも、目や耳に障がいがある人でもコミュニケーションが取れます」

Bridglassは昨年11月、アイデアと技術を競う「U-22プログラミングコンテスト」(実行委員会主催)で経済産業省商務情報政策局長賞と企業賞(useful(日本事務器)賞)を受賞した。
原点は、小学生時代の友人との会話
物理部員として、平日は放課後1時間、週末は研究とプログラミングに時間を注ぐ日々を送っている。
Bridglassは、2年生の4月から開発を始めた。原点は、幼いころの体験にある。「小学生の頃に難聴の友達と話す際、思いをうまく伝え合うのが難しいと感じたんです」
友達は補聴器を使い、相手の口の動きを見て会話を理解していた。「僕は活舌が良くないし、早口だから、うまく話が伝わらない時がありました」
さらに、たまたま見たバラエティー番組で視覚障がい者と聴覚障がい者が「2人きりでは会話できない」という現実を知り「どうにかしたい」と思った。
高校に入ると物理部に入部し、「ものづくり」に関するコンテストに応募するようになった。「次のコンテストは『コミュニケーションの障壁をなくす』ものを作ろう」とアイデアを考え、顧問の岡田直之先生や企業のエンジニアとも相談しながら構想を形にしていった。
「すべての人に共通する言語があればいいのに、と考えていたんです。スマホの翻訳機能だと、一度スマホに話しかけて、画面を見せ合う必要があります。一方でBridglassはメガネ型なので、直接顔を見て、言葉を交わせるんです。対等に話しやすくなるはずだと考えました」
AI搭載の小型デバイス化に苦闘
最大の難関は、音声認識、手話認識、顔認証、翻訳といった複数のAIを小型デバイスでリアルタイムに動かす処理能力の確保だった。「スペックに限りがある中で、どう最適化するかが大変でした」。コードの無駄をそぎ落とし、処理の効率化を重ね、安定した動作を実現した。
開発中は、問題を一つずつクリアする「課題発見→解決→改良」のサイクルを繰り返した。「特に行き詰まったのは手話認識です。使ったシステムは『単語』でしか認識せず、『会話』ができませんでした」
行き詰まった時は、物理部を手伝ってくれるIT企業の社員に相談して、アドバイスを得た。「止まっても諦めず、一つずつ地道にやるしかないということを学びました」
「現実にできる」プログラミングの力
プログラミングを本格的に学んだのは高校に入ってからで、「物理部の先輩に教えてもらったり、本やネットで情報収集したりして知識を身に着けました」。
開発を通して、社会課題を発見し、技術で解決する力が育った。コンテストでは他の出場者の作品を見て、「こんな課題があるのか、こうして解決するのか!」と刺激を受けることも多い。
「プログラミングって、ドラえもんの道具みたいに、あったらいいなを本当に作れるところが魅力です」。誰かの役に立てるのが、この上ない喜びだと語る。

オリジナルのAIを開発したい
高校卒業後は大学に進学し、情報系の学部で学びたいという。「今使っているAIはすでにあるものを活用しているので、オリジナルの手話認識AIや音声認識AIを作りたいです」
今後はさらに改良を重ね、実用化に向けてステップを進めるのが目標だ。「まずは障がい者雇用をしている企業に使ってもらいたい。将来的には一般販売できればいいと思っています。社会に役立つ技術をもっと生み出していけるように、プログラミングの力を磨き続けたいです」