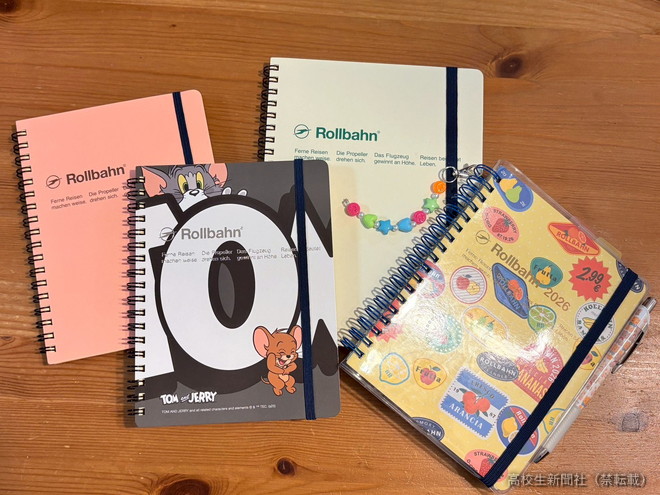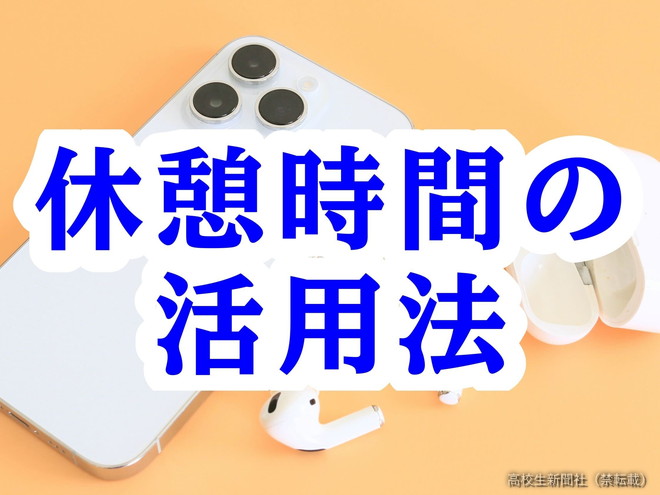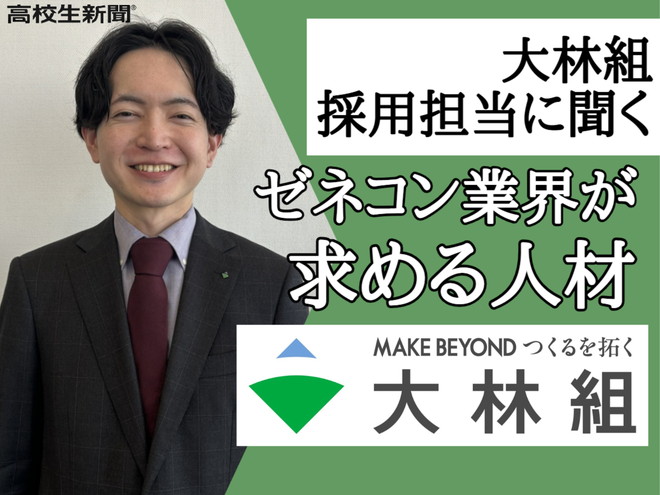この記事は公開を停止しました。
オススメ記事・特集
-

高1から理解するべき「入試制度」受験方式を決め打ちするのが危険な理由
2025.04.02
●大学進学ニュース
-

【年内入試アドバイス1】高3から志望校を決めて間に合わせるには 併願は何校?
2024.06.06
●大学進学ニュース
-

奨学金って何? 大学生の半数以上が利用、「自分は関係ない」と決めつけないで
2025.04.28
●学びサポート
-

【早わかり解説】「物価高」は若者の敵か味方か 経済を活発にするメリットも
2025.02.13
●学びサポート
-

再生医療で世界が注目、武部貴則先生 吹奏楽部に全て捧げた高校時代が人生の力に
2025.01.08
●学びサポート
-

あさのあつこさんが信じる「10代だけがもつ力」 新作では孤独を知る高校生が起業
2025.02.07
●エンタメ・トレンド
-

「気を抜け~」「人の目を気にするな~」やす子さんから10代に自然体のススメ
2024.04.19
●エンタメ・トレンド
-

「コミュ力おばけ」に聞いた友達付き合いの秘けつ 必要なのは才能…ではなかった
2025.03.14
●高校生ライフ