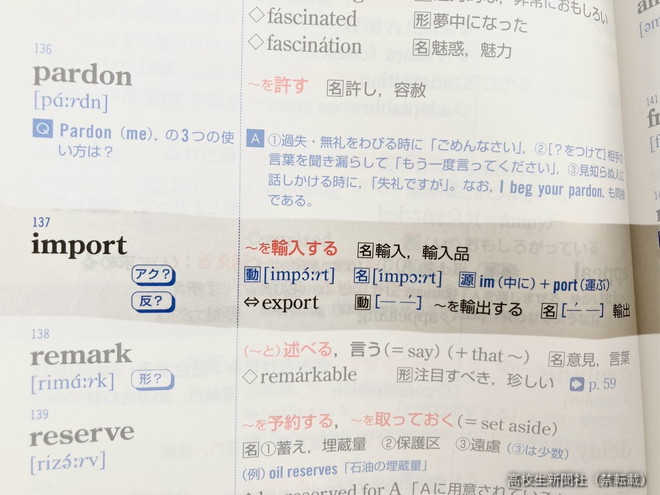小石川中等教育学校(東京)の6年生7人(高校3年生相当)は3月、高校生が筆記と実技で科学の力を競う「科学の甲子園」(科学技術振興機構など主催)で初の総合優勝を飾った。どうやって日本一を勝ち取ったのか聞いた。(黒澤真紀)
科学の精鋭メンバーで挑戦
筆記では理科・数学・情報分野の知識が問われ、三つの実技では毎年異なる分野やテーマで出題される。総合得点で順位が決まるため、あらゆる分野に対応できるチーム編成が重要だ。
長井琉晟(りゅうせい)さんが5年(高校2年生相当)の時、同級生の中からメンバーを集めた。中学生対象の「科学の甲子園ジュニア」で優勝した実力者など、「各教科の得意な人」に声をかけたという。長井さん自身も、日本情報オリンピックなど科学系のコンテストの経験者だ。チーム編成から準備に至るまで、教員は指導に関与していない。

「生物」の実技で1位になり、総合得点で1位に輝いた。都立学校が総合優勝するのは、科学の甲子園が始まって以来初だ。前回激戦の東京都予選で敗れた悔しさをバネに挑んだ今大会で、ついに頂点に立った。
放課後に集まり車体を改良
実技のうちの一つは唯一、事前にテーマが発表される。今回は回転するおもりに蓄えたエネルギーで走る「フライホイールカー」を操る工学実験だった。
放課後ほぼ毎日、土日のどちらかも朝から晩まで実験室にこもった。設計図を引き、部品を作りながら試行錯誤し、速さや安定性を考えながら、おもりを調整するなど細かな工夫を重ねた。
意見をぶつけ建設的に話し合い
作業が進むにつれて、何度も意見がぶつかり、空気がぴりつく場面もあった。冀思暢さん(き・しのぶ)は「お互い、正しいと思っているからこそ譲れなかった」と振り返る。
そんな時、冷静に場を仕切ったのが高井良紘斗さんだった。「それぞれ正しいけれど、今回はこうしよう」と提案するなど、メンバーの思いや言い分を整理した。重い空気がふっと軽くなり、また手が動き始めた。「お互いの人格と意見を切り分け、自由に言える雰囲気」(長井さん)があり、チームの強さとなった。
本番では、作ったフライホイールカーにボールを載せ、落とさないようゴールを目指した。「坂道や段差があるので、ボールがすぐに転げ落ちてしまうのが難しい」(赤澤佑月さん)。「車体上にボール用の坂を作り、ストロー素材で衝撃を受け流すなど細部にまで配慮しました」(長井さん)
大学レベルの実験書を読み込んだ
生物の実技はリーダーを日吉雪乃さんが務めた。日吉さんは昨年の国際生物学オリンピックで銀メダルを獲得している。当日の課題が分からない中、生物に関する過去問題を全て確認し、図書館で大学レベルの実験書を読み込み、問題の傾向を分析した。当日使いそうな実験器具「マイクロピペット」の操作の流れを頭にたたき込んだ。

テーマは「世界最大のウイルスを探せ!」で、手動PCRによるウイルスDNAの検出が課された。通常は温度設定を自動で行うが、この競技では98℃・55℃・72℃の温度管理を手動で行う。さらに、温度域ごとに決められた時間で試料を反応させることを30サイクル繰り返した。秒単位の温度調整は過酷だ。
亀田蒼太さんと冀さんがお湯の準備や実験結果の撮影などを担当し、日吉さんはマイクロピペッターによる精密な操作や試料の扱いに神経をとがらせた。「生物以外は得意じゃない。自分がチームに貢献できるのはここしかない。何が何でも高得点を」(日吉さん)と、プレッシャーをはねのけ最高得点を出した。
「得意」を生かして役割分担
物理の実技では、スマホなどについている加速度センサーを用いる実験を行った。手回しのロクロを使って、回転数を測定。その後、加速度センサーが見えない状態でどこにセンサーがあるのかを探し出した。
亀田さんが加速度の方向や変化を計算。物理の難問を軽々解く「物理の鉄人」だと信頼されている高井良さんが理論的な考察を担当。「暗算が得意で周りからスーパーコンピューターと言われている」という赤澤さんがグラフ作成や数値整理を担った。
日本代表としてアメリカへ
5月には、アメリカで行われたサイエンス・オリンピアドに日本代表として出場した。
大会を終えた今、それぞれが胸に抱く「これから」がある。中島瑞貴さんは「楽しさを知ったので、将来はものづくりの現場で働きたい」と夢を語る。「大学で生物を深く学びたい。いつかは大会の運営側にも立ってみたい」と話す日吉さんの目には、すでに次のステージが映っていた。
-
次回開催が来年3月に決定
第15回科学の甲子園全国大会は、2026年3月20日(金・祝)から23日(月)までの4日間、茨城県つくば市のつくば国際会議場およびつくばカピオで開催。出場できるのは、都道府県の予選で勝ち抜いた1チーム。6人以上8人以内で編成し、メンバーは高校や高専などに通う在籍通算2年未満の生徒で構成。競技形式はいずれもチームごとに分担・協働して取り組む構成で、筆記1:実技2の配点比で総合成績が決まる。詳細はホームページを参照。