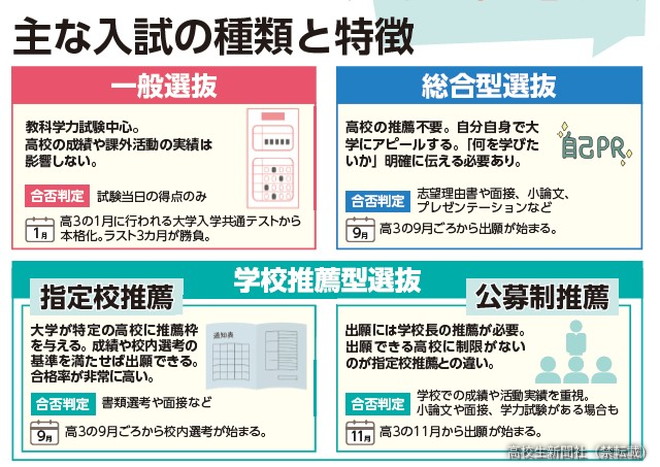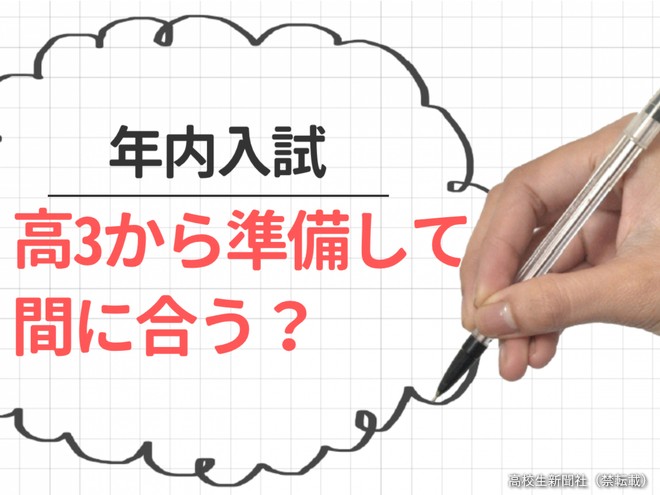超高齢社会の先に、多死社会がやってくると言われている。スーパーグローバルハイスクールの指定を受けた不動岡高校の3年生3人は昨年度、「医療や介護は誰のためのものか」について研究し、死について人々がどう考えているのかを調べた。

3人は昨夏に参加したクイズ大会で意気投合し、研究グループを作った。昨年12月、福島県で「死からの逆走」をテーマにしたフィールドワークに参加した。校長の模擬葬儀を行ったり、おむつをはいたり、介護食を食べたりして、人生の最期の過ごし方について考えた。
本来、自分でできることを他人にしてもらうのに違和感を覚えたという。「実際に棺おけに入る体験もしました。とても孤独に感じて……生きている間くらい、もっといろんな人と話したいと思いました」(武田敬吾君)
本人の意思が尊重されない

介護やみとりについて、家族など介護する側からの視点しか持っていないことに気付いた3人は、当事者である高齢者の視点から医療や介護の現状を調べた。統計によると、「自宅で死を迎えたい」と思っている人が多かった。また「みとり場所」「延命治療」「終末期の告知」についても、家族より本人の意思を尊重すべきと考えている人が多数だった。だが、死亡場所は圧倒的に病院で、主導権は家族が握っているケースが多いのが現状だ。
本人の意思決定が尊重されていない理由として、医療技術が発展し、自宅でのケアが難しくなったこと、終末期をどう過ごすか考え、意思を表明する機会が少ないことを挙げた。社会的な背景として、アメリカやフランスは「何も分からない状態で生き続けることは意味がない」という死生観だが、日本では不明瞭であることも指摘した。
死がリアルなものに
中村優希さんは、死を「実感がないもの」「現実逃避の手段」のように感じていたという。「何かうまくいかないと、気軽に『あー死にたい』と口にする人がいますよね。研究を進めるうちに『死って、本当にあるんだ。自分もその一途をたどるんだ』と思うようになりました。介護も死も一人ではできない。人とつながっているものだとイメージが変わりました」
小林穂乃佳さんは、死は「逃げたい、避けたいもの」、できるだけ死という言葉を使いたくないという気持ちがあった。研究を通じて「日本では死をタブー視する」ということを改めて実感したという。「実際に棺おけに入る体験をした際、ためらいました。(棺おけに足を)踏み入れて、死は自分にとって必ず訪れてしまうものと感じました」。その後、人工透析を中断した患者のニュースを見て、父親と延命治療の意思決定について話し合ったという。

もっと気軽に考えよう
3人は、人生の最期をどうするかを本人が決めるには、日ごろから周囲で話すことが必要だと感じている。死について考えること、思いを口にすることをタブーだと考えず、もっと気軽に死を考えるきっかけを作りたい。そんな思いを胸に、3人は文化祭の出し物として来場者に棺おけに入る体験をしてもらおうと計画している。
(文・写真 野村麻里子)