なんでも自分で決めたがるタイプがリーダーになると、独裁的になり、メンバーに不平不満が集まってしまいます。高校生から寄せられた体験談を例にして、リーダーシップ論に詳しい日向野幹也先生(共立女子大学客員教授)にワンマンにならない組織運営のコツを聞きました。(木和田志乃)
-
【悩み】部長が全部ひとりで決めちゃいます…
コーラス部なのですが、全体の決め事など、部長が全部ひとりで決めてしまうんです。以前コンサートの時に部長が休んでしまった際は、たまたま副部長に内容を共有していたので、事なきを得たけれど……。一人で決めた方が手っ取り早いのかもしれませんが、普段から考えを共有してほしいんです。(赤ネクタイ・高校2年)
相談しないのは「大きなリスク」
効率を重視するあまり、誰にも相談せずに「全部自分でやったほうが早い」と判断し、部長が段取りや準備を、副部長や部員に共有せず一人で抱えてしまう。独断が続けば、部員の不満が一気に爆発するおそれがある。後から部内の信頼関係にひびを入れかねない。
部長がコンサート当日に急に欠席したケースでは、副部長がたまたまスケジュールや段取りを把握していたため、対応できた。日向野先生は「たまたま共有していただけでは不十分です。常に情報を複数人と共有しておく必要があります」と語る。
リーダーが一人で情報を抱え込んでいる状態では、万が一の時に他の人が動けず、大きなリスクにつながる。
部員が「受け身」すぎる場合も
一方で、部員や副部長が「決定に従うだけ」の姿勢でいると、部長の負担が増え続ける。部員が何も言わなければ、部長も気付かないまま続いてしまう可能性がある。
「違和感があるなら、きちんと伝えるよう心がけてください。周囲が言われなければ、問題に気づけません」

スマホでのやり取りも活用しよう
忙しさやタイミングの問題で、話し合う機会を設けるのが難しい場合もある。しかし、LINEなどのツールを使えば、簡単に意見を集められる。「『自分はこう考えてるけれど、どう思う?意見があったら明日までに教えてほしい』と連絡の最後に書いておくと、意見が出やすいです」。オンラインでやりとりする時でも、意見や質問を歓迎する気持ちを表すだけで印象が大きく変わる。
情報共有が信頼につながる
部長が全体の動きを見ながら判断するのは当然の役割である。だが、部員に知らせないまま決めてしまえば、信頼は築けない。互いに情報を共有し合える関係があれば、どんな場面でも安心して行動できるようになる。
編集部にあなたの声が届きます
この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。













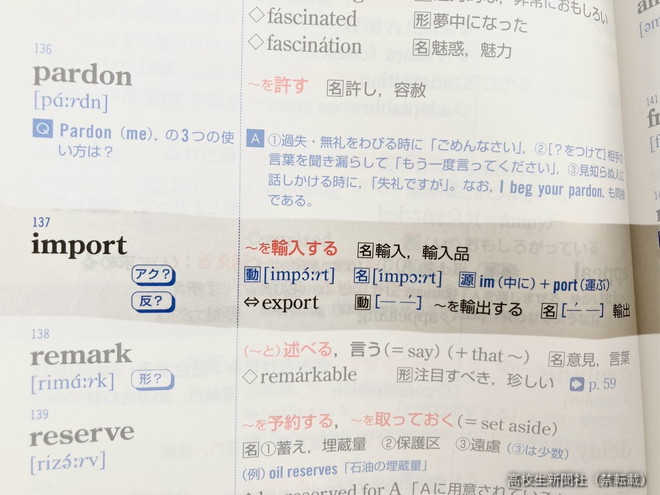





日向野幹也先生
ひがの・みきなり 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター教授などを経て、共立女子大学客員教授。東京大学社会科学研究科経済政策専攻第二種博士課程修了。 教育現場におけるリーダーシップ開発を専門とする。著書に『高校生からのリーダーシップ入門』(ちくまプリマー新書)など。