生徒の意見を代表して、先生たちに改善を提案する生徒会の仕事。先生と生徒の板挟みに苦しむケースが少なくない。実際に高校生から寄せられた悩みを例に、リーダーシップ論に詳しい日向野幹也先生(共立女子大学客員教授)にアドバイスしてもらった。(木和田志乃)
-
【悩み】先生と生徒の間で板挟みになりツライ
生徒会役員として活動しています。生徒から目安箱に校則変更に関する要望が届くと、役員の中で会議にかけて先生に提案するのですが、通らない場合も多いんです。仕事をしているのに、生徒からは何もしていないと思われていそうでモヤモヤします……。(ぺんね・1年)
結果よりも「経緯」を伝えて
投書に対して学校側から満足のいく回答が得られない場合、どのように対応すべきか。日向野先生は「信頼を得るには、結論だけでなく、結論に至るプロセスの共有が欠かせません」と語る。
校則の見直しなどに関する意見が届くと、生徒会では内容を検討し、教員に提案する。しかし、最終的に認められない場合も多い。生徒に結論だけを伝えると、「提案が無視された」「議論されていない」と受け取られ、役員への不信感につながるおそれがある。
「生徒は『結果よりも、どのような経緯で結論に至ったかを知らせてほしい』と役員に伝えると、役員も何を共有すべきかが明らかになります」と助言する。

過程の「見える化」が信頼につながる
「議事録を公開して、提案から結論に至るまでの流れを生徒にも共有すれば、誤解されにくくなります」。話し合いの日付、議題、教員からの回答を、生徒に示すだけでも、信頼を得やすくなる。提案が否決されたと場合でも、「反対された理由を共有できれば、生徒の納得感は大きく高まるはずです」。
仮に職員会議の議事録の公開を学校側が拒否する場合は、理由を文書にしてもらい、生徒側に伝えるよう交渉する方法もあります。
「反対でも提案する」姿勢が信頼を生む
役員自身が届いた意見に賛同できない場合もある。「納得できない内容であっても、生徒会で教員に提案をすると決めた案件は、責任を持って提案を進める姿勢が求められます」。役員が個人的に賛同していなくても、生徒全体の声を代弁しようとする姿勢を示せば、説得力が増し、教員側も受け止めやすくなる。
生徒と教員の「ズレ」をなくす工夫を
意見が通らなかったとしても、結論に至る過程を丁寧に伝えれば、「役員が何もしていない」と誤解される心配は少なくなる。「見える形で過程を共有すれば、結果が望んだ内容にならなくても、生徒の間には生徒会役員の活動について理解が広がります」。生徒と教員の間にある認識のずれを減らす働きも生徒会役員に求められる大切な役割だ。
編集部にあなたの声が届きます
この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。










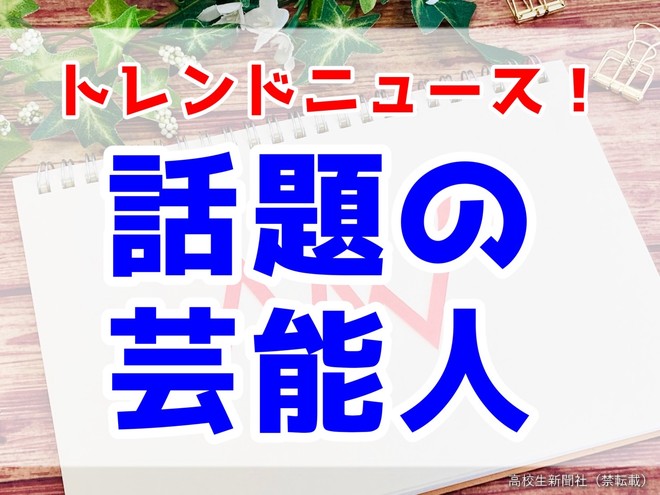


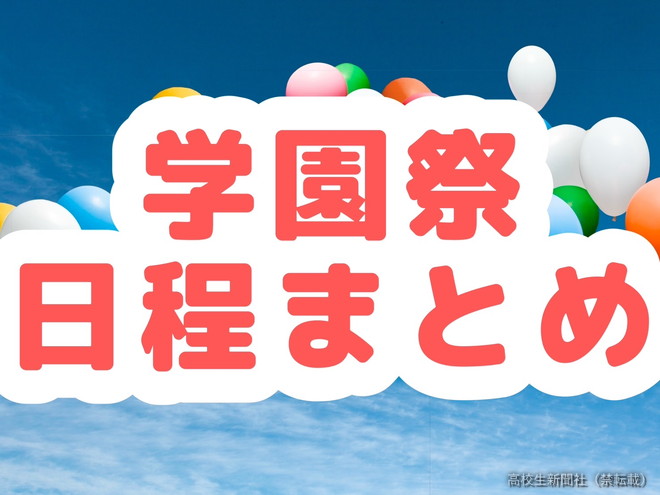





日向野幹也先生
ひがの・みきなり 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター教授などを経て、共立女子大学客員教授。東京大学社会科学研究科経済政策専攻第二種博士課程修了。 教育現場におけるリーダーシップ開発を専門とする。著書に『高校生からのリーダーシップ入門』(ちくまプリマー新書)など。