投票率の低さから「若者は政治に無関心だ」と言われる。実際、「政治は自分に関係がなく、影響もないもの」と考えてはいないだろうか。政治哲学に詳しい宇野重規先生(東京大学教授)に、政治に無関心でいるとどうなるのか、その先に潜むリスクについて聞いた。(安永美穂)
政治への無関心「悪くはない」けれど
―「政治には関心がない」「自分には関係ない」と思っている高校生は少なくありません。先生は「関心が持てなくても、『関係ない』と思わないでほしい」とおっしゃっています。
政治に関心がないこと自体は、悪いわけではありません。学校の成績、友達関係、家族……みなさんの人生にとって大切なことって、もっとたくさんありますよね。政治が自分にとって一番優先順位が高いかと言われたら、そうでもないのは当然です。
ただ、社会の仕組みが自分にとって不利に働いたり、やりたいことの妨げとなったりする可能性もあり、誰しもが政治と無関係でいられません。

政治は「納得のいく人生」に必要
―無関心の結果、何がもたらされるのでしょうか。
例えば、投票しなかった時に選ばれた政治家によって戦争が起こってしまった場合、「あのとき投票に行けば良かった」と思っても手遅れで、ダメージは自分自身に返ってきます。
無関心であっても罪ではありません。政治が一番大切な価値のあるものだとも必ずしも言えません。ですが、政治は間違いなくじわじわと皆さんの暮らしに影響を与えます。差別的な仕組みが導入されれば、やがてあなた自身の人生の選択に暗い影を及ぼすかもしれない。
納得のいく人生を送るためにはある程度は関わらざるを得ません。それならば「関係ない」と決めつけずに、可能な選択肢の中で何を選ぶべきかを考えてみてほしいと思います。
身近な人助けも「政治」になる
―人生に関わるものなのに、「政治は遠い世界の話に感じる」という高校生の声もあります。自分に縁がないものと感じるのと同時に、関心や意見がないから「黙っているしかない」と考える高校生もいます。
政治参加というと、投票のほかに、デモへの参加や署名活動などをイメージする人が多いかもしれません。でも、そのような狭い捉え方にとどめずに、身の回りの課題解決から始めてはどうでしょう。
「ウクライナの戦争やガザの虐殺を止めたい」といって行動するのも大きな政治活動ですが、身の回りで困っている人のために行動を起こすのも、立派な政治活動だと私は考えています。
―具体的にはどんな行動が考えられますか?
例えば、町内の清掃や雪かき、買い物に行けない高齢者の支援、貧困に苦しむ子どもを助けるための子ども食堂の運営など、地域社会における課題を解決するための行動はたくさんあります。困っている人の話を聞く、地域の課題を皆で協力して解決する仕組みを作るなど、自分にできることから始めるのが大切です。

【取材後記】自分が生きる未来は自分で作りたい
「政治に”無関心”でもいいけど”無関係”だと思ってほしくない」という先生の言葉が一番印象に残りました。政治は、私たちの生活に直結していて、社会をよくするための行動はすべて政治とみなせるから、だそうです。
投票率が低いのは、結果が出る前から政治を見限っているのではないかと思いました。ですが、投票率が5%上がれば、日本の政治は今と大きく変わるそうです。つまり、一票を投じる小さな行動からでも、社会を変えられる。自分が生きる未来は自分で作りたいと思えました。(高校生記者・あおいちご=3年)
編集部にあなたの声が届きます
この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。













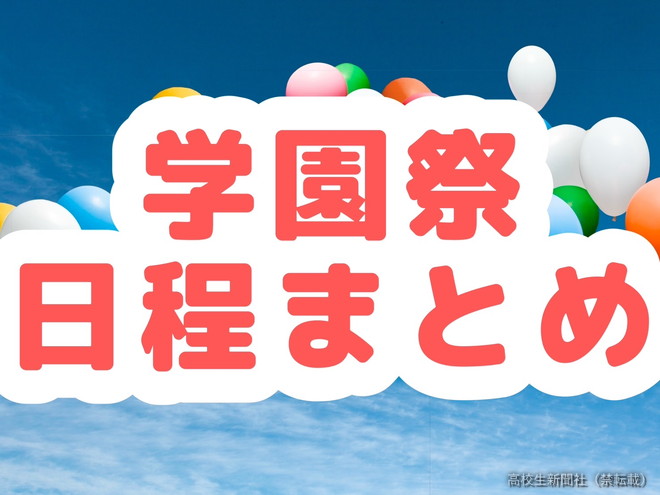
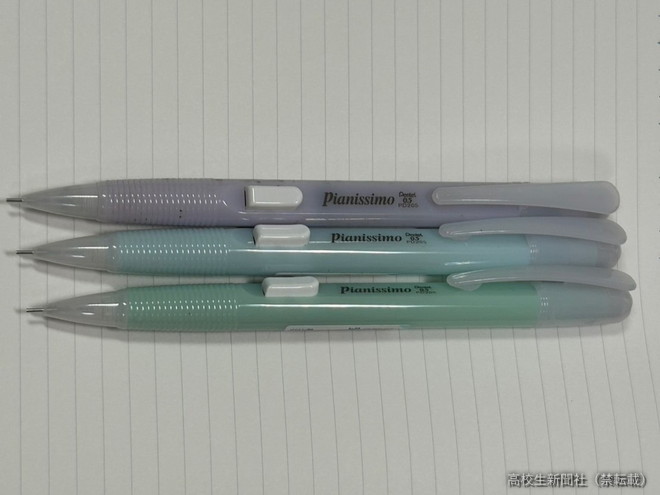




宇野重規先生
うの・しげき 東京大学社会科学研究所教授。2024年から同研究所長。博士(法学)。東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科博士課程修了。客員研究員としてフランスやアメリカに滞在した経験もあり、現在は東京大学社会科学研究所で所長を務める。専門は政治思想史、政治哲学。『民主主義とは何か』(講談社現代新書)など著書多数。