「民主主義」は、国民が自分たちの代表を選挙で選び、みんなの意見を聞き、できるだけ公平に決定を下すことを目指す仕組みだ。政治哲学を研究する宇野重規先生(東京大学教授)に、令和の今、メリットとデメリットの両面がある民主主義を続ける意義について聞いた。(安永美穂)
「みんなのことはみんなで決める」
―宇野先生は「民主主義は完全な制度ではない」とお話しされています。どのような意味なのでしょうか?
民主主義とは「みんなに関わることはみんなで決める」ことです。とはいえ、しばしば多数決が用いられるものの、多数派の意見が常に正しいとは限りません。少数派の意見が無視されたり、時には誤った決定が下されたりする可能性もあります。
さらに、話し合いによって合意を目指す民主主義はどうしても意思決定に時間がかかり、緊急事態が生じた際は迅速な対応が難しい場合もあります。このようにして見ると、民主主義は決して完全な制度とは言えません。それをより良いものしていくため、今後も検討を重ねていく必要があります。

代議制民主主義の歴史はまだ浅い
―民主主義の社会において、選挙はどのような意味を持つのでしょうか?
国民が選挙で選んだ代表者が政治を行う「代議制民主主義」は、19世紀に具体化されたもので、まだ160年ほどの歴史しかありません。比較的新しい制度であり、まだまだ改善の余地があります。今から約2500年前の古代ギリシャにも民主主義の考え方は存在していましたが、選挙ではなく抽選で選ばれた市民が政治に参加し、自分たちで物事を決めていたと言われています。
こうした歴史を踏まえて考えてみると、選挙のときに投票するだけで、本当に「みんなに関わることはみんなで決める」となっているのかは、考え直す余地があるのかもしれません。
当事者意識を育てることが重要
―「わかりやすい答え」「すぐに結果が出る仕組み」が求められる時代に、あえて時間のかかる民主主義を続ける意義とは何でしょうか?
民主主義は絶対ではありません。優秀な独裁者やAIが効率的に物事を決定してくれるなら、それで良いとする考え方もあるでしょう。しかし、自分に関係のある大切なことが、自分の知らないところでいつの間にか決まっていくような社会は、本当に良い社会だと言えるのでしょうか。
民主主義の最大の意義は、多くの人に社会について当事者意識を持ってもらう機会を提供することにあります。自分にとって大切なことを自分で決めたい、議論に参加したいという欲求を満たすのは、人間の尊厳を守ることにもつながります。
編集部にあなたの声が届きます
この記事はLINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。あなたもぜひフォローして、記事の感想や取り上げてほしいテーマ、生活の中の悩みや困っていることなどを聞かせてください。











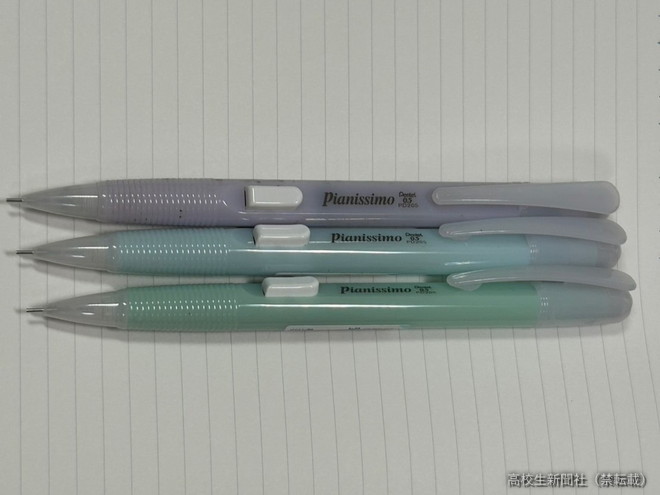

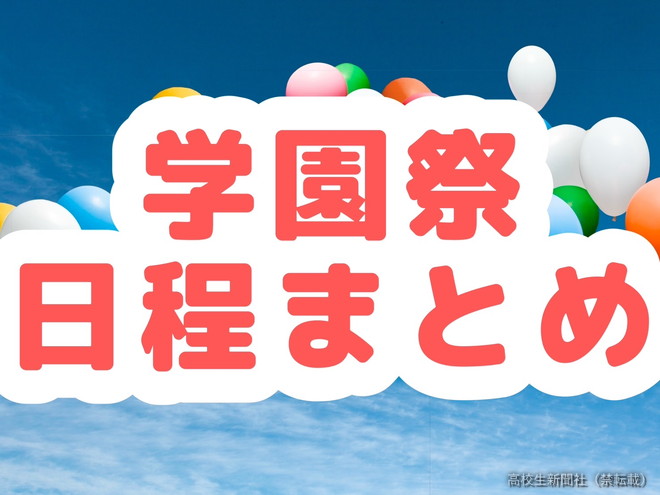





宇野重規先生
うの・しげき 東京大学社会科学研究所教授。2024年から同研究所長。博士(法学)。東京大学法学部卒業。同大学法学政治学研究科博士課程修了。客員研究員としてフランスやアメリカに滞在した経験もあり、現在は東京大学社会科学研究所で所長を務める。専門は政治思想史、政治哲学。『民主主義とは何か』(講談社現代新書)など著書多数。