「オープンキャンパスに行っておらず大学のイメージがつかめない」という声が寄せられた。総合型選抜や学校推薦型選抜など「年内入試」の増加にともない、高校1・2年のうちから参加するのが望ましいが、まだ志望校や志望学部が決まっていない人も多いだろう。オープンキャンパスの参加先をどうやって選ぶか、自分に合った大学かをどう見極めればよいのか、進路指導アドバイザーの倉部史記さんに聞いた。(安永美穂)
何も考えないでオーキャンに行くと…

総合vs単科、都心vs郊外…対照的な大学に行こう
―志望校や志望学部が決まっていない人は、オープンキャンパスでどんな大学を見に行けばよいのでしょうか?
総合大学と単科大学、都心の大学と郊外の大学、女子大と共学の大学というように、対照的な大学に足を運んでみましょう。複数の大学を見比べることで、自分にはどんな環境が合っているのかが見えてくるはずです。学部に関しても、文系・理系の両方を見てみることをおすすめします。
同じ分野でも大学により教育内容が変わる
―同じ名称の学部、同じ偏差値帯の大学は、どうやって比較すればよいでしょうか。
自分の夢を実現するために重要なポイントや、大学進学にあたって自分が特に重視しているポイントを事前に整理しておいて、その充実度を比較してみましょう。施設・設備などの教育環境、カリキュラムの内容や授業形式は、大学・学部ごとに異なります。
大学案内にはグループディスカッションやグループワークを始めとする「『アクティブラーニング』を実施」と書かれていても、アクティブラーニングは授業全体の10分の1程度で、ほとんどは大教室での講義ということもあります。「実際のところはどうなのか」をオープンキャンパスの個別相談でしっかり確かめましょう。
「大学・学部の学びの特色」をつかもう
―何を見たり聞いたりすれば、自分にあった大学選びに役立ちますか?
学食やサークルなどの「キャンパスライフ」に関することに目が向きがちですが、「大学での学びに関すること」を見聞きしてくることが重要です。施設・設備を見るときも「きれい」という感想で終わらせずに、「これを活用してどのような学びができるのか」を意識してみましょう。
例えば、「カリキュラムはどうなっているのか」「どんな先生や学生がいるのか」「その学部で学ぶ内容はどのような仕事につながるのか」といったことを個別相談などで確かめてみると、それぞれの大学・学部の学びの特色が見えてきます。
オープンキャンパスの参加レポートが高校の宿題になっている場合は、上記のほか、模擬授業を受けた感想などを書いてみるのもよいでしょう。
回り方のプランを立てよう
―マンモス校のオープンキャンパスは「来場者が多すぎてうまく回れない」「実際の大学生活が見えない」という声も聞きます。うまく回るには何を意識すればよいですか?
大型テーマパークに行くときと同様に、自分が知りたいことを検証するには、どこをどんな順番で回ればよいかを事前に調べ、プランを立てておきましょう。多くの大学では、当日のタイムスケジュールをウェブサイトで公開しています。模擬授業や先輩のトークセッションなど、時間が決まっているプログラムは事前に確認し、優先順位を決めておきましょう。
プログラムによっては、事前申し込み制で定員が設けられていることもあります。すぐに定員に達してしまうこともあるため、申し込みが始まったらなるべく早く申し込むことをおすすめします。
編集部にあなたの声を聞かせてください
この記事は、LINE公式アカウント「高校生新聞編集部」をフォローしてくれている読者の声をもとにつくりました。このアカウントでは、読者の悩みや疑問をいつも受け付けています。編集部から企画のためのアンケートや原稿募集をすることもあります。あなたもぜひフォローして、高校生新聞に参加してください。










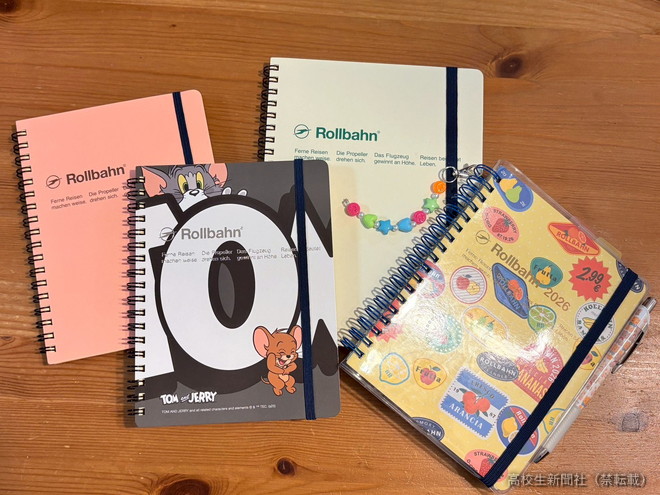



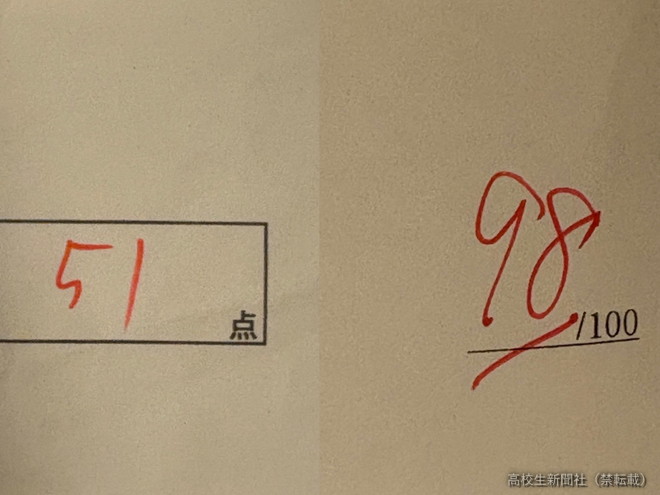




倉部史記(くらべ・しき)さん
進路指導アドバイザー、高大共創コーディネーター。追手門学院大学客員教授。高校生の「ミスマッチのない志望校選び」を支援するために、全国の高校での進路講演や高校・大学の教職員向け研修などを行う。著書『ミスマッチをなくす進路指導』(ぎょうせい)など。