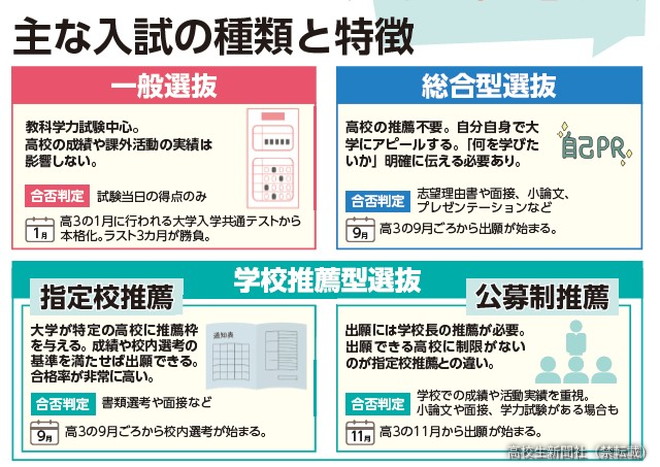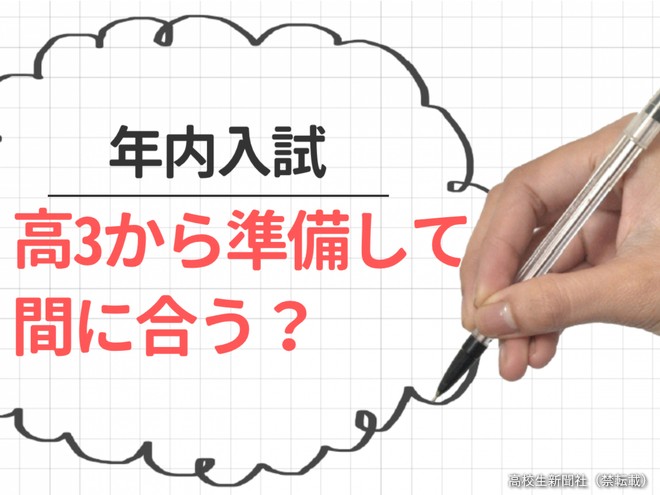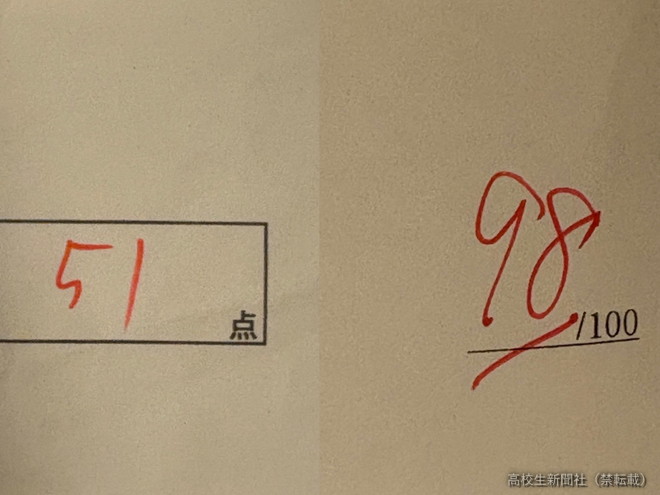当たり前にそこにいると思っていた。でもそれは当たり前じゃなかった……高校生記者のこころさんの祖父は難病にかかり、体が不自由になっていきました。祖父の姿をどう受け止めたのか、振り返ってもらいました。
おじいちゃんが10万人に1人の難病に
私はおばあちゃん子でした。毎年鹿児島の祖父母の家に帰省するたび、冷凍庫いっぱいにアイスを買ってくれたり、おいしいご飯をごちそうしてくれたり、毎日温泉に連れて行ってくれたりしました。とにかく私はおばあちゃんに甘えていました。

一方で、祖父とはそこまで仲がよくありませんでした。畑で泥遊びをして、汚れたままリビングへ行って叱られたり、食事を残してアイスを食べようとして叱られたりしました。無口で怒りっぽくて、「ザ・昭和の親父」という祖父に、異変が起きたのは3年前のことです。
「5年で車いす、10年で寝たきりだって」
中学3年生のとき、母にそう言われました。祖父は、原因が不明で治療法も見つかっていない、10万人に1人という筋肉が衰える難病にかかったのです。その年の冬休みに帰省すると、すでに祖父は体が不自由になっていました。お箸を使ってご飯を食べようとしても、手がふるえてうまく食べられませんでした。でも、それはまだ想定内のことでした。私は、これ以上進行しないでと願うしかできませんでした。
涙をぬぐうことさえできずに
そして翌年、高校1年生の夏休みに帰省し、祖父の姿を見て、私は思わず泣いてしまいました。祖父は幼児のように、誰かに手をつないでもらわないと移動ができなくなっていたからです。
「こころちゃん、おじいちゃんをお手洗いへ連れて行ってちょうだい」
祖母にそう言われ、私ははじめて祖父の手を取りました。指を動かすことができずグーのままでしたが、私はしっかりと祖父の手をにぎりました。それまで祖父と手をつないだことがありませんでしたが、その手は、本当にあたたかい小さな手でした。

2週間が過ぎ家に帰るとき、祖父は泣いていました。自分で涙を拭うことすらできず、ただただ目から涙があふれていました。そして、それがおじいちゃんとのお別れとなりました。
ありがとうを伝えられなかったから…
私はおじいちゃん子ではありませんでしたが、帰省したらいつもそこにいて、それがずっとあたりまえに続くものだと思っていました。私の結婚式までは長生きしてくれるのだろうと、勝手に思っていました。
あっけなく亡くなったおじいちゃんに、私は一度も「ありがとう」と伝えることができませんでした。厳しい昭和のおじいちゃんだったけど、叱ってくれてありがとう、いつも応援してくれてありがとう、私を愛してくれてありがとう…。お墓参りをするたびに、これからずっと伝えたいと思います。(こころ=3年)