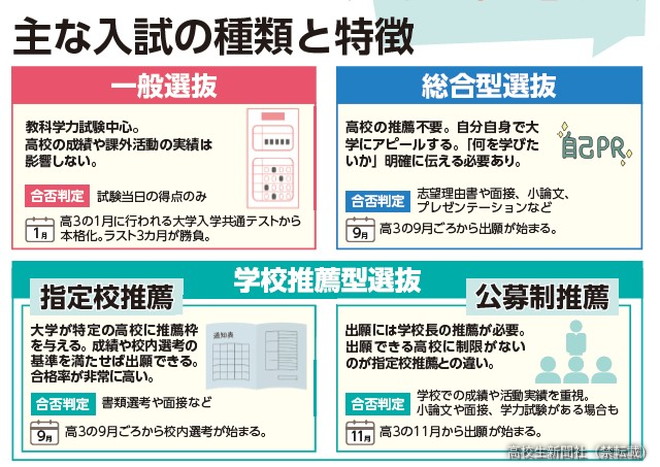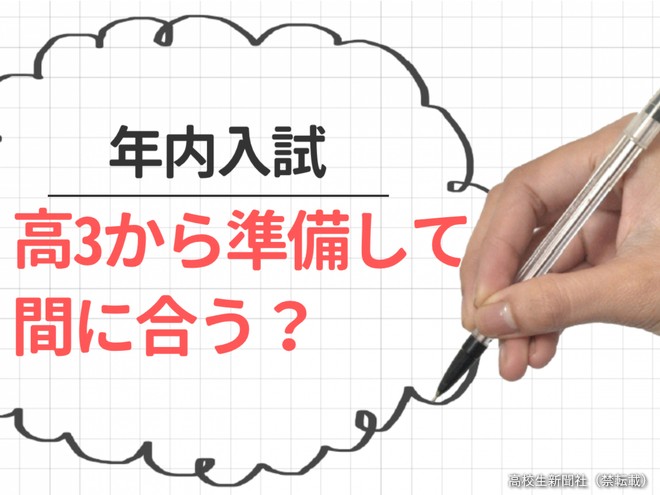最優秀賞 「ゴリラ・ゴリラ・ゴリラ」 埼玉県立蕨高等学校 二年 松本 昂之
前の席はゴリラだ。後ろの席もゴリラ。横を見てもゴリラ。ゴリラ祭りとでも称したものか。しかし連日これでは、祭りも何もない。この学校、この教室は以前人間で溢れ返っていた。皆同じ制服、しかし個々違う顔を持ち、日々は穏やかだった。その日常に満足していたかと聞かれれば即答はできない。けど。
「ホームルーム始めるぞ、席に着け!」
担任のゴリラが声を上げる中、改めて思う――こんな、奇妙な日常はいらなかった。
発端はおよそ一ヶ月前。通学の途中、ゴリラが発狂していた。小さな島ゆえ動物園など無い。まして、人語で泣き喚くゴリラなど普通いない。いれば確実にテレビで見世物だ。その見世物になるであろう物体が、其処彼処にいた。もしや自分は狂ったのかと本気で思い悩んだが、通りがかった同級生が慌てている様を見て安堵した。彼はまだ人間だった。しかし学校に行ってみると、生徒や教員にもゴリラがいた。人語も操る自転車にも乗る、しかし外形は紛れも無くゴリラ。皆で狂ってしまったのか、と認識を改めた時に、担任から報告が入った。曰く、島の住人の何割かが朝起きたらゴリラになっていた。狂乱、困惑、爆笑――反応は様々。島外ではこの様な話は無く、混乱はこの島に限られていたらしい。メディアに知られるまでは。夕方には、早くもニュースでゴリラパレードが放映された。島民、科学者を交え侃々諤々の議論――されど原因の究明など出来ない。兎に角島は殆ど封鎖状態になり、物資の補給以外で船が来ることは無くなってしまった。翌日、ゴリラが倍になっていた。翌々日で過半数、一週間で人の姿が消えた。
「欠席は無し、と」
そんな状況でも、学校は行われていた。人間の適応力とはかくも強い物か。暫くの間混乱は続いた――が、やがて混乱に疲れると、どうやら日常生活に支障は無いようだと皆判断し、各々の生活を再開した。この小さな学校も一ヶ月という時間が経ち、最早異を唱える者はいない。服は着ていないが、体毛に覆われているので大丈夫なのだろう。多分。
けれど。
「仁は今日も変わらずか」
隣の席に座る真太が声を掛けてきた。他にも数人、俺を見ていた。前はよく喋っていたのに、今では世間話さえろくにしていない。
「何でかね……」
特に言いたいことも無く、適当に答えた。
何故だ?この教室で制服なのは一人だけ――島で人の姿を保っているのは、俺だけだ。
「食い物も随分と変わったな」
午前の授業も過ぎて昼休み。普段通り机を合わせてきた真太が俺の弁当を見て呟く。食の嗜好も彼らはゴリラ化していた。真太はバナナを袋に入れ、弁当箱には簡素なサラダと虫類。細いバナナの皮を器用に剥き、勢い良く口へ放った。バナナを軸に食を進めていく。
「俺もいくらか変わったさ」
店に並ぶ食材も嗜好の変化に準じていた。
「しかし……未だ人間、ってどう何だ?」
前にどかりと座り、真太が問い掛ける。
「どう、って言っても……」
言葉に詰まる。忽ち――様々な感情や思考が頭から喉へと下っていった。
思いを音にするのは容易、けど明確な言葉にするは困難だ。そしてその行為が、彼にどんな事を思わせるか――分からなかった。
「特に変わりないさ。少し目立つだけでね」
結局、誤魔化す。その返答に興味も示さず、真太は生返事で果実を手に取った。
会話も態度も、日常の風景も変わった。俺の周りは妙に静かだ。不変を装い、けど時折俺を見る周囲の眼は以前のそれじゃない。友人に向けるものではない。珍しい物を見る眼――ずっと、どうにも変わらない眼だ。
帰りのホームルームも終わった。所謂帰宅部の自分、放課後の学校に用事は無い。金曜午後の空気の中、一人で短い家路を歩いた。
家は静かだった。両親は事件の起こる前、仕事の都合で島の外に出ていた。島民であっても中々帰らせてもらえないらしい。穏やかに過ごしているとは言え、自分たちは隔離されているのだ。学生服を脱いでベッドに転がった。今日も今日とて、平穏、長閑。異変など何も無いかのように誰もが振舞っている。俺は一人で、その日常に取り残されているというのに。そんなことを思った瞬間――現れた。日頃覚えた、奇妙な感触。
この感覚は何だ?ずっと苛まれていた。島が変わった日から――いや、周りが変わった日から。ずっと苛立っていた。おかしかった。俺は変わらずにいるのに、周囲が変わったせいで、まるで俺だけが異端な様だ。いや実際異端なのだ。この状況下、島内に仲間外れがいるとすれば、それは間違いなく自分だ。
「俺が、何かしたって言うのか」
思わず小さな声が漏れた。俺は何もしていない。悪い点など一つも見当たらない。けどこの感情は唐突且つ止め処無く湧いてくる。日頃隠した感情が、即座に心を埋め尽くした。
どうして自分が惨めに思える?どうして自分だけ疎外感を感じなければならない?
周りが自分を一歩引いた目で見るのが、堪らなく不快だ。自分だけ変われないのが狂おしく悲しい。こうした思いを何かにぶつける事も出来ず、只管奥の方へ押し込んでいるのも重苦しく辛かった。少し余裕ぶってみたって、この現状は変わらない。大袈裟と言えば大袈裟かもしれない。けれど、自分が腫れ物同然である事は分かりきっていた。真太だって、昼に机を合わせるのは最早惰性だ。教員の接し方さえ、何かが違う。こんな風に差が出来た事がどうにも恥ずかしく、思えば思うほど遣る瀬無かった。
何故?何で?どうして?
意味の分からない感情にありったけの疑問符をぶつけ、大きく寝返りを打ってみせた。
落ち着いてみた所で、何も変わってはいなかった。本棚は静か、自分は未だ人のまま、ベッドは少し乱れている。デジタル時計が夕方頃の時分を示していた。明日明後日――二日間の休みの過ごし方はもう決めていた。一歩も家を出ない。こんな状況でも期末考査の日時は刻一刻と迫っている。自らあの空間へ赴くくらいなら、家で問題集と睨めっこしていた方がマシだ。枕に頭を落とす。心労のせいか意識がぼやけてくる。妙に眠たかった。
重たい。何だこれは?頭が重かった。体も妙に重量がある。起こすのも一苦労だ。
眼を動かし時計を見た。月曜、朝の七時。淡々と過ぎた土日は知識で埋め尽くされた。今日から、また五日間の苦悩――身体を起こして、何気無く足先を見た。
見た。毛布から少しはみ出た、異物の脚を。黒みがかった、謎めいた物体を。直後、背筋に何かが走ったような気がした。その背筋もまた昨日までのそれはない。
それから溢れ出た物は複雑だった。少々の疑問、幾分かの衝撃。それらより多い、分かり得るはずの絶望感――そして更に僅かに大きい、安心感の様な物。遂にと言うべきか、今更と言うべきか――化けてしまった。霊長目ヒト科、ゴリラ属。いや、ゴリラと言う割には人間の頃の様な身体の自由も利くので、完全なゴリラではないのだろう。しかし洗面台で眺めた自分の姿は、紛れも無いそれだった。着ていた服は無残にも破れていた。
一先ず、日課となっていた弁当作りに取り掛かる。サラダを盛りながら、ふと考えた。皆はどう反応するだろう?元々目立つ奴でもないから、いつも通り平然としているかもしれない。或いは少しばかり騒いでくれるだろうか?どちらにせよ分かっていた。自分はもうあの視線を向けられることは無いと。あの異物に向ける、違和感と羨望と悲哀を浮かべた目つきを見ることは無いのだと。
「ははっ」
無意識に笑い声が零れた。鏡に映る器用なゴリラの姿が何故か笑えてしまった。この安堵の感が余裕を生んでくれたのだろう。身体は重くても、心は妙に軽やかだった。
廊下を歩きながら唾を飲んだ。妙に緊張する。短い通学路を駆け抜け、誰にも会うことなく学校へ辿り着いた。もうホームルームの時間が近く、既に皆教室へ入っているようだ。
この姿を窓に映すと、改めて楽しみになった。皆がどんな反応をするのか?どんな声が上がるのか?想像もつかない。緊張したまま教室の戸口に着いた。少し間を置いて、扉を思い切り、スライドさせた。
そして見た。ゴリラの黒毛――じゃない。
一面の白。柔らかホワイト。何だこれは。
「あー……廣野……」
担任が――面影も無い可愛げなヤギが自分を見ていた。教室が、ヤギ牧場になっていた。
二本足で直立するヤギ。器用に座るヤギ。蹄ばかり黒かった。『紙を食べるな』という張り紙が食われていた。俺は膝を落とした。
何故だ。何でゴリラからヤギなのだ。脈絡も無く。いや、何に変わったかはこの際問題じゃない。結局――俺はまた取り残されているじゃないか。追いついたはずなのに、奴らは先を行っていた。何故だ。知りようも無い。
ただ、一つ悟った。きっと俺は、今後も追いつけない。俺がヤギになる頃、この教室は犬か熊にでも成っているのだろう。一度遅れた人間が追いつく事は容易じゃない。時にはどう足掻いたって無理な物もあるだろう。こんな理解不能な現象ならば尚更。そこに良いも悪いもない、ただ特異な物として扱われ――或いは嘲笑される。社会とはそんな物か?
最早笑う他なかった。阿呆みたいに笑う。皮肉な事に、家での笑い声とよく似ていた。
—————————————————————————————————–
■優秀賞 「立待月(たちまちづき)」 神奈川・横浜市立東高等学校 三年 今井 静月
江戸は内藤新宿。その一角に「梅処(うめところ)」という名の一膳飯屋(いちぜんめしや)がある。老夫婦と一人娘で切り盛りしている小さな店だが、客足は良い。地元の町人や遠方の旅客たちが度々訪れては笑い声が絶えなく、大いに賑わっていた。
そんな飯屋の外で、お梅は水撒きをしていた。そっと溜息が漏れる。店の中は落ち着く様子はなく、客たちが帰る気配はない。「はあ」とまた溜息をつく。いつまでこの生活が続くのだろう。お梅は歳は十九。十七ぐらいで嫁ぎに行き、子を設けている娘がいる。だが自分は、ひたすらに茶を運び客の話し相手をし、両親の庇護のもとで暮らしている。しかし、この先のことを考えていないわけではない。それでも家を出られないのは、年老いた両親と、自分の名がついたこの店を置いて行けないからだと、胸中をごまかしていた。
一通り仕事が終わり、お梅は店の裏で片付けをしていた。すると、遠くの方から「ちりんちりん」と涼やかな音が聞こえる。お梅は「はッ」と手を止め外へ飛び出し、辺りを見回した。しばらくして、音の主はこちらへ瞬く間にやってきた。
「与七様、御苦労様です」
そう言うと、与七は白い歯を見せて笑った。
「あっしのような飛脚にそんな御言葉をくれるのは、お梅さんだけでございますよ」
「与七様……」
頬を赤く染めるお梅を見て、与七は頭を掻いた。そして「あッ、そうだ」と書簡を手渡した。
「ありがとうございました。……あの、今度ぜひ食べにいらしてくださいね」
それを聞いた与七は予想以上に喜んでくれていた。お梅はそれが嬉しかった。
与七が去った後、お梅は書簡の封を開けた。京太郎からであった。品川にある打物屋の若旦那である。お梅は何度吐いたか分からない溜息をした。内容は縁談のことだった。
このことは前々から話に出ていた。ひと月ほど前に京太郎が「梅処」に訪れて以来、幾度も書簡を寄越してくる。一度か二度目くらいでは冷かしだろうと思っていたお梅も、ここ最近では何気なく考え始めていた。試しに両親に話をしてみると「良かった。良かった」と喜ばれてしまった。だが、大事な愛娘が首を縦に振るまで、二人は何も言わずにいてくれているのを、お梅は知らずにいた。
仕事ではなく私事で与七がお梅のもとを訪れたのは、あれから四日後のことである。日はとっぷり暮れ、先客たちは既に帰ってしまい、与七は一人床几に座っていた。
「御待たせいたしました」
お梅は盆に白米と麦湯をのせて持ってきた。「おいしそうだ」と言って受け取ると、与七はがつがつと食べ始めた。お梅は然りげ無く傍に腰かけた。
「それにしても、今日はきれいな満月ですね」
食べ終えた与七は空を見上げて言った。
「はい……」
お梅も慣って見上げた。なるほど、確かにきれいであった。きんと冴え渡る夜空に、それは浮かんでいる。
「わたしたち飛脚は『十七屋』と呼ばれることがあるのですが、何故だか分かりますか」
与七に見つめられるなか考えたが、結局「いいえ」と返事をした。
「十七夜と掛けているのですよ。十七日目の月を『立待月』と言いましてね。それは立ち続けて待っていられるほど早く空に昇ってくるのです。そこから、出した手紙がたちまち届くという意味で、そう呼ばれるようになりました」
語り終えた後も、お梅はじっと見つめていた。こんなにも熱心に話す与七を初めて見たからで、目が離せずにいたのだ。
「いやァ、すいません。勝手にべらべらと」
与七はきまりが悪そうに頭を掻いている。
「誇りを持っているのですね。大切なことだと思います」
真面目に言うお梅を見て、与七は真顔になった。
「はい、そうです」
きっぱりと返事をした与七の口から、この後意外な言葉を聞いた。
「打物屋の旦那、大丈夫かな」
ほぼ呟きでしかない声量だったが、お梅は聞き逃がさなかった。
「何か、あったのですか」
言い様のない必死さを感じた与七は、町中で囁かれていることを話した。
「京太郎は狡猾な男だ」
そんな噂が飛び交っているというのだ。出所は不明。ただ、既に広範囲で出回っており、店の売り上げにも響いているらしい。このままでは家業停止も有りうるとのこと。
与七は続けた。
先の噂だけではなく、他にも巷では流れているという。
「京太郎は親を脅して、店を譲り受けた」
「堺の悪徳商人と手を結び、商売している」
といったことであった。どれも根も葉もないことであろうが、世間の口の戸は閉まらない。そう与七は言った。
お梅は困惑していた。頭の中で考えていた人物の名前であっただけに、驚きも一入である。しかしこの状況下にいるのにも関わらず、縁談の話をしてくる京太郎の心境を、お梅は無意識に心配していた。
「何だか御疲れのようなので、御暇いたします」
その声にはッと我に返った。
「ありがとうございました。またいらしてください」
慌てている様子のお梅を見て、与七は微笑んだ。
天上の月が、別れた二人を照らしている。与七と楽しく話をしていたあの時間が、お梅には遠く感じられた。
京太郎の話を聞いた日から二日後。与七が訪れてきた。客足が落ち着き、日が沈み始めた頃であった。
「あの、御勤めの方は……」
「いえ、今日は終わりました」
お梅は何となく重い空気を感じ取った。
「大事な御報告があって参ったのです」
二人は床几に腰かけたが、しばらくは互いに黙って座っている。お梅は与七が話し出すまで待った。
「打物屋の若旦那のことで」
突然の切り出しに、体がぴくッと反応する。
「どうやら店の方は大丈夫みたいですよ」
今度もまた、与七は丁寧に説明してくれた。
噂の出所が判明した。同じ品川に店を出しているもう一つの打物屋であった。そこの奉公人たちが町中を歩き回り、不埒なことを言っていると役人に言いつけた者がいて、やっと落ち着いたとのこと。理由は商売上の妬みで、客を引き離そうとしたためであった。しかし時間はかかったものの、京太郎の人望で何とか解決へ向かったというのが、この二日間で起こったことである。
「……では、今はもう」
「はい。多少の損失はあるようですが、元の売上げに戻り始めているみたいです」
お梅はふうッと胸を撫で下ろした。
「飛脚という仕事をしていると、町中の話題を耳にするのです。こうしてお梅さんに御話しできて良かった」
「ええ、ありがとうございました。噂を流した打物屋の方も、与七様のように誇りを持って御勤めしてくださればいいのですけど。そうすれば、今回のことも起きなかったかもしれませんのに」
染みじみと言うお梅を、与七は抱き寄せた。
「そう思ってくださるなら」
驚きで声が出せぬ相手に構わず、与七は続けた。
「そう思ってくださるなら、わたしと結婚してください。お梅さん」
はッと息を呑むと、体が硬直してしまった。
「えッ、あッ」と返事にならない言葉ばかりが出ていく。与七はそんなお梅を離れさせると、歯を見せて笑いかけた。
「冗談ですよ。安心してください」
ぽかんとしているお梅を見て、また笑った。
「あなたは京太郎さんの元へ行くべきです。そうでしょう」
そう聞かれ「わたしは――」と声を発したが、手で制されてしまった。
「もっと御自分の心に素直になってください。その決断が間違いではないことを、あっしが保証します」
与七は立ち上がって軽く頭を下げると、堂々とその場を去って行った。
お梅は呆然としていた。たった今の出来事を整理できずにいた。ただ、与七が言った京太郎への思いだけは確認することができた。
わたしはあの方が好きなのだ。直接話をしたことは少なくても、忘れることなく書簡で思いを送り届けてきてくれた。今は先の件で色々と大変であろう。明日会いに行って、手伝いをしてこようか。そんなことをゆっくりと考えていた。そして、お梅の目には涙が溜まっていた。何故泣いているのか、自分でもよく分からずにいる。ただ頭上の空では、いつの間にか昇っていた月が、お梅を照らしていた。
—————————————————————————————————–
■優秀賞 「退社時間」 広島県立呉三津田高等学校 二年 白石 幸太郎
秒針が12を指そうとする。傾いた日の光が射し込んで、部屋は橙色に染まる。
「課長、それではお先に失礼します。お疲れさまでした。」
私のその言葉に、課長である中山は苦い顔でこちらに一瞥をくれる。何が不満なのか。私の仕事は全て終わらせた。残業など私はしない。―午後5時、定時退社。―
私の生活の中に無駄があってはならない。無駄な時間、無駄な行動を省いてこそ私の人生である。
この建築物の五階に勤務する事務所がある。5階のエレベーターホールで待つ女性社員が数名見える。愚かな者たちだ。この時間は、上の階の事務所の社員も退社する時間。エレベーターが5階に着くころには、中は人でいっぱい。乗り込むことなどできないのだ。そうなれば、次のエレベーターが来るまで待たなくてはならなくなる。私はエレベーターホール手前の階段へと続く廊下を右に曲がった。階段は、15段×10降りることで一階へと辿りつく。無駄な時間を省くことができるのであれば、体力は惜しまない。そうこうしている内に、最後の15段へ来た。
「右側に出口。斜め右に5度の傾きに。」
そう一人でつぶやきながら、かけ降りた。これで約0.1秒の省略。流れる動きで1階のロビーへと出てきた。あと出口まで15メートル。とここで思はぬ事態が症じた。後ろから私の名を呼ぶ声。
「戸倉さん。これから俺たち飲みに行くんすけど、戸倉さんもどうですか。」
面倒くさい。なんて無駄な時間なんだ。
「いえ、今日は遠慮しときます。すいません、また今度。」
と笑っておく。冷たく突き放せば良いのだが、そうはしない。それこそ無駄な行動だ。私は彼らに一礼して駅へと向かった。
ホームで電車を待つ私。いらいらが募ってくる。しかし、便利な世の中になったものだ。最近はICカードをかざすだけで、改札を抜けることができる、私の味方なのだ。時間の省略、私の生きる糧。さすが大袈裟か。ホームで電車を待つ私。何もしない、ただ電車を待っているだけのこの時間は非常に腹立たしい。電車が来るまであと4分。
快速電車に乗り込んだ。火曜日の今日、この車両はすいている。この快速電車は、私の家の最寄り駅には停まらない。私は最寄り駅の一つ前の駅で下車し、自宅まで歩く。そうした方が、この快速電車の次に来る普通電車を待ち、それに乗って最寄り駅で降りて帰宅するより約4分20秒の省略が可能となる。私の二年の研究結果である。我ながらこの研究はすばらしい結果をもたらしてくれたと思う。この快速電車に間に合わせるために、私は歩幅を10センチメートル延ばした。
さて、私の降りる駅に電車が入った。この車両に乗っておけば出口が近・・・緊急事態だ。この近くの小学生の集団、修学旅行帰りか。あのわんぱく坊ずども、階段をふさぎやがって。はて、どうするか。このままでは、全ての計算が狂ってしまう。何も思いつかないままホームへ降り立ってしまった。しかし考える時間こそ無駄である。とりあえず階段へ足を進めよう。いっこうに前へ進もうとしない小学生たち。こうなれば、
「まもなく電車が参ります。黄色い線の内側までお下がり下さい。そこのスーツの方、黄色い線まで下がって下さい。危険ですので下がって下さい。」
駅員の声、たぶん私に向けての声だろう。たが、私は従わない。小学生の集団を避け、階段の奥のエレベーターに乗るため、私は黄色い線の外側を駆け抜けた。
やっとのことで駅を出た私。いつもより2分も遅れてしまっている。しかしあのまま小学生の波に乗ってしまっていたら、これだけの遅れじゃ済まなかっただろう。仕方ない、どこかで取り戻そう。ここからの道は、障害は多いが、何もなければ大幅に時間を稼ぐことができる。さあ、家に帰ろう。
駅から300メートルまで来た。ここまで障害はなかった。いつもなら自転車おばちゃん集団や、お迎え帰りの親子連れ集団、携帯とおしゃべりに夢中の女子高生達など大変だ。しかし、今日は何とも順調だ。あとはこの商店街を抜ければ、自宅もすぐである。だが、私は心得ている、今日が火曜日だってことを。毎週火曜のこの時間、この商店街はどの店も安売セールを行う。つまり、主婦の通りとなるのだ。だから、少し遠回りして帰った方が結果的に早く帰宅することができる。しかし、まだ気を緩めてはならない。これから通る道はまだ研究途中。何が起こってもおかしくはない。やばい、また女子高生か。
やっと家に着くことができた。最後の道、やはり研究が浅すぎた。結局、いつもの帰宅時間より8分も遅い。落ち込む私。
「はあ、少し気を張りすぎたか。」
ネクタイを緩めながら、グラスに水を注ぐ。
「どこにやったか、お、あったあった。」
私は薬を一気に飲み込んだ。精神科で処方された薬は全部で12。少々重度の精神病との診断。少々重度って何なんだ。
「と、この映像を見て分かるように、極度のマニュアル人間というのは、非常に危険な病気ということが多いのです。では、今日の講義は以上です。来週までに今日の講義のプリントを提出すること。」
多くの学生が講義室を後にする。
—————————————————————————————————–
■優秀賞 「夏郷」 群馬・東京農業大学第二高等学校 二年 堀川 恵理
祖母の家の最寄り駅に向かうための最後の乗り換えを済まし、空いていた隅の席へと腰をおろす。ごめん、母さん達無理そうだから一人でおばあちゃんのとこ行ってくれるかな。数時間前の母の弱々しい言葉がふと脳裏をよぎった。
時刻は午後十二時。正午。とてもお盆の午後とは思えないほどがらんとしている車両は、冷房の音が聞こえるほどの静寂に包まれている。緑ばかりが流れていく景色をぼんやりと見つめながら、僕は喉の奥に詰まっていた重い空気を吐き出した。乗り気しない、日帰り旅行である。目当ての駅まであと数十分といったところだろうか。特に眠気が襲ってきているわけではなかったが、僕は頭を壁に預け、ゆっくりと目を閉じた。
祖母のことを避け始めたのは小学校高学年くらいからだった。
当時の僕は年相応に反抗期真っ只中で、家族よりも友達が大事、遊びが第一と楽しんでいたときであった。遊び呆ける自分を指摘する両親に反感を抱き、何度も衝突したし、疎ましくも思っていた。それは祖母も例外ではない。毎年の恒例行事としてお盆に家族で祖母のもとを訪ねたときも、母よりも厳しいその物言いを腹立たしく思った。初めて祖母に反抗した。以後数年間祖母との接触は極力避けている。行かない年もあったし、行っても遠まわしな嫌味を言い言われるような関係だ。今となっては反抗期の自分の考えや言動が馬鹿馬鹿しく思え笑い事で済ませるほどなのだが、祖母を避けてきた数年間の溝は馬鹿にはできない。何でこんな大事な時に夏風邪なんてこじらすのか。両親が恨めしかった。
次は―。アナウンスが告げた駅名に、僕は目を開ける。心の調律は済んだかい。内の自分に語りかけ馬鹿らしさに息を漏らした。下車の準備を始める。徐々に速度を落とした電車は、都会とは縁のないような小さな駅に停車した。手動の重い扉を開き、その瞬間のむせかえるような暑さに眉をひそめる。
改札を通過してすぐの待合室に、ただ真っ直ぐ前を向いて座る祖母の姿を見る。待つ人も、待たす人も、他にはいなかった。祖母は目を細め僕を見て立ち上がると、
「よく来たね。」
それだけ言った。表情に変化は無い。僕も軽い返事だけする。とても年に一度会うか会わないかの身内には思えないほど、冷え切った再会だ。やっぱり、溝は深い。
何も言わずにさっさと家に歩き出す祖母の斜め後を歩く。記憶の中の祖母よりも少し、腰が曲がった気がした。
駅から歩いて十五分ほどの大きな一軒家の扉を開き、祖母に続いて中に入る。昼間だと言うのに薄暗い廊下を抜け、居間に荷物を置く。祖母は台所へと消えていった。座布団に座り、畳に手をつく。冷房はついていないが自然と建築のつくる冷涼感がとても心地良い。背後の縁側に吊るされた風鈴の儚げな音色は、何度来ても変わらぬ不思議な安心感をもたらしてくれた。
「お昼はそうめんでいいかい。」
台所から祖母が少し大きな声で尋ねる。
「うん。ありがとう。」
体制を立て直す。同じくらいの声量で答えた。そうめんはあまり好きではないけれど、もうお昼もとうに過ぎていたし、ほかに返事の仕方も思いつかなかったし。
家で寝込む両親に、メールで到着の報告をする。返信はない。寝ているのだろうか。することもないのでそのまま携帯電話で時間を潰すことにした。かと言って特にやることもないのだが、気休め程度にはなるだろう。この家の雰囲気は心地良いし、嫌いではないのだが、時間がゆっくりと流れる気がしてなんとなく頭が重い。街の喧騒も、雑踏に紛れる緊張感も、ここにはない。静かにすべてを受け入れるような、寛大な空気がここにはある。違う世界のようだった。そして、そこに住む祖母との距離こそ世界が違うかのように遠いものだ。
一杯に入れられたそうめんが透ける、ガラス製の大きなボウルをテーブルに置き、祖母は再度台所に戻る。めんつゆの容器と箸を持ってきてテーブルに置くと、僕の相向かいの座布団に座った。僕は携帯電話をポケットにしまいこむ。いただきますと言ったのは同時だった。亡き祖父よりも厳格だという祖母は、食事中の必要以上の会話は品がないと嫌う。そのせいあって流れる空気の重さが増したような気がした。お互い無言に、ずるずるとそうめんと啜る。
「食べ終わったら、墓参り行くからね。」
「えっ。」
唐突に祖母が言うものだから変な声が出てしまった。チラリと祖母を見たが、案の定目線は合わない。表情一つ変えることなく、またそうめんを口に運ぶ。ああ、はい。墓参りね、うん。
まさかあの厳格な祖母が食事中に言いだすとは。チラチラと祖母の様子を覗いながら、慣れない気持ち悪いようなむず痒いような感覚に襲われる。特に何か言うわけではないけれど。
あれ。ちょっと待て。
祖母はひょっとしたら、
「慌てず食べなさいな。」祖母の言葉に思わず固まる。
僕に気を遣ってくれている?
見渡す限りの畑と小山。緑が青々と生い茂り、セミたちは短命を削って必死に鳴く。都会の喧騒となんら変わりのない音量だが、騒々しくは思わない、むしろ心地よいくらいの自然の不思議に魅せられる。僕らのほかに、小さな墓地に人はいない。祖母の首元の汗が、日光に反射してきらりと光った。太陽は真上より西へ着々と向かっている。祖母は墓石を丁寧に磨き、僕は線香と花を添えた。亡き祖父の墓だ。物心つく前に病気で早くして他界してしまった。厳格で、勇ましい人だったと聞く。祖母が僕に手厳しくあたるのは、そんな祖父の意思を継いだつもりなのかもしれない、なんて昔から考えていた。目を閉じ、墓石に手を合わせる。祖母はぶつぶつと祖父に語りかけているようだった。先に目を開け、祖母を見る。柔らかい表情が、何年も見ていない記憶の中の祖母の笑顔を思い浮かばせた。
二人黙って身内の墓を転々とし、一人一人に両親が体調不良で来られないことを謝罪する。帰路につくころには、景色はぼんやりと薄紅色に染まり、影が長く伸びていた。定位置のように祖母の斜め後ろを歩きながら、やっぱり腰が曲がった気がするなあと考える。祖母が気を遣うのは気のせいだったかな。結局墓参りの最中言葉を交わすことはほとんどなかった。でも少し、微かに。やっぱりなんだか気持ちが悪い。理由も分からないままに。
「ばあちゃん。」
祖母の後ろ姿に声をかける。歩みを止めることもなく、一声かけて僕は黙り込んでしまう。何だ。僕は何を言いたいんだろう。
「さっきじいさんがね、こう言ったんだよ。」
特に驚くこともなく、祖母の紡ぐ言葉に聞き入る。
「『孫の成長を褒めてやれないのはそりゃあ悲しいことだ。お前が代わりに、おれの分まで厳しくも優しくもしてやれ』。」
夕暮れを告げるヒグラシの鳴き声が響く。祖母の言葉は、それでもしっかりと僕の耳に届いていた。
「『孫が立派に育ってくれて嬉しい』って。」
この人は、どうも遠回しにものを言うのが得意らしい。
歩みが止まることはないけれど、さっきより少しゆっくり歩いている気がした。時の流れのせいだろうか。ふっと笑いが漏れる。
「ばあちゃん。」
返事のない背中に語りかける。僕が祖母に言う言葉なんて決まっている。
「それツンデレって言うんだよ。」
いつだって嫌味だ。
空には星が瞬きだしていた。日中の蝉の大合唱はいつの間にか幕を下ろしていて、風鈴の音に似た鈴虫の演奏が始まっている。交わした言葉こそ少なかったが、なんだが大きな何かを感じることができた気がする。駅についたとき、一時間に一本ほどの電車がくるまであと数分だった。隣を歩いていた祖母の顔を見ずに、じゃあ行くねと告げる。ひと呼吸おいて、気をつけて帰りなさいよという返事が返ってきた。踵を返し、祖母はまた何も言わずにもときた道を歩み出す。まったく誰の腰が曲がったとういのか。見慣れた祖母の後ろ姿は、記憶の中のそれとなんら変わりのない凛としたものだった。
「ばあちゃん!」
歩みを止めないその影に、孫らしい挨拶をひとつ。
「また来るね!」
その背中から、返事はなかった。
切符を買い、がらんとした電車に乗り込み隅の席に腰をおろす。静寂と冷房で冷え切った空気は清々しい。喉の奥に詰まっていたかのような空気を吐き出し、また大きく吸い込んだ。暗くなったために車窓から外の景色はのぞけない。鏡のように映った自分の姿がそこにあるのみだ。
気乗りしない、日帰り旅行だったな。
僕は頭を壁に預け、ゆっくりと目を閉じた。
—————————————————————————————————–
■佳作 「手紙」 東京・鴎友学園女子高等学校 三年 深澤 径子
『久しぶり。口頭で報告してからだいぶ経つけど、このたびようやく結婚することになりました。式は親族だけで簡単に済ませることにしちゃった。キミには特に謝らなきゃね。スピーチ頼んでたのにごめん。結婚報告も兼ねてみんなに日頃の感謝をしようという話になり、今こうして手紙を書いています。
キミと初めて会ったのは高校の時だったね。私は文芸部の部長、キミは副部長。部員二人の弱小部だったけど、それでも毎日飽きずにお互いの作品を読み合って、高めあって。何をするにも全力だったあの頃は、世界が今よりずっと鮮やかだった気がします。私はキミの作品独特の空気感が何よりも好きでした。
「夏」
恋に破れたその日、空はどこまでも青く高く、地面にへばりついた僕の影を惨めに浮かび上がらせていた。刺すような日ざし。―どうでもいい。鼓膜に反響する蝉の声。―構わない。君との関係をこんなにもあっさりと手放して取り残された僕は一人、ブロック塀に身を預けて呆然と立ちつくしていた。…
急いで文集から引っ張ってきました。一番よく覚えてる作品です。これを読んだとき、…なんて言えばいいのかな。いろんな気持ちが混ざり合って、無性に泣きたくなりました。
すごい、とか、私には書けない、とか、私も書きたい、とか。キミと一緒に文芸部ができてよかった、とか。
キミはきっと、小説馬鹿だった私の唯一の理解者でした。恥ずかしい気もするけど今なら言えます。ありがとう。
最後に二人で会ってからもう三年ですね。三年の間に変わったことも、変わっていないこともたくさんあります。私に関して言えば、あれから髪を伸ばしました。蝉はまだちょっと苦手です。大通りを一人で歩けるようになりました。病気一つせず健康です。
久しぶりに、キミの声が聞きたいです。』
私は筆を置いた。切手を探そうと立ち上がると、窓の外から五時を告げる夕焼け小焼けの歌とともに、ふわりと涼しい風が舞い込んできた。昼間の暑さが嘘のようだ。
…たぶん、初恋だった。今更どうという話でもないけれど。
夏が終わろうとしている。私は明日、結婚する。
* * *
『手紙読みました。懐かしいな、最後に会ったときは君も僕も大学生だったっけ。変わらず元気そうで安心しました。
結婚式の友人代表スピーチ、実は密かに張り切ってたんだけど、身内だけの小さな式で済ませるそうですね。どうせなのでこの手紙をスピーチの代わりにしようと思います。最後まで聞いてくれると嬉しいです。
「青い馬」
いつからそこに居たのだろう。一頭の青い馬が私を見据えていた。美しい馬だった。毛並みには艶があり、脚はたくましく、水を張ったように澄んだ瞳は私と世界を青く反射しながら、ただ静かに凪いでいた。そして、―シンパシーとでも言うのだろうか。その瞳を見返した瞬間、唐突に私は、もう二度ともといた場所には帰れないのだと悟った。…
恥ずかしくて懐かしい作品を君が引っ張り出してくるから、お返しに僕も。君の作品の中でいっとう好きな話です。君は人一倍想像力があって、不思議な動物を考え出しては僕に話してくれたよね。
人の夢を食べるハリネズミ(バクの方が新参者だと言い張っている)。ドとレとミとファとソとラの蛙(輪唱がうまくいくとお捻りを求めてくる)。涙の川を泳ぐ金魚(淡水の刺激ではもの足りないらしい)。死者だけを乗せる青い馬(かき入れ時はお盆だそうだ)。
じっと窓の外を眺めては新しい小説を書いていた君に対して、何が見えてるんだって冗談半分ではやし立てる奴もいたけど、君には本当に何かが見えていたのだと僕は思っています。君の小説を読むと、ハリネズミが食べた夢の味も、蛙が奏でた音楽も、金魚が泳いだ水の温度も、馬が映した世界の青さも、全部自分がそこにいるみたいに伝わってきて。僕はいつだって、君の想像力が羨ましかったんだ。
君に追いつきたくてずっと頑張ってきたからこそ、今君が人生の門出を迎えることを心から嬉しく思います。
さて、少しだけ、彼女の隣でこれを読むかもしれない旦那さんへ。僕みたいな同級生の存在はさぞ不愉快だと思います。でも僕としては、あなたと一晩くらい飲み明かしてみたかったです。きっと趣味が合ったでしょうから。
最後にもう一度君へ。
三年前、大学を卒業したら結婚するって嬉しそうに報告してくれた君の顔を今でも覚えています。友人代表のスピーチをする約束をして、喫茶店を出るタイミングがあと少しずれていれば。信号を待たないで歩道橋でも使っていれば。
あのとき僕たちに向かってトラックが突っ込んでくることはなかったかもしれないのに。
君がそうやって自分を責め続けていたのが、僕にはたまらなく辛かった。とっさに君を押しのけたことを、僕は一度だって後悔したことはありません。責任を感じて三年も結婚を延ばす必要なんか、ちっともなかったんだよ。事故の直後は外を歩くことさえままならなかった君が、一人でも大通りを歩けるようになったみたいで安心しました。良かった。心配でずっと見てたけど、もう大丈夫だよね。僕はそろそろ行こうと思います。
結婚おめでとう。君に会えて幸せでした。君もどうか、幸せになってください。
追伸
もしまた昔みたいに小説を書いたら、暇なときでいいから墓前に供えてください。なんたって、僕は君のファン第一号だからね。』
「お待たせ」
返事を書き上げて僕は振り返った。
憧れてやまなかった彼女の世界観。彼女が本当に見ていたのか今となっては確かめるすべもないが、こうやってゆかりのもので送られるのは、まあ、悪くない。
青い毛並みの美しい馬はゆっくりと二回まばたきをして、僕を乗せるために身を屈めた。
—————————————————————————————————–
■佳作 「夏空に紙ヒコーキ」 鹿児島県立加世田高等学校 一年 三浦 琴乃
クーラーの効いた部屋の中、茉莉は一枚のプリントとにらめっこしていた。プリントの上には、『進路調査』の文字。
さほどランクの高くない公立高校の三年生になって数ヶ月。茉莉は未だに、自分の将来を決めかねていた。大学へ行くには実力が足りない。夢がないのだから専門学校へは行けない。かといって、履歴書を書く自分なんて想像出来ない。
そして結局。六月上旬にもらった調査票は、白紙のままだった。
『夏休み明けにはせめて、進学か就職かぐらいは決めておけよ。』
家の中よりクーラーが効いている職員室で、終業式の日に担任から釘を差された。それでもやっぱり、茉莉は自分の将来像なんて思い描けなかった。
「…よし、アイス。」
考えることに疲れた茉莉は、この夏買ったばかりのサンダルを履き、近所のコンビニへと出かけることにした。
空っぽに近い財布から小銭をかき集め、好物のバニラアイスを手に入れた茉莉。そんなルンルン気分の帰り道、いつもは何も停まっていない公園の駐輪場に、赤い大型バイクがある。
(まさか、帰ってきてんの。)
茉莉は好奇心から、公園を覗く。
隅の自販機の前に、背の高い男がいた。見つけた瞬間、茉莉の声は発せられていた。
「あんな所にバイク停めちゃ駄目だろうが。」
「えっあ、いや、俺のバイクは駐輪場の…、て、茉莉ちゃんじゃん。」
「久し振り、安城汐。」
安城は茉莉の兄 淳也と同級生で、茉莉より一つ上の大学生。安城と淳也はよくつるんでいて、自然と茉莉もよく遊んでもらっていた。
「兄貴、元気でやってるの。」
「知らない。連絡来ないし。」
茉莉が自販機を指すと、安城は苦笑いしながら、百円のサイダーを買ってくれた。
「茉莉ちゃんは元気だったの。」
「この通り、夏を満喫してますよ。」
「嘘つけ、肌真っ白じゃん。」
「どこ見てんの、変態。」
久々に飲むサイダーは、冷たくて甘かった。
しばらくお互いは無言で、茉莉はサイダーを、安城はお茶を飲んでいた。チラリと安城を茉莉は盗み見た。つい半年前にいなくなったのだから、見た目は大して変わっていないように見える。さっきも、ちょっと警官の真似をしただけでビビったところを見ると、小心者な点も相変わらずなようだ。
「あれ、どこの大学行ったんだっけ。」
「俺ね、大阪だよ」
そうだった、と茉莉は思った。確か食いだおれ太郎がどうのこうのとか、そんな話をした記憶がある。
「そうだよ、お土産ちょうだい。」
「ごめん、無い。」
「ふざけんなよ、安城。」
茉莉ににらまれ、あたふたし出す安城。
「だって、急に母ちゃんに呼び出されて、そんな暇無かったんだよ。」
ごもごも言う安城は、自分より年上に思えず、溜め息がもれた。
もういいけど、と呟けば、安城はホッとしたように笑った。
「で、何の勉強してるんだっけ。」
「茉莉ちゃんには難しいよ。」
(あ、子ども扱いした。)
サイダーを飲みつつ、大人ぶっている安城をにらむ茉莉。もちろん、気付かれなかったけれど。
「簡単に説明してよ。」
「一言で言えば、宇宙についてかな。」
「そういうの好きだったんだ。」
「ロマンがあるじゃん。」
アルミ缶を太陽にかかげ、ヘラッと笑う安城。そんな姿が、茉莉は心底羨ましかった。
「そういう茉莉ちゃんだって、昔はパイロットになるって言ってたじゃん。」
「…言ったっけ。」
本当は覚えていた。
初めて飛行機に乗った時、すごく感動した。だから茉莉は、ずっと飛行機に乗っていられるパイロットになりたいと思った。
「別に、気まぐれだったし。」
その感動から、六年経った十四の秋。その頃から『出来る子』であった兄に言われた。
『パイロットって、勉強も出来て、それに虫歯とかあったらなれないんだって。』
淳也がどういうつもりで茉莉に言ったのか茉莉には分からなかった。それに、それが事実かどうかも分からない。
ただ茉莉はその言葉が、暗に『おちこぼれ』と言っているように聞こえた。
だから、辞めた。
努力することも、夢を見ることも、何もかも辞めて。結局、本当の落ちこぼれになっていた。
「ねえ、どうしてもその勉強したかったの。」
「したかった。月を観に行きたいから。」
「じゃあ、宇宙飛行士になりなよ。」
茉莉の言葉に、笑う安城。
「俺、体力無いからさ。」
確かに安城は学生時代、部活動に所属していなかった。
「運動もだけど、勉強も出来ないし。けどやっぱり、宇宙に関することをしたかったから。 だから俺、淳也に手伝ってもらって、めっちゃ勉強して、大学に行けたんだ。」
無邪気に笑い、ピースサインをつくる安城はキラキラしていて。茉莉は目を反らしていた。
「頑張ってたんだ。」
(何もしないで、落ちこぼれた私とは大違い。)
何の夢もない茉莉からしたら、今の安城が眩しかった。
「茉莉ちゃんは卒業したら、どうするの。」
「知らない。」
他人事のように吐き捨てた茉莉に、安城は苦笑する。
「だって、わからないよ…。」
安城のように夢も無いし、兄のように進学先が選び放題なわけでもない。文字通り、お先まっ暗なんだから。
「わかんないんだよ…。」
うわ言のように、そうくり返す茉莉。
そんな茉莉の手を、安城は何も言わずに握りしめていた。
「あ、んじょ…。」
「茉莉ちゃん。俺はね、本当は大学に行く気なんてなかったんだ。」
急に語り出す安城。茉莉は驚いて安城を見たが、彼はいつもと変わらないヘラヘラとした笑顔のままだった。
「俺、バカだし。でもやっぱり先生から期待されてた淳也のこと、羨ましいなって思ってた。俺、一回だけ言っちゃったんだよ、『天才なお前とバカな俺じゃ、吊り合ってないよなあ。』て。」
そしたら、と茉莉は急かした。
「淳也はね、こう言った。『確かに、なりたいものがあるのに頑張らないお前は、ただのバカだ。』俺、言い返せなかった。」
やっぱり兄は、悪意を持っていたんだ、と茉莉は密かに思った。でも同時に、疑問が生まれた。
「なんで、そんなこと言われたのに、兄と一緒にいたの。」
茉莉は淳也に夢を砕かれてから、彼と話すことに苦手意識を持ってしまったのに。
でも安城は、やっぱり笑いながら言った。
「俺にはその言葉が、応援してるよって聞こえたから。」
「…なんで。」
「やれば出来るよって、言いたかったんじゃないのかな、アイツは。」
なんてポジティブなんだろう、茉莉は安城のその思考が、ただ羨ましかった。
「私も昔、そんな風に言われたことある。」
自分には、見下されたように聞こえた言葉が、安城にはどう聞こえるのか。気になった茉莉は、昔言われた言葉を安城に伝えた。安城による解釈は、こうだった。
「たくさん勉強して、健康だったらパイロットになれるってことじゃないかな。」
不器用な兄なりの、妹へのメッセージ。安城がいなかったら気付けなかった、兄の本心。本当は悪意なんて無かった。
「ねえ、安城汐。私、虫歯出来たことないの。」
「そりゃすごい。」
「勉強、今からでも間に合うかな。」
「茉莉ちゃんなら大丈夫だよ。」
その言葉が素直に嬉しかった。
その後、お土産を約束させて安城と別れた茉莉は、バイクの吐く煙を見つめていた。
「茉莉ちゃんなら大丈夫、か。」
すっかり溶けきったバニラアイスを冷凍庫に入れ、自分は未だクーラーの効いている自室に戻ってきた。テーブルの上には、出掛ける前と同じ様に『進路調査』の文字が躍る紙。
「…私の夢は、パイロットです。」
茉莉はそう呟き、ペンではなく紙を手に取った。
また、あの感動を感じたくて。また、夢に向かってはばたきたくて。
「テイクオーフ。」
飛行機と化した調査票が、力の無い、でも意思のこもった呟きを合図にして、茉莉の手から離れた。
—————————————————————————————————–
■佳作 「貝殻」 宮城・常盤木学園高等学校 二年 村上 佳代子
私の箱には白い貝殻。毎年毎年、少しずつ増える。けれど、まだ半分にも届かない。
夏休み。私は家族でおばあちゃんの家へ泊りに行く。二泊三日の毎年恒例の行事。
小学四年生だった私は、正直この行事があまり好きじゃなかった。だってこっちにいる間は友達と遊べないし、宿題も早めに済ませておかなければならない。おばあちゃん家にはゲームも何もないし、クーラーもない。
おばあちゃんは優しかった。私たちが泊まりに来た時は、必ず私の好きな甘口カレーをつくってくれたし、私が暑くてだれていると、「アイス食べる?」「ジュース飲む?」と声をかけてくれた。私はいつも、おばあちゃんの言ったことに「うん。」とか「ううん。」しか答えなかった。おばあちゃんが嫌いだったわけじゃない。ただ、年に一、二回しか会わないおばあちゃんとの会話を慣れてなくて、恥ずかしかったのだ。
こっちに来て二日目の夕方、私はただぼっとしてテレビを見ていた。内容はよく分からないニュース番組だったけど、チャンネルを変える勇気もなかったので、それしか見るものがなく、することも他になかった。私の横でお父さんが寝っころがっていびきをかいている。いつも仕事であまり家にいないお父さんがこんなにくつろいでいる姿を見せるのは、おばあちゃん家に来た時だけだ。
台所ではお母さんがお夕飯をつくっていた。
「あれ?」と思った。
「お母さん、おばあちゃんは?」
「さっき海岸の方へ行くって出かけたわよ。夕飯前に帰るって。」
「ふぅん…。」
そういえば、昨日のお夕飯もお母さんがつくった物だった。おばあちゃんは昨日も…もしかしたら毎日、この時間帯に出かけているのだろうか。暇なので何か手伝おうか、と言おうとした時に、母は大根を切りながら、「あんたも海岸、行ってみたら?」と言った。
「えー、やだよ。外暑いもん。」
本当の行きたくない理由は他にあったけど、言いたくなかったのでごまかした。
「もう夕方だからいくらかマシになってるでしょ。それにほら、家から近いって言っても、おばあちゃん一人で何かあったら危ないし。様子見くらいで良いから行ってきて。」
そんなこと言われて断わったら、なんだか自分が悪い子になる気がして。結局、私は海岸へと向かうことになった。家を出てものの五分で、目的地に到着した。砂浜と同じ色の帽子を被っていたおばあちゃんを見つけるのには、少し時間がかかった。
こちらが声をかけるのに戸惑っているうちに、下を向いていたおばあちゃんが顔を上げた拍子に私に気づいた。
「おや、どうした? まだ夕飯の時間じゃないはずだけど。」
私は、正直に「お母さんに頼まれたから。」
と言っていいものか迷った。何け抜け口になるものはないかと視線をさ迷わせていると、おばあちゃんが持っている箱に目が止まった。
箱といっても金属でできたもので、以前クッキーやら菓子やらが入っていたと思われるもの。私の視線に気づいたのか、おばあちゃんは「あぁ、これ?」と箱を開けてみせてくれた。中に入っていたのは、貝殻だった。
「夏になると毎日ここに来て、気に入った貝を拾ってるの。これがおばあちゃんの一番の楽しみでね。」
砂浜に点々と散っている貝殻。それをおばあちゃんは腰をかがめて拾う。貝はしばらくおばあちゃんに見つめられた後、また元の位置に戻った。どうやらおばあちゃんの眼鏡には適わなかったようだ。その一部始終を、私は少し離れた所から見ていた。おばあちゃんは少し離れた所から見ていた。おばあちゃんは楽しい、と言っていたが、今の光景が私の目にはどうしても淋しいものに映って、このままおばあちゃんを残して帰る気になれなかった。
しばらく海岸に接する階段に腰かけ、貝拾いに没頭するおばあちゃんを見ていて分かった。おばあちゃんの貝たちへの審査は必要以上に厳しかった。まず見た目。ここでほとんどの貝が落とされている。次に肌ざわり。おばあちゃんのシワだらけの指が二、三度殻の上をすべる。この段階でも数個落とされた。
このセカンドステージを突破した強者たちを待ち続けるのは何だろう、と固唾を呑んで見守っていると、おばあちゃんは貝をそっと耳に当てた。真剣に、何かを聞こうとしているような、そんな仕草だった。お父さんはおばあちゃんと電話で話す時、普段より大きな声を出す。それはおばあちゃんの耳があまり良くないからだ、と聞いたことがあった。
私は何が聞こえるのか、気になった。だから自然と、おばあちゃんに尋ねることができた。「何が聞こえたの?」と。
「聞いてみるかい?」
おばあちゃんが私に差し出したのは、黒と白が混ざり合ったブチ柄の貝。もちろんどこにも音が出てきそうな穴なんかないし、貝がしゃべるわけもない。少しだけ耳に当てて、返した。「聞こえた?」とおばあちゃんが聞く。
「なんにも。もしかして、おばあちゃんは耳がすごく良いの?」
アハハ、とおばあちゃんが笑った。「そうかもね。」と言って。
「おばあちゃん、その貝は合格?」
「んー、そうだね。この子は見た目は今ひとつだけど、肌ざわりは良い。音も悪くないし、よし。」
おばあちゃんは箱を開けた。さっきも見せてもらったけれど、中にはたくさんの貝たちが眠っていた。色、形、肌ざわり…は見た目ではちょっと分かりづらいが、色々なものがある。同じようなものなどひとつもなかった。
その中からおばあちゃんは一つ、取り出すと、海の方へと歩き出した。私もその後ろをついて行く。海面ギリギリの所へ到り着くと、おばあちゃんは箱から取り出したその一つを、ポン、と海に放った。ポシャン、と水しぶきの音がした。
箱には代わりに今日合格した貝殻が収められた。何も聞くまでもなく、おばあちゃんは一人言のように「これ以上入らないからね。一つ拾ったら一つ捨てないといけない。」と言った。それ以上は何も言わなかった。
今年も夏がやってきた。例年通り、何時間ものドライブを経て、おばあちゃんの家へ行く。お母さんからは、今年は無理して行かなくても良いわよ、と言われたけれど、私は行きたいから、と答えた。
五年前の夏から、私は貝を拾い始めた。でも私の貝箱はまだガラガラである。毎年一個は良いものを見つけて箱に収める。それが私の決めたルールだ。
今年で六回目の貝拾い、私は左手に箱を、右手におばあちゃんの腕を、おばあちゃんは左手に箱を、右手に杖を持って海岸をゆっくりと歩いていた。
見つめるのは海でも夕日でもなく、足下の砂浜。その中に、小さな白が埋まっているのを見つけた。拾い上げて見せると、おばあちゃんは「こりゃあ本当に白かい?なんだか違う色に見えるけどね。」と笑った。夕日が照らして、白は夕日色になっていた。自分の箱を開けて、まだ少ない仲間にそれを加えた。それでも私の箱は何だか淋しく見える。
「どうしたら、良いものをたくさん見つけられるんだろ。」
「あんたは白いのしか集めないのかい?私にとっちゃ、どれも同じに見えてつまらないよ。」
確かに、私は白しか拾わなかった。だからなかなか溜まらない。
「よく見てごらんよ。そこにも、ほらここにだって落ちてる。とにかく見つけたら、拾ってごらん。触ってごらん。聞いてごらん。少しでも良いと思えるものがあったら、自分の箱に収めればいいさ。箱にはまだ十分空きがあるんだから。」
おばあちゃんは一つ拾うと、一つ捨てる。
私はただ、拾う。箱がいっぱいになるまで、捨てることなく、拾い続ける。
終わり
—————————————————————————————————–
■入選
「雑魚」愛知・名古屋国際高等学校 三年 櫻井 美奈子
「俺の妹とその友達」埼玉・星野高等学校 二年 水村 遥香
「黒猫」東京・昭和第一高等学校 三年 加茂 千咲
「嫉妬」神奈川・横浜雙葉高等学校 二年 坂元 愛美
「ある日死んだはずの妻が帰って来た~1泊2日の家族旅行~」東京・東亜学園高等学校 三年 高野 隆一
「夢のその先」青森県立青森高等学校 二年 小杉 愛