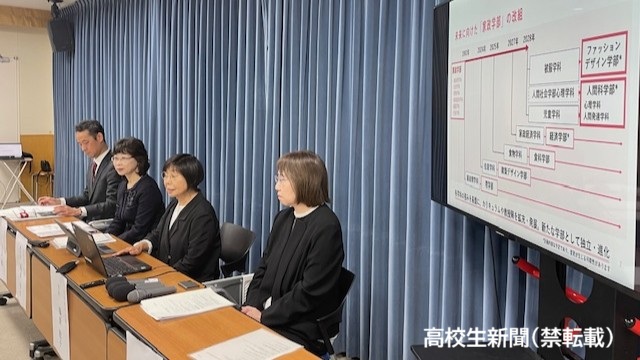地震大国と呼ばれる日本。首都直下型地震など、大地震が起こることが心配されている。いざというときに焦らないためにも、知っておくべきことは何だろう。災害時に本当に役に立つ技や知恵を発信しているNPO法人プラス・アーツの坂本良子さんに、災害時に高校生に期待される役割などについて聞いた。(文・野口涼、写真・野村麻里子)

自分の学校は自分たちで守る
高校は災害時に地域の避難所になることがあります。もし自分の学校が避難所になったら、「自分たちの学校は自分たちで守る」「自分たちの学校が地域の人たちを守る」という気持ちを持ってほしいです。
そのためには「トイレ掃除は誰がするのか?」「そのための用具はどこにあるのか?」といったことを、委員会活動と関連づけて、普段から話し合っておく必要があります。運動部の合宿など、実際に校内で集団生活をしたことのある生徒にアドバイスを求めるのもいいでしょう。

いざというときの連絡方法を再確認
もうひとつ、家族とのいざというときの連絡方法をぜひ話し合っておいてください。家族の安全が確認できれば、安心してその場で待機できます。LINEやツイッターはもちろん、NTTの災害用伝言ダイヤルは一度ぜひ試しておきたいもの。また、集合場所は「●●中学校の正門の右側」などできるだけ具体的に決めておくこと。過去の震災では、同じ中学校に避難していながら3日間も会えなかった親子がいるそうです。
首都直下型地震が30年以内に起こると言われてから、すでに10年が経ちました。災害があったとき、高校生には助けられる側ではなく、助ける側になってほしい。その第一歩として、ここで学んだ防災情報を今すぐ周囲の人に伝えてもらえればと期待しています。
【NPO法人プラス・アーツ】阪神・淡路大震災から11年後の2006年、防災への関心が薄れつつあった神戸で設立。震災時に実際に役立ったもの・ことを伝えるために全国で活動している。