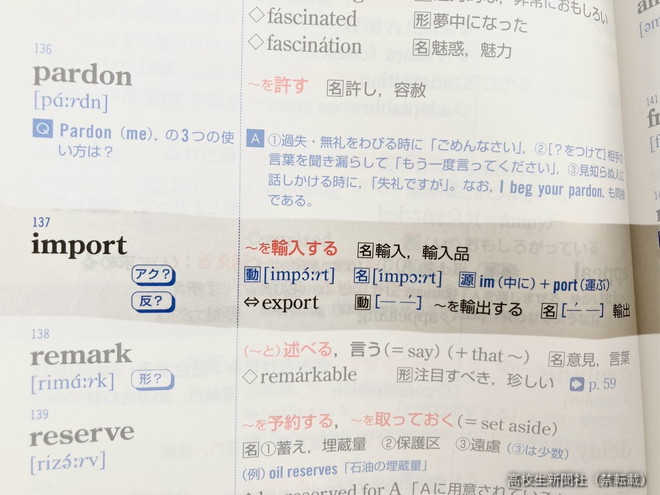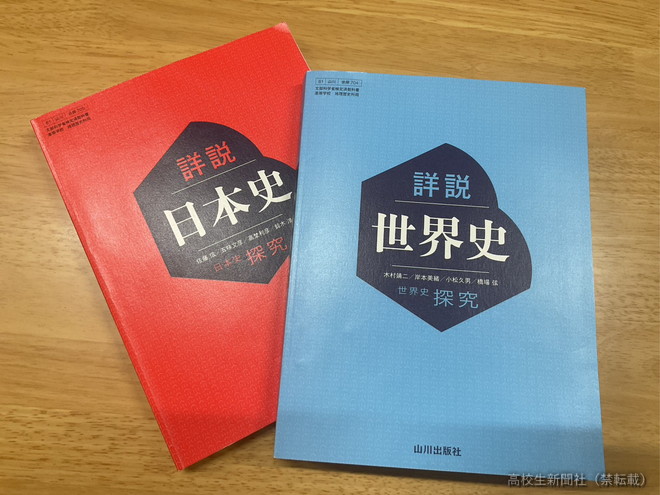昼休みが5分短くなって、授業に間に合わない……この問題を解決するべく、八重山高校(沖縄)の生徒会副会長・大城愛夏さん(沖縄・八重山高校3年)は、昼休みの延長を求めて改革を実行。粘り強く先生と対話を続け、公開討論を実施し、諦めずに改革を成し遂げた。
「昼休み5分短縮」で遅刻増加
大城さんは「生徒会が行事の運営だけに偏っていないか」と疑問を抱いていた。生徒の意見を学校全体に届け、変化を生み出す仕組みをつくった。

大城さんが取り組んだのが、一日の流れを示した「日課表」改革だ。以前は50分だった昼休みが、昨年から45分に短縮。加えて、以前は昼休み後に設定されていた掃除の時間が、最後の授業後に設定された。「すると、昼休み後の授業に遅刻する生徒が増えてしまったんです」
石垣島にある同校の特殊な事情も絡んだ。「石垣島の高校では、昼休みに家や寮に帰ってご飯を食べる生徒も多いんです。『行きと帰りの時間を含めると、45分では足りない』という声が多く寄せられました」

教員と生徒で公開討論
生徒総会前の学級討議で、多くのクラスから「改善を望む」と発議があり、生徒会が草案を作成。「掃除の時間は、先生たちの予定の兼ね合いなどの理由で変更不可。『では昼休みだけなら変えられますか?』と、話し合いを重ねました」
学級代表委員会で承認を得て、生徒総会では大城さんのアイデアで、初めて教員と公開で議論を行った。「先生と生徒って対立しがちだけれど、先生には変更できない理由が、生徒には変更したい理由がある。お互いの事情を知ってもらうためにも、公開討論を行いました」
先生と生徒で考え方に「違い」
校長・教頭・主任らが参加する会議、職員会議と段階的に協議を進める中で、壁にぶつかった。
「先生側と生徒側で、『復活させたい5分』の扱いが異なりました。八重山高校ではスマホは休み時間にしか使えないので、『昼休み』として5分を復活させたい。対して先生たちは、スマホ利用不可の『移動時間』として5分を延長させるならOK、という考えだったのです」
昼の「5分」を取り戻した
「遅刻防止」という目的に沿うと、先生の言い分も理解できた。話し合いを重ねて、試行期間を経て、「昼休み45分+移動時間5分」の新しい日課表が25年4月に正式導入された。
「改革には手間がかかり、1年間ほど時間もかかりました。でも、『誰のための改革か』を見失わずにいられました。昼休みに家に帰る生徒から『ゆっくり安全に行き帰りできる』と言ってもらえました!」
大城さんの活動は、「第9回日本生徒会大賞」(生徒会活動支援協会主催)の高校生・個人の部で最優秀賞となる「大賞」を受賞した。意思決定のプロセスを生徒主体で組み立てた点が、高く評価された。
提案を繰り返す姿に先生も評価
生徒会担当の松元輝先生は、改革を成し遂げた大城さんを「すごいの一言だ」と評価する。
「放課後よく職員室に来て、改革案を提案してくれました。『それはこういう事情で難しい』と話すと、数日後にはその事情を踏まえて新しい提案をしてくる。みんなの先頭に立って、変えていく力があります」(松元先生)
生徒総会で起立性の承認を導入
大城さんはほかにも生徒総会で起立制承認を導入し、報告や計画が流れ作業にならない工夫も加えた。
「拍手承認の総会は具体的な人数も数えないし、『音が大きいからよいか』と雰囲気で進んでいました。それは、生徒の意思決定とは言えません。だからこそ、参加実感を持てる総会にしたかったんです」
2年生だけだった役員構成に1年生枠を加え、引き継ぎ体制を整えた。

「自分たちの代でやりきる」
改革の過程では、仲間の熱量の差や、同級生への注意で孤独を感じる場面もあった。「私は学校生活で生徒会活動を一番大事にしていたけれど、他の役員は部活など、別の居場所もありました」。それでも、「自分たちの代でやり切る」という責任感を持ち続けた。
「生徒会を『自分のため』に使いたくなかった。誰かの役に立てるなら、大変さも意味があると思えました」

全国の生徒会とつながる未来へ
改革を通じて、「自治」の可能性を実感した。他校の取り組みを知る中で、全国規模での情報共有やネットワークづくりの必要性も感じている。
今後は生徒会連盟の設立や、全国の生徒会との交流の場づくりを目指しながら、自校においてはさらなる自治の強化と引き継ぎ制度の充実に取り組んでいくつもりだ。