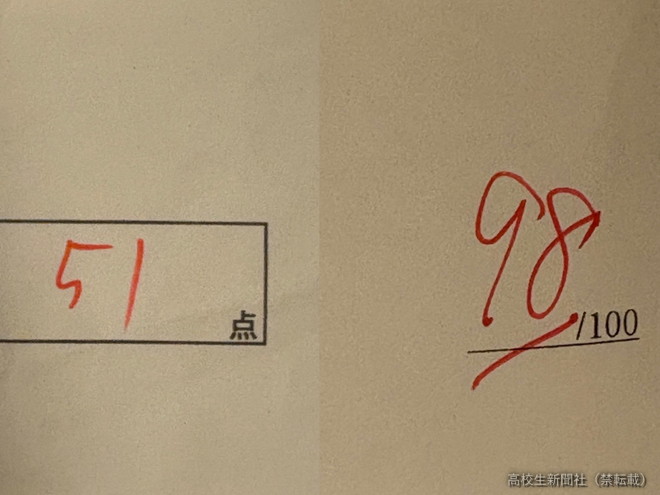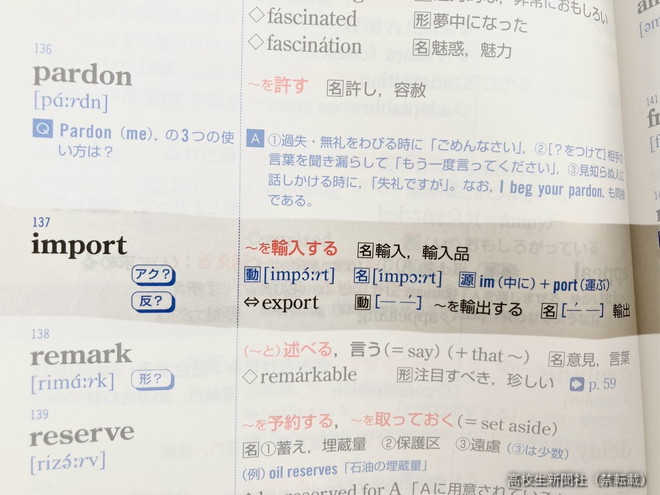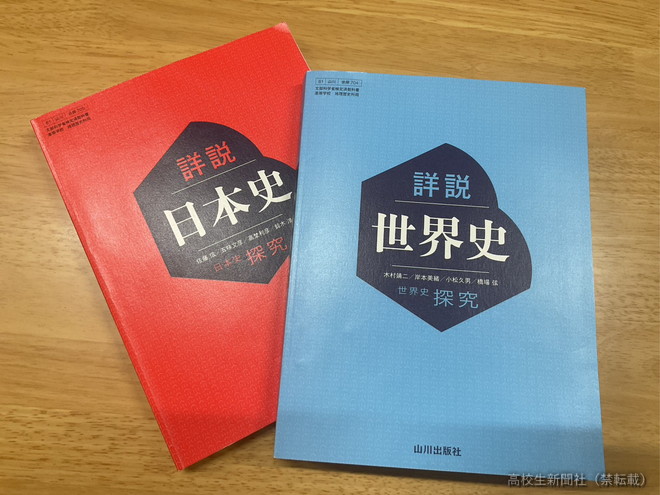泉松陵高校(宮城)の生徒会執行部は「生徒から出た意見をかたちにする」ことを目指している。学校内はもちろん、地域を巻き込んで変化を生み出してきた。どんな活動をしているのか、生徒会長の尾形結愛那さん(3年)に聞いた。
意見が届く「生徒総会」に変えたかった
生徒から「意見を出しても変わらない」という声が上がり、生徒の声をいかに反映できるかが課題だった。「生徒総会でも生徒から意見が出ず、『早く終わらないかな』という雰囲気が漂っていて、形だけの行事になっていることに違和感を抱いていました」

粘り強く先生と交渉
尾形さんたちは、意見提出後の確認作業や対応方針を丁寧に整理し、学校との信頼関係を少しずつ築いた。
「『学校にアイスの自販機を設置したい』など実現が難しい内容も多く、先生方とぶつかる時もありました。でも、代議員会で粘り強く整理し、先生にも何度も確認を取りました。今では『文化祭でのスマホ利用』が緩和されるなど、実現できる意見も少しずつ増えてきました」

不登校気味の役員の声から「多世代あいさつ運動」へ
他にも、登校時に地域の大人や小中学生と一緒に立ち、あいさつを交わす「多世代あいさつ運動」に力を入れている。
「クラスメートとトラブルになり、『同世代といるのがつらい』と不登校気味だった役員が『もっといろんな世代と関わりたい』と提案したのがきっかけでした」
地域であらゆる世代と関わる活動を考えようと、町内会との意見交換を重ねた。出た意見が、学校近くの大通りであいさつ運動をする「多世代あいさつ運動」だ。「学校と地域が一丸となってできるようなことを考えて生まれた活動です」
現在は最大で70人近くが参加。温かいつながりが少しずつ広がっている。

こうした「声を拾って、かたちにする」取り組みの成果が認められ、「第9回日本生徒会大賞」(生徒会活動支援協会主催)の高校生・学校の部で最優秀賞となる「大賞」を受賞した。
「強く引っぱる」より「居心地のよさ」を重視
生徒会長として、尾形さんが一番大切にしているのは「居心地のよさ」だ。「誰もが安心して話せる雰囲気をつくれば、自然と人は動き出すと思っています。否定せずにまず受け止める、頑張りに気づいて声をかける……そういう積み重ねが大事です」
リーダーが強く引っぱるのではなく、全員が自然に力を出せる空間づくりがチーム全体を前向きにする鍵だと語る。
行動で信頼を示したい
とはいえ、苦しい経験もあった。「思うように会がまとまらず、自信を失った時期がありました」
そのとき、尾形さんは何度も対話の場を設けた。言葉だけでなく、行動でも信頼を示そうと決意したという。
「相手の話を真剣に聞き、自分の思いも率直に伝え、どうすれば進めるかを一緒に考えました。お互いが納得できる形を見つけられて、行動の重みを実感しました」
「より良い学校づくり」は対話と行動から
今後は、多世代あいさつ運動のさらなる発展と、生徒の声を集める仕組みの強化したいという。「もっと安心して意見を言える環境をつくりたい。誰かの声から、また新しい変化が生まれる。そんな学校にしていきたいです」
最後に、他校の生徒会に向けてメッセージをくれた。「意見の違いや迷いがあるのは当然です。でも、対話を続けることで必ず理解の糸口が見えてきます。完璧な正解を求めるより、小さな一歩を大切に。『困難は成長のチャンス』です。自分たちらしい生徒会をつくってください」