「熱中症なんて、暑さのピークはまだ先だから大丈夫!」と油断していない? 実は、気温がそこまで高くなくても、熱中症の危険は潜んでいる。救命救急医の清水敬樹先生(多摩総合医療センター)に、どんな状況で熱中症が起きやすいのか知っておくべきポイントを聞いた。(木和田志乃)
熱中症は春でも起こる
今年4月、鳥取で高校生が熱中症とみられる症状で救急搬送された。「まだ春なのに?」と思った人もいるかもしれないが、実は熱中症は夏だけに起きるわけではない。総務省の統計では、昨年5月の段階で熱中症による救急搬送が2799件にものぼっている。
「暑さ指数」を知ろう
清水先生は、「熱中症のリスクを考えるときは、気温だけでなく『WBGT(暑さ指数)』を見ることが大切です」と言う。「WBGT」とは、気温・湿度・日差しの照り返し(輻射熱)などをもとに計算される。

「気温30度、湿度70%、日差しの強さ」が警戒基準
日差しが強く、気温が30℃前後、湿度が70%を超えると、例え夏でなくても警戒が必要だ。
「特にWBGTが28を超えると、熱中症で運ばれる人が一気に増えます」。28は「厳重警戒」レベルに該当し、日常生活を送っているだけでも熱中症のリスクが高まる。外では直射日光を避け、室内ではエアコンを活用するなどの対策が必要だ。
「30」を超えたら外出は避けて
WBGTが31になると「危険」レベルに。外出を避け、なるべく涼しい室内で過ごすことが求められる。激しい運動は中止だ。
33を超えると予想される時には「熱中症警戒アラート」が発令される。不要不急の外出を避け、適切にエアコンを使用して涼しい環境で過ごし、こまめに水分・塩分補給、運動を原則中止するなど、普段以上の対策を採るように呼びかけられる。
冬でも熱中症は起きうる
気温がそれほど高くなくても、湿度が高く蒸し暑い日は注意が必要だ。「冬でも湿度が高いと、熱中症が起きた例もあります」
さらに気をつけたいのが、アスファルトのように地面からの照り返しが強い場所だ。「日差しが強いだけでなく、地面が熱を反射し、体が感じる暑さはさらに増します」。こうした場所では体温が上がりやすく、熱中症のリスクが高まる。

アプリやHPで暑さ指数をチェック
文部科学省も、体育や部活動で暑さ指数を使った行動の目安をガイドラインとして示しており、学校でも対策が進んでいる。
熱中症は、暑さが厳しい環境に行かないようにすれば、防げる病気だ。「暑さ指数が高い日は、無理に出かけず、やむを得ない場合は、あらかじめ涼める場所を把握するのが重要。避暑シェルター(クーリングシェルター)として解放されているコンビニや公共施設など、休憩できる場所を確認しておくと、体調の急変を防ぎやすくなります」
天気予報でも「暑さ指数」として発表される。「今は熱中症アラートのアプリや環境省のLINE、自治体ホームページ等でWBGTの数値や警戒アラートを確認できるので、日ごろからチェックする習慣をつけてほしいです」。ちょっとした意識の差が、自分の体を守ることにつながるはずだ。












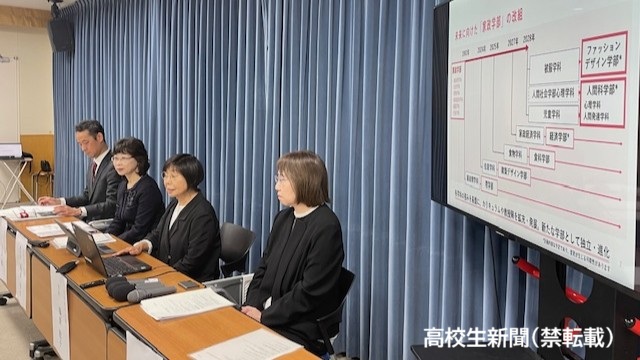






清水敬樹先生(多摩総合医療センター)
しみず・けいき 東京都立多摩総合医療センター・救命救急センター部長。熱中症や救急救命治療などに専門的に携わる。