日々研究が進む薬学。AIの活用や新薬の開発など、薬剤師を目指す高校生が知っておきたい「最新の薬学事情」について、明治薬科大学学長の越前宏俊学長、齋藤望教授、林弘美教授に聞いた。(野口涼)
薬剤師のAI活用は「拡大の傾向」
―AIが急激に普及しています。薬剤師の仕事にどんな影響を与えていますか?
越前 どの病気にどんな薬が効くかなど、人間の頭脳よりAIの方が適切な答えを出せる場合はあるかもしれません。調剤などの定型的な仕事がロボット化されている国も既にあります。日本でも将来は薬剤師の仕事でもAIが担う業務が多くなってくるのは間違いないと思います。

齋藤 機械は人間と違って疲れませんから、人間よりも間違えません。処方せんに書いてある医薬品を薬棚から取り出し用意する業務である「ピッキング」をした後の監査をAIで自動化するシステムも開発されているようです。
ただ、薬剤師にとって、もっとも大切な「対人業務」はAIには決してできないのではないでしょうか。
「人にしかできないこと」に注力できる
林 AIの普及は、薬剤師が会話の行間を読んだり、患者さんに応じた気配りをしたりといった 「人にしかできないこと」に集中できるというプラスの側面があると感じます。
―「人にしかできないこと」とは?
林 薬剤師は、薬局や病院にいるイメージが大きいですが、患者さんのお宅を訪問してどんな生活をされているのか把握したり、学校でプールの水質検査をしたりといろいろな場所で活躍しているんです。AIが普及すれば、薬剤師の大切な仕事である「対人業務」により注力できるのではないでしょうか。
薬学部へのVR導入は道半ば
―近年はAIやVR(仮想現実)が教育現場でも活用されています。薬学部ではいかがでしょうか?
越前 医学部などでは、学生が実習に行っても実際にはなかなか入れない手術室や救急の場などを擬似体験できるVR教材を使っている大学もあるようです。まだ発展途上の段階です。いずれは広く採用されるようになるのではないでしょうか。
―創薬研究の場など、現場ではどのように生かされているのでしょうか。
齋藤 創薬についても、従来は膨大な化合物ライブラリを用いた化学実験によるアプローチでしたが、最近はビッグデータやAIを活用して新たなアプローチを考える研究もされています。ただし、こちらもまだ教育で活用できるレベルには至っていません。
まれな病気の新薬開発が進む
―最近の薬の開発について教えてください。
越前 最近は、比較的まれな病気(希少疾患)の患者さんの病気の原因治療を目指す「分子標的薬」という薬が作られています。病気の原因になる異常にだけ作用する薬です。患者さんが少ないので必然的に非常に高価になり、従来の薬と同じかそれ以上の開発費用が掛かります。
―身近な病気の新薬研究は活発ですか?
越前 高血圧・高脂血症などの生活習慣病や、患者さんがたくさんいる感染症に対する薬は、「ほとんど探し尽くした」といわれており、最近の新しい薬の開発は方向転換が迫られています。ただし、人間の科学の発展の歴史は、行き詰まりとブレークスルーの連続でした。今後また画期的な新薬が出てくる可能性は大きいでしょう。それを発見するのがこれからの若い方々ですね。
齋藤望(さいとう・のぞみ)
1972年北海道旭川市生まれ。91年旭川東高校卒、95年北海道大学薬学部卒、2000年同大学大学院薬学研究科博士課程修了。博士(薬学)。専門は有機合成化学、有機金属化学。
林弘美(はやし・ひろみ)
1964年東京都武蔵野市生まれ。83年国立高校卒、87年お茶の水女子大学文教育学部卒、93年同大学大学院博士課程人間文化研究科単位取得退学。博士(言語学)。明治薬科大学では薬学英語などの授業を担当。












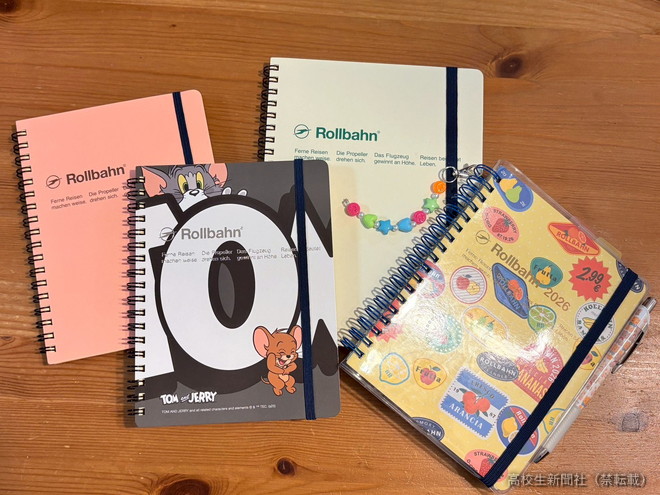
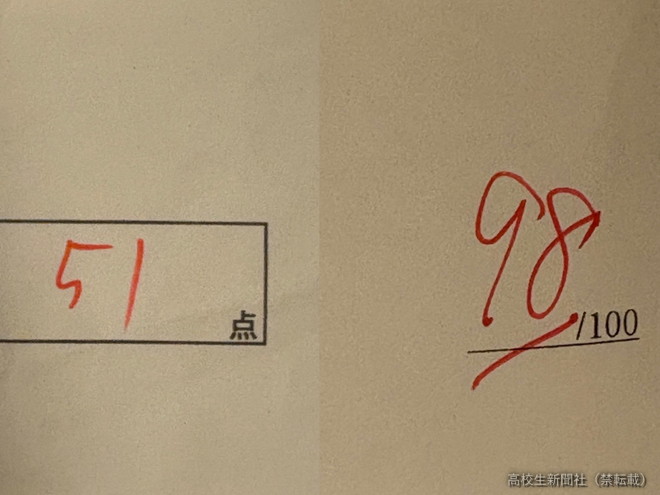

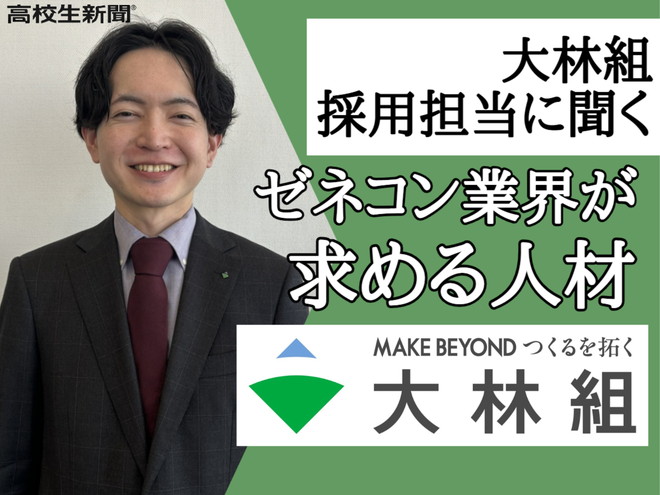





越前宏俊(えちぜん・ひろとし)
1954年北海道生まれ。72年函館ラ・サール高校卒、78年北海道大学医学部医学科卒。78年国立国際医療センター内科、その後米国およびドイツ留学。86年博士(医学、東京大学)。専門は臨床薬理学・消化器病学。2020年より現職。