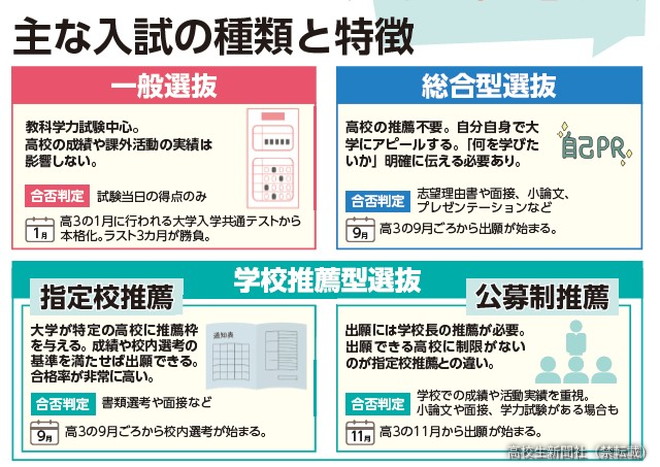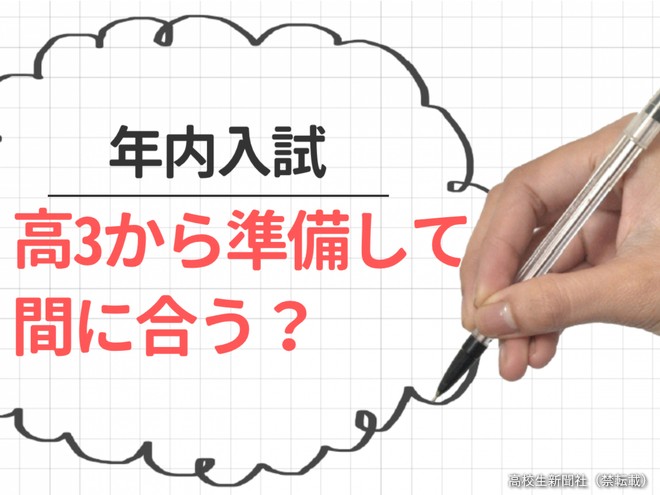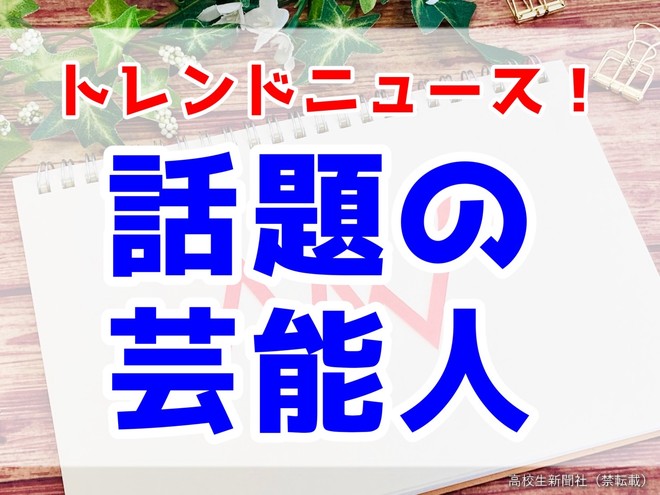第73回全日本バレーボール高校選手権(春高バレー)決勝が1月10日、東京体育館で行われた。女子は就実(岡山)が優勝した。(文・田中夕子、写真・中村博之)
ノーシードから勝ち上がり、25大会ぶりの頂点に立った。昨年敗れた悔しさを晴らすべく、試合がない中でもそれぞれが練習を重ね、心を切らさずつかんだ勝利だった。その陰には、劣等生だった3年生たちの目に見えない覚悟と努力があった。

「練習の成果を出すのはここだ」
24-12。サーブ順が回って来た自分を「ついている」と思った。今までやってきたすべてを出し切ろう、と周田夏紀(3年)が渾身(こんしん)の力と思いを込めて放ったサーブは、堅守を誇る大阪国際滝井の選手も返球できず、サービスエース。
「サーブにはこだわりを持ってきました。心の中で『打て』『攻めろ』、練習の成果を出すのはここだ、と思って打ちました。その1本が決まって、こんな最高の機会をバレーの神様がつくってくれたんだ、と報われる思いでした」
「成長した姿見せたい」毎日5キロ走り体力UP
高校2年時、19年のインターハイを制覇。春高も制し、二冠を狙ったが結果はまさかの初戦敗退。

悔しさを晴らすべく、最後の1年は絶対にインターハイ、国体、春高とすべてのタイトルを獲ると意気込むも、公式戦は相次いで中止となり「もう試合ができないんじゃないかと思って落ち込んだ」と振り返る。
だが、くよくよしていても時間は過ぎていく。
全体練習ができるようになった時、以前よりも成長した姿を見せたいと決意した。特に力を注いだのはラントレだ。
就実伝統の「2キロ走」では8分を切らなければならないのだが、入学したばかりの頃は10分以上かかっていたこともあり、毎日5キロを走り、プラスして瞬発力を高めるためにダッシュも取り入れた。
その成果は全体練習が始まってからにとどまらず、ノーシードで連戦が続いた春高でも活かされ「前はラリーになると息が切れてしまうことが多かったけれど、今大会ではどれだけラリーが続いても動き続けることができた」と胸を張る。
日本で一番長く3年生とプレーしたい
成長したのは体力面だけでない。
チームの柱として活躍するのは、下級生で双子の深澤めぐみ(2年)と深澤つぐみ(2年)。どちらも頼もしい存在であることは確かだが、下級生の活躍を見れば見るほど自分たちがふがいなく、もっと頑張ろうという気持ちが空回りする。

「このままでは(3年生が)全員レギュラーになれないのではないか」と焦ることもあったと言うが、ずっと試合すらできない中、ようやくこのチームで1つになって戦える機会はこれが最後。
ゲームキャプテンも務めるエースの深澤が「日本で一番長く、3年生と一緒にプレーしたい」と話していたように、1、2年生は「3年生のために戦おう」と自分たちの背中を押してくれる。

西畑美希監督からも「春高は3年生の大会だから、3年生が頑張らないと」と鼓舞された3年生たちの心に火がついたのは、春高開幕数日前。「自分のためだけじゃなく、お互いのため、誰かのために頑張ろう」と1つになり、挑んだのがこのチームで臨む最初で最後の春高だった。
ニュース見るたび不安に…「そんな時こそ一日一日を大切に」
コロナ禍での開催で、会場入りできる選手は登録18名のみ。
出られない3年生たちから送られたミサンガをつけ試合に臨んだが、日々ニュースで新型コロナウイルスの感染者数が増加するたび「いつ大会が中止になるかわからない」と不安も抱いた。
だが、そんな状況だからこそ、1日1日を大切に。3年生同士で毎日話しながら戦ってきた最後の最後、自分にサーブ順が巡って来た時は「ついている」と思ったし、「思いきり打つしかない」と覚悟を決めた。
レギュラーになれなくても、試合に出られなくても、一緒に会場で戦うことはできなくても心はひとつ。そして、今まで積み重ねて来た努力も消えるわけではない。すべての思いを込め、放ったサーブでつかんだ就実25大会ぶりの日本一。周田が言った。

「苦しいことが多い1年でしたが、苦しい時に頑張ったことが結果になると実感しました」
悔しさや不安もすべて乗り越えて、最後に流したうれし涙。頑張ってきてよかった、とすべてが報われた瞬間だった。
- 【チームデータ】1950年創部。部員32人(3年生12人、2年生8人、1年生12人)。17年の春高で準優勝、19年インターハイで優勝。日本代表でリオデジャネイロ五輪にも出場した石井優希や、小川杏奈、小川愛里奈などVリーグにも多くのOGを輩出している。
-