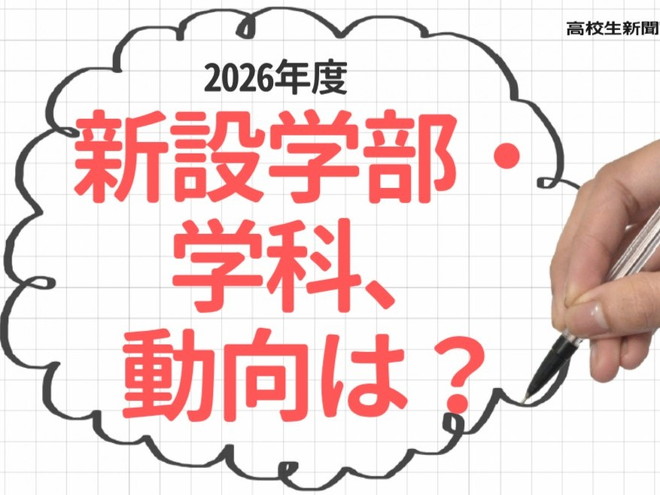必由館高校(熊本)和太鼓部は第49回全国高校総合文化祭(かがわ総文祭2025)の郷土芸能部門・和太鼓部門で、最優秀賞となる文部科学大臣賞を受賞した。優秀校東京公演(8月23・24日、新国立劇場)では、一糸乱れぬバチさばきを披露した。(中田宗孝)
徹底した基礎練習を繰り返す
部長を務める小田恵史さん(3年、大平太鼓・篠笛担当)は、和太鼓の演奏力をレベルアップさせるためには「基礎を怠らない。何度も基礎練習を繰り返すことです」と話す。
部では「二分音符」「四分音符」「八分音符」「十六分音符」と細かく分け、それぞれの長さをたたく和太鼓の基礎練習を徹底して取り組む。リズム感を体に染み込ませる、テンポキープを覚えるという効果のほかにも「基礎力が身につくと、それが太鼓奏者としての『自信』につながっていくんです」。基礎練習に打ち込めば、メンタル面にもプラスに働く。

リズムを口ずさみ息を合わせる
曲練習の際は、和太鼓のバチを使わない練習「口唱歌」を必ず行う。曲中の和太鼓でたたくリズムを声だけで表してみる試みだ。部員たちは円を作ってリズムを口ずさむ。「ドンドンドドド、ドドドンドン」。この練習では、言葉で発してリズムを覚えやすくしたり、奏者同士の息を合わせたりできる。
「単にリズムを口にするだけでなく、うちの部では曲調や盛りあがり部分を意識して感情を込めて歌っています」。喜びいっぱいのドドドンや、悲しさあふれるドドドンと、情感たっぷりの口唱歌を響かせる部員たち。「そうすることで部員一人一人が『このパートは楽しく、こっちは抑えてたたこう』と、曲の雰囲気を理解し、表現力の部分も高められるんです」
食い違う意見も否定しない
和太鼓ステージの醍醐味(だいごみ)は、奏者たちの華麗なバチさばきによる一糸乱れぬ演奏だ。このパフォーマンスを可能にするのが、「部員間のコミュニケーション」と小田さんは言う。「私たちの部は『心をひとつに「和」』を部訓に掲げ、全部員52人の気持ちを一つにしようと、学年関係なく意見を交わせる空気づくりを心掛けてきました」
とはいえ、意見の相違が起こる場面はおとずれる。「『相手を尊重する姿勢をもとう』と伝えてきました。自分と反対の意見だとしても、『でもさ』『じゃなくて』と即否定せず、まずは相手の主張や考え方を一度受け入れる。これが大事」

「音を届ける意識」を持つ
今夏、「かがわ総文祭2025」の郷土芸能部門・和太鼓部門で日本一に輝いた。部は受賞歴多数の強豪ゆえに、周囲の期待も大きい。大舞台で普段どおりの実力を発揮できる理由を小田さんは「観客のみなさんに音を届ける意識」だと語る。
「大会で好成績を収めるのはもちろん目標の一つではあります。ですが、それ以上に、演奏を聞いてくださる方々に、自分たちの思いをのせた演奏を届けたいと思って舞台に立っています」
-
必由館高校和太鼓部
2001年創部。部員52⼈(3年生21⼈、2年生12⼈、1年生19⼈)。活動⽇は週5⽇。これまで「総文祭」郷土芸能部門には12回出場し、最優秀賞2回受賞、優秀賞5回受賞。