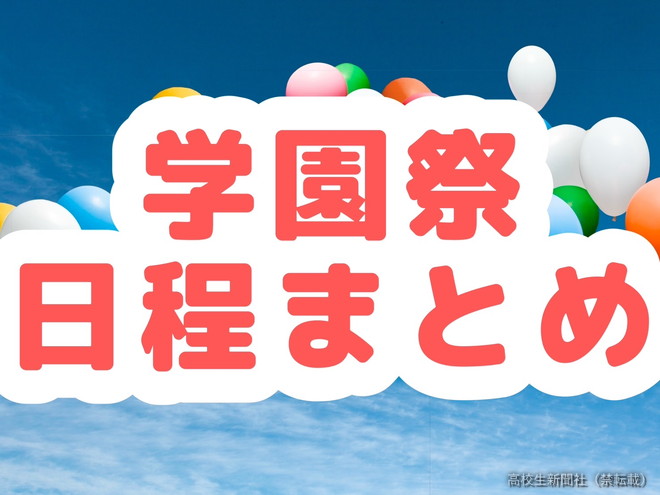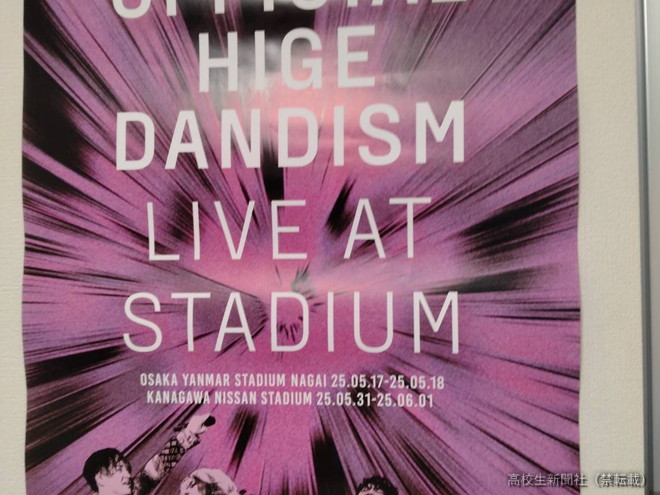伊丹北高校(兵庫)放送委員会は、放送部の全国大会「NHK杯全国高校放送コンテスト」の常連で強豪校だ。魅力的な番組やスキルの高いアナウンス、朗読の技術はどのように生まれているのか、部員たちに聞いた。(文・写真 木和田志乃)
「Nコン」全国出場を目指して
「NHK杯全国高校放送コンテスト」(Nコン)への出場を最大の目標だ。部員はNコンの部門ごとに分かれ、ラジオ・テレビのドラマやドキュメンタリーなどの番組制作に取り組む。朗読やアナウンスといった個人部門への出場も全員が目指している。日々の校内放送活動で直面する問題を解決するための工夫や研究にも力を注ぐ。一人ひとりが団体と個人の両方で熱心に活動している。

コードネームで呼び合う
先輩が新入部員に「コードネーム」(あだ名)をつけ、お互いをその名で呼び合う伝統がある。部長の上田恋羽さん(2年)のコードネームはレイ。好きな色や作家、行きたい国などから取った文字を組み合わせて名付ける。「互いの本名がわからなくなるぐらい浸透しています」。部の明るく和やかな雰囲気を作り出しているという。
【1日のスケジュール】部門ごとに分かれて番組制作
平日は放課後2時間、休日は午前中3時間、活動している。発声練習は2~3人ずつで体育館の前など部室以外の場所で行う。部室では部門に分かれ、番組制作を進めている。
テーマ決めから、シナリオ作成、取材、編集まで担当する。他部門の作品作りにもキャストとして参加することもあるため、自分の部門の制作と他部門の作品の収録が同時期に重なる場合も多い。
-
<ある日の上田さんのスケジュール>
16時 部活開始
16時~16時30分 発声練習
16時30分~17時30分 他部門のテレビドラマ撮影に演者として参加
17時30分~18時 ラジオドラマ部門に合流し、編集した音源をチェック。提出用進行表の作成
18時~18時10分 ミーティング、部活終了
【Nコンに向けた流れ:朗読部門】絵コンテを描いて場面を想像
Nコンの個人部門には「朗読部門」と「アナウンス部門」があり、部員は全員いずれかへの出場を目指している。大会に向けて、どう活動を進めているのか、「朗読部門」を例に紹介する。
Nコン終了後、翌年の指定作品5点が発表される。まずは「1分30秒から2分以内」の規定時間に収めるため、作品のどの部分を抜き出すかを慎重に選ぶ。

ストップウオッチを持って時間を計りながら読む練習を、毎回合計で1時間程度行う。「具体的に想像しながら朗読できるように、すべての場面の絵コンテを描いています」(小坂こころさん・3年、前副部長)
意識しているのは、文章と文章の「間」。どのくらい空けるかは、何度も試行錯誤を繰り返し、他の部員の意見を聞いて決めている。
他校の生徒との交流会や研修会にも参加する。「自分の朗読への評価を聞くがありますし、他校の生徒の朗読から多くを学べます」(小坂さん)
Nコン県大会のエントリーは5月のゴールデンウィーク明けのため、その前に校内でミニコンテスト、オーディションを実施。アナウンス部門、朗読部門で各10人の出場者を決めている。
-
<Nコンに向けた流れ:朗読部門>
前年8月 朗読作品の決定、朗読部分の抽出
前年9月 朗読原稿作成、練習開始
前年11月 県高校総合文化祭出場
前年12月 県個人部門強化宿泊研修
2月 放送フェスティバル(地区別研修会)
4月 ミニコンテスト
5月 校内オーディション
6月 N コン兵庫県大会
7月 Nコン全国大会
【Nコンに向けた流れ:ラジオドキュメント部門】全国大会翌日から次のテーマを検討
部員は「ラジオドキュメント部門」「テレビドキュメント部門」「ラジオドラマ部門」「テレビドラマ部門」「校内放送研究」部門に分かれて活動する。それぞれ全国大会への出場が目標だ。「ラジオドキュメント部門」を例に、大会に向けた流れを紹介する。
Nコン終了後、すぐに翌年の大会に向けてテーマの検討を始める。ニュースには普段から目を通しているが、実際には部員同士の雑談からアイデアが生まれ、テーマになる場合が多い。
今年のNコンで優良賞を獲得した番組は、生成AIのメリットや問題点がテーマだ。都築友花さん(3年)の「夏休みの読書感想文がなぜ必須でなくなったのか」という疑問から生まれた。生成AIで作った文章は先生にばれるのかを調査し、生徒や外部の専門家などに取材した。

「テーマを深く掘る中で、自分たちの視点も変わります」(都築さん)。番組の内容にお笑いを取り入れるなど、聞いてもらう工夫を重ねる。情報を入れすぎずにわかりやすい編集を心がけながら、構成の変更や再取材を重ねて番組を練り上げる。5月下旬の県大会音源提出まで、綿密な作業が続く。
-
<Nコンに向けた流れ:ラジオドキュメント部門>
前年8月 テーマ選定
前年9月~3月末 学内の生徒・教師への取材・アンケート開始。場合によって学校外の専門家にも取材。適宜テーマを修正。
4月上旬~4月下旬 集めた取材内容を並べ、必要なナレーションを考え、台本の第1稿完成。
4月下旬~5月上旬 ナレーションの録音と編集作業を同時に進行。規定時間に収まるように使用するインタビューを厳選し、台本を修正し、ナレーションを再録。音楽を入れていったん完成。
5月中旬~5月下旬 さらにインタビューの順序変更、使うインタビューの変更など構成を何度も練り直し、完成。
5月下旬 音源提出。
6月 Nコン県大会予選、準決勝、決勝
7月 Nコン全国大会
【年間スケジュール】学校行事やラジオでも活躍
「私たちは、放送部ではなく、放送委員会なんです」と語るのは、前部長の邨井春花さん(3年)。「メインの活動は番組制作ですが、入学式や卒業式の音響・映像・記録、体育大会の司会・記録や会場設営、学校説明会でのプレゼンテーションなども行っています」(邨井さん)
年間4回、地元のFMラジオで1時間の生放送を担当している。地域のイベントの司会や、県内の作品コンテストへの応募など、活動の場は学校外にも広がっている。放送委員会には、学校や地域社会を支える役割も期待されている。
-
<年間スケジュール>
4月 入学式 音響・記録
5月 ハッピーエフエムいたみ『青春放送局』出演。学校説明会で学校紹介プレゼンテーション
6月 NHK杯全国高校放送コンテスト兵庫県大会。文化祭 音響・司会・記録
7月 NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会。市民ピアノリレーコンサート司会。HYOGOヒューマンライツ作品コンテストに向けた作品制作
8月 ハッピーエフエムいたみ「青春放送局」出演
10月 体育大会 音響・司会・記録
11月 県高等学校総合文化祭。いたみマダン司会
12月 ハッピーエフエムいたみ「青春放送局」出演。個人部門強化宿泊研修(県)
2月 放送フェスティバル(地区別研修会)。伊丹市共生福祉社会フォーラム司会
3月 ハッピーエフエムいたみ「青春放送局」出演。卒業式 音響・映像・記録
【上達のコツ】「基礎」を大切に毎日練習
部員たちは「上達の秘訣(ひけつ)は、基礎の繰り返し」だと声をそろえる。みな、毎日の地道な練習を欠かさない。コンテスト前や学校行事の準備が重なると、個人練習の時間が取りにくくなる。そのため、お風呂やエレベーターの中、自転車通学の途中など、場所を問わず練習している。
喉を痛めないためにも、おなかから声を出す腹式呼吸が重要だ。腹式呼吸ができているか、背中やおなかに手を当てて筋肉の動きを確認しながら練習している。
番組制作の取材では、事前に質問項目を準備しておく。回答で少しでも疑問があれば、「なぜですか」と重ねて質問する。インタビュー前に雑談をして相手と打ち解けると、より良い取材ができると感じるという。取材方法は先輩のやり方を見て学んでいる。
-
伊丹北高校放送委員会
 伊丹北高校放送委員会
伊丹北高校放送委員会1973年創部。部員30人(3年生11人、2年生10人、1年生9人)。全国大会(Nコン、総文祭)23年連続出場。Nコンは2015、16年創作テレビドラマ部門優勝。