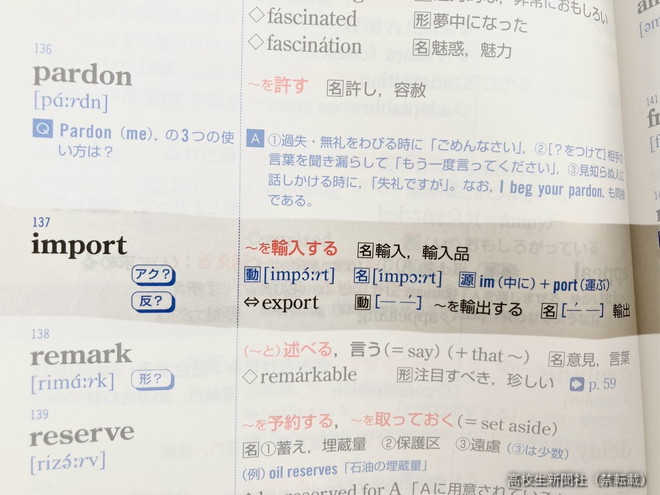尼崎双星高校(兵庫)吹奏楽部の打楽器八重奏は、3月に行われた第48回全日本アンサンブルコンテスト(全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催)高校の部で金賞を受賞した。部としては2度目の出場だ。音をそろえ、動きをそろえ、心までそろえる。奏者の呼吸を完璧に合わせ、心までそろえ、奏者の呼吸を完璧に合わせた。(文・写真 木和田志乃)
難曲に挑戦「曲のイメージ」を深め
曲はライアン・ジョージ作曲「コンシダー・ザ・バーズ」を選んだ。マリンバやビブラフォンなどの鍵盤打楽器を中心に、複雑なリズムと和音が重なる難度の高い作品だ。

作品のテーマは、ムクドリの群れと1羽の鳥のさえずり。部長の澤地玲さん(3年)は、「音楽の情景がつかみにくい」と感じ、チームでストーリーを考えた。「1羽の鳥と少年が出会い、嵐に立ち向かい、ムクドリの大群に襲われ鳥は連れ去られ、別れた後にお互いを思い合う情景」を思い描いた。そのうえでメンバー間で話し合い、作り出したい音を決めていった。

リズムとタイミングを完璧に
昨年10月から毎朝7時から1時間半ほど、アンサンブルコンテストに向けて練習を続けた。演奏全体を通す日もあれば、前日に気になった箇所を一つひとつ丁寧に確認する日もあった。動画を撮影し、譜面と照らし合わせて音のズレを見つけては修正する作業を繰り返した。
同じ旋律を1拍目から演奏する人、2拍目から演奏する人……と、追いかけるように音を重ねて演奏する部分も多い。タイミングをそろえるのは大変だった。
「最初はリズムとタイミングを完璧に合わせる練習から始めました。強弱をつけず、音をぴったりそろえるために全員1拍目から演奏。練習を重ねて音が合ってきたら、楽譜通りの演奏をする……という練習を繰り返しました」(野田侑利さん・3年)
響きと動きの美しさを両立
石橋優那さん(3年)は、音の広がりにこだわった。「打楽器はたたき方で音が大きく変わるため、手首の使い方を研究し、ホール全体に響く音を研究しました」
澤地さんは、「ゆっくりで弱い音」の部分に特に力を入れて練習した。「全国大会では強弱の表現が評価された」と手応えを感じている。
音だけでなく動作の統一にも意識を向けた。打楽器は視覚的な動きも注目されるため、横から見て腕の高さや手首の角度をそろえた。

大会ごとに小さな目標を積み重ね
目標の「全国大会金賞」をかなえるため、小さい目標を積み重ねた。地区大会では「タイムオーバーをしない」、県大会では「奏法のアドバイスを守り、自分たちの100%を出す」。関西大会では「全国出場を決める覚悟」と「最後かもしれないから楽しむ」。大会ごとに目標を立てて進んだ。
「常に本番のつもり」で練習
4人は昨年も打楽器八重奏のメンバーとして全国大会に出場していた実績から、今年も全国大会に出場するのが当然だと周囲に期待されていた。関西大会前はプレッシャーも大きく、部内は少しピリピリした空気が流れていた。
特に野田さんは、曲の冒頭の音を一人で担当していたため、「最初でミスをしたら全体の印象が崩れる」と不安を抱えていたという。
そのため、チームでは練習の時から本番のつもりで演奏するのを心がけた。だからこそ、本番では練習のように臨め、緊張感の中でも力を発揮できた。
野田さんは、関西大会の緊張を乗り越えた経験が、全国でも自信につながったと感じている。

意見のぶつかり合いも音楽の糧に
アンサンブルでは指揮者がいないため、演奏者同士の呼吸を合わせる力が非常に重要になる。
山中真斗さん(3年)は「合わせる力はアンサンブルで最も鍛えられる部分であり、吹奏楽にも生かせる」と話した。アンサンブルで一番大切な要素を問うと、「コミュニケーション」だと即答。
曲全体のストーリーは共有していたものの、細部の表現については意見が食い違い、ぶつかる場面もあったが、澤地さんは「意見の違いが音楽を良くするのが面白かった」と感じている。時に対立が生じても、時間をかけて折り合いをつけられたという。
全国大会への挑戦は、音楽だけでなく人間関係と真剣に向き合う経験にもなった。8人でつくった金賞の音楽には、響き以上の思いが込められていた。
-
尼崎双星高校吹奏楽部
2011年創部。部員106人(3年生32人、2年生34人、1年生40人)。「関西吹奏楽コンクール」は9回出場、金賞5回受賞。「マーチングコンテスト関西大会」は9回出場、金賞2回受賞。「全日本アンサンブルコンテスト」には、2023年度初出場。練習前に好きなことわざや四字熟語を紹介し合う時間を設けている。