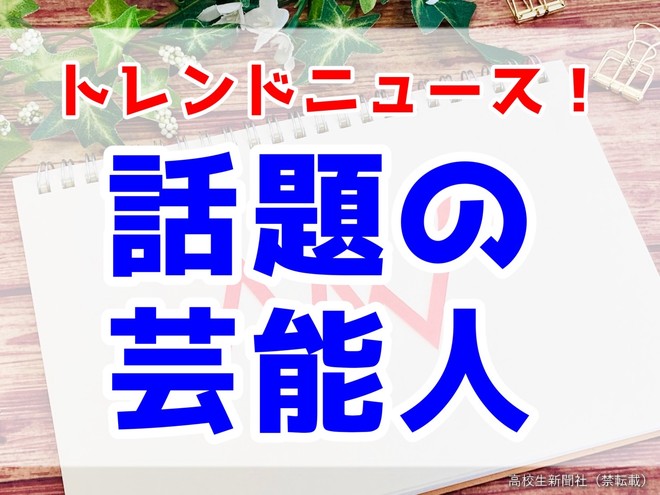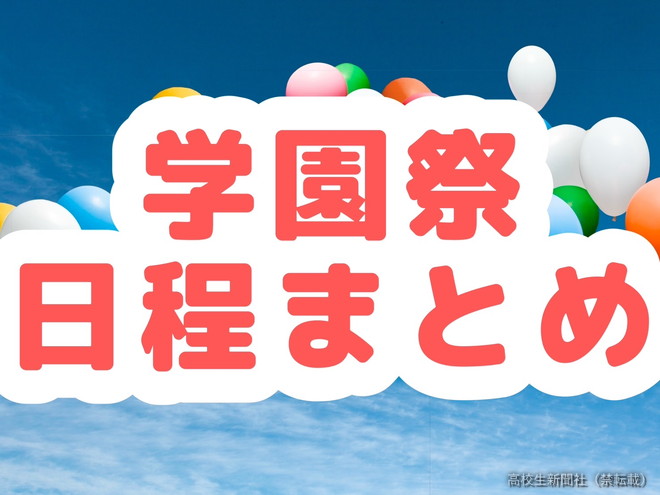新しい環境になじめず、中学時代に不登校を経験した庄子怜未さん(宮城・宮城県農業高校3年)。学校に行けなかった過去を乗り越えて、今はかつての自分と同じ「不登校」に悩む生徒を支える活動をしている。(文・黒澤真紀、写真・本人提供)
知り合いゼロ、溶け込めず不登校に
庄子さんは、中学1年の9月に不登校になった。中学進学と同時に引っ越し、知り合いはゼロ。周囲は小学校からの友人同士で、なかなか溶け込めなかった。初めての定期テストでも点が取れず、ストレスが重なった。

「家に帰ると毎日ぐったり。小学校の頃は明るかった自分が、気づけば気持ちを言えなくなっていました」
2学期に入る頃から、朝起きられなくなった。次第に欠席や遅刻が増え、9月下旬には完全に登校できなくなった。
心閉ざし誰の言葉も響かず
次第に自室からも出られなくなり、教科書やノート、カバンはすべて押し入れの奥にしまった。「学校に関するすべてを目に入れたくなかったんです」
母に「死にたい」と漏らした日もあった。「母は泣いて止めてくれましたが、当時は誰からの言葉も響きませんでした。不安や嫌な気持ちが、自分の中に収まりきらず、どうしたらいいのかわかりませんでした」
「ありのままの私」を見てくれた
中学2年に上がる前、学校から外部のフリースクールをすすめられ、少しずつ外に出られるようになった。しかし、家から離れた場所にあり、バスを1本逃した日は通えなくなってしまう。
「学校の方が行きたいタイミングで少しずつ外に出られるんじゃないか」と考え、中学2年の春、学校で教室に入れない生徒のために設けられた「ホットルーム」に足を運んでみた。常駐している元教員のスタッフに「学校に来ようとしてるだけで、十分すごいよ」と声をかけられた。
「不登校の自分はダメだと思っていた。でも、先生は、学校に行こうとする努力を分かってくれ、ありのままの私を受け止めてくれました」。少しだけ前に進む力が生まれた。
「給食までに登校する」と決意
毎朝「給食までに登校する」と決めて、10時ごろ学校へ行くようになった。ホットルームで絵を描いたり、本を読んだりしながら、自分のペースで過ごした。好きだった国語から少しずつ、リモートで授業に参加していった。
「ホットルームは、完全に学校に行けない『0』と、教室で過ごす『100』のちょうど真ん中の場所。安心できました」
高校進学を目指し教室に復帰
高校進学を望むようになり、宮城県農業高校を目指した。「親と相談して全日制の高校を受けると決めました。高校見学に行った際、校舎がすごくきれいで広くて、『ここに通ったら面白そう』と思ったんです」
高校に行くには朝から学校に行って、授業を受ける必要があると考え、「4月からの3カ月間は、毎朝登校時間に登校する」と決めた。5月ごろには国語の授業を教室で受けられるようになり、夏休み明けには主要5教科すべてを教室で受けるようになった。
部活の顧問の先生に背中を押され
現在、小学校時代まで過ごした地域にある宮城県農業高校に祖母の家から通っている。「高校は中学と違って、もともとできている人間関係に入っていくわけではない。不安もありましたが、『スタートダッシュを切れれば楽しく過ごせる』と思っていました」
高校1年の終わり、部活の顧問の先生に中学時代の不登校の経験を話した。「それって他の人ができない、すごくすてきな経験だよ」と返され、「学校の先生や両親に支えてもらったことを、今不登校の子どもたちやることが一番の恩返しになる」と強く思うようになった。

高校2年になり、母校のホットルームで、高校で育てたサツマイモを使ったスイートポテトづくりの出前授業を企画した。「楽しい時間を提供するなら、私にもできるかもしれない」と考えたからだ。
女子中学生4人が参加し、男子も気にしてのぞきに来た。「高校に進学したい」と相談されたときは、自分の経験を語った。
不登校を経験したから「悩みを話してもらえる」
母の知人の地方議員に、自身の不登校の経験と、不登校の生徒を支援をしたい思いを話した。「その方も子どもや学校に関する活動に熱心だったので、話してみたいと思ったんです」
地元の集会所を使えるよう協力してもらい、不登校の中学生向けにティッシュカバーづくりのワークショップを開催した。料理や裁縫といった手仕事は、自然な会話を生みやすいからだ。

参加者に自分もかつて不登校だったと話すと、子どもも保護者も、悩みを打ち明けてくれた。「不登校の理由って、本当に人それぞれ。でも、私自身も経験しているからこそ、『この人はわかってくれる』って思ってもらいやすいんです」
昨年12月、ボランティア活動をする中高生を表彰する「ボランティア・スピリット・アワード」(プルデンシャル生命など主催)に参加し活動を発表、応募者の中から8組に送られる全国賞を受賞した。
教師になって不登校の子どもを支えたい
文部科学省が2024年10月に発表したデータによると、不登校の小中学生は11年連続で増加している。昨年は34万6482人で過去最高の数値を記録した。不安や悩みを相談できなかったり、一人で抱え込んでしまったりする子どもたちを、サポートする必要がある。
「私にとって、不登校の過去は欠点ではありません。不登校の経験があるからこそ、今、子供たちに寄り添える。大事な原点であり、強みです」。今の自分の姿が「不登校になったからといって終わりじゃない」というメッセージになると信じている。
将来は教師を目指す。「子どもたちに寄り添っていきたいです」
※この記事は高校生新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。
- *つらい気持ちになったら、気持ちを落ち着ける方法・相談窓口
- 「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/