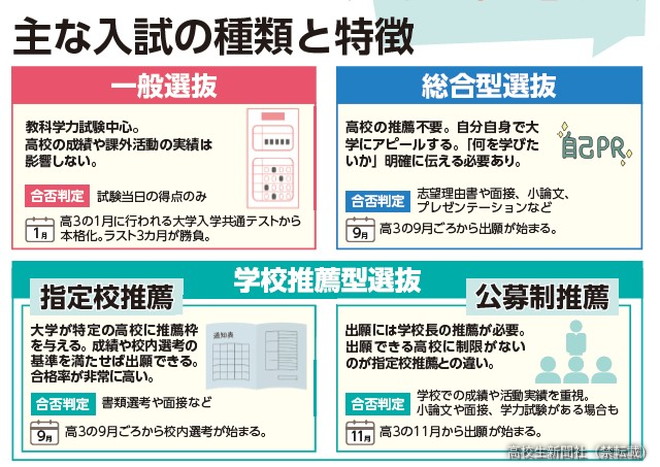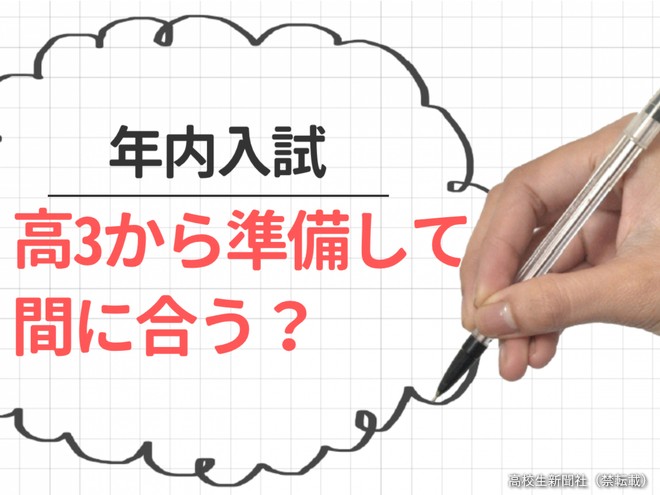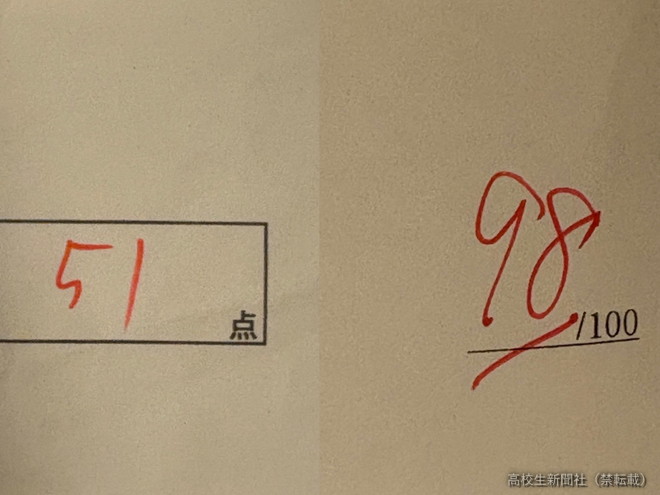景山さんの弁論原稿「苦しみを乗り越えて生きるということ」
悪い巡り合わせに、たまたま当たってしまっただけなのでしょうか。
私が過ごした中学校時代、家庭環境は、決して悪いわけではありませんでした。学校生活でも、一緒に過ごしてくれる人たちも居て、特に困ることは感じていませんでした。
勉強はとても苦手だったけれど、母も、父も、「勉強が苦手でも、ちゃんと学校に通えているならいいよ。」と言ってくれるので、成績が悪いことも、あまり気に病まずに生活することができていました。
人生の歯車が狂い始めたのは、吹奏楽部に入部した後のことです。
受け持ったパートはパーカッションでした。未経験で、全てゼロからのスタートだったのですが、担当の先輩は、私の演奏が思うようにできないと、バチを折って、猛烈に怒りました。次第に、私は「自分ができないからこうして怒られるんだ。」と思うようになり、部活に行くことが辛く、保健室に逃げ込むことも多くなっていきました。そうなるともう、楽器を見ることすら嫌になっていき、程なく退部してしまいました。もともと音楽が好きで入部したはずなのに。
悪いことは重なるものなのでしょうか。
この頃から、家庭環境も悪くなり始めました。今一つ調子の出ない私が気に入らないのか、ストレスを抱えていたのか、父の私に対する態度が、厳しく暴力的なものに変わっていったのです。例えばご飯を食べているときに、料理の入った皿を床に投げたり、悪態をついたり。私は家に居ることを辛く感じるようになりました。同時に、私の心は学校からも離れていってしまいました。
私の異変に気づいた母は、「いじめられてるの?」「友達とけんかしたから?」と気遣ってくれましたが、その時の私の心には、どれも当てはまりません。確かに友達とも疎遠になっていきましたが、それが原因ということはなく、なぜ学校に行けないのか、自分でも本当に分からない状態でした。
一つだけ言えることは、学校を休んだとき、私はとても楽な気持ちになれるということでした。平日は両親とも仕事で家にはおらず、母が用意してくれた冷凍の昼ご飯を一人で食べながら、「とてもおいしい。」と思ったものです。そのうち完全な不登校となり、給食は止められ、「今頃は、クラスメイトからも、先生からも、不登校のレッテルが貼られてしまったんだろうな。」と、思ったりしました。今でも正確に言い表すことは難しいのですが、当時はその状態を「サボり」としか表現できませんでした。
母は次第に焦り出し、手のひらを返すように「もう長くなっているのだから、いいかげんに学校に行きなさい」と私を叱るようになりました。「私もそう思っているよ。」と心で叫びました。そのうち、毎朝親と言い合いをすることが私の日課になり、苛立ちと焦りの空気が、私の家を覆うようになりました。
ある夜。母が、日頃あまり話をしない父に「周囲から『学校に行かせなさい』と言われていて、とても辛い。」と話しているのが聞こえてしまいました。
「結局、私のことは蚊帳の外で、他人に言われるのを気にしているだけなのか。」
なぜ学校に行けないのか自分でも理由が分からず、苦しみにさいなまれているのに、それを理解してくれない両親への怒りがあふれそうになりました。しかしそれ以上に、学校に行くことができない自分に、情けない気持ちで一杯でした。
そんな時、父の怒りは爆発しました。学校のことを聞かれても「分からない」としか私が答えないためでした。その矛先は買ったばかりのテレビに向けられました。コップを全力で投げつけ、破壊してしまったのです。破片を拾い集める母を見ながら、泣いて立ちすくむことしかできない自分を、私は心の中でずっと責め続けました。
「もうこれでおしまいだ。」学校に行きたくない。家に居たくもない。私は部屋に引きこもりました。
このような出来事を経て、私は施設に入ることになりました。生活が一変し、心に少し余裕ができると、不思議なもので「学校に行こう。」という気持ちが芽生えてきました。そして、通い始めた学校で、ある先生との出会いがありました。
その先生は、私がしばらく休んでも「多分明日も来ないだろう」と思わず、「明日はきっと来るはず」と期待し続けてくれました。苦手な数学の復習のために分厚いワークブックをわたしてくれて、分からないところを白紙で提出しても、他の生徒と違う扱いをせず、時には難しい問題に挑戦させるなど、私の学習習慣が身につくように仕向けてくれました。また、朝学習でも、放課後学習でも、いつも勉強に付き合ってくれました。この先生の接し方は、「私は期待されている。そして、信頼されている。」という気持ちを思い出させてくれました。このことが大きな救いになり、現在も自分の心を安定させることにつながっています。
先生が生徒の勉強に最後まで付き合うというのは、ごく当たり前のことかもしれませんが、あのような経験をした私にも、他の人と同じに、教師らしく厳格な接し方をした人は、その先生だけでした。こうした日々が積み重なり、私は受験に向かうことができ、現在の高校に合格することまでできました。
思えば不登校だった頃、私は人を信じることができませんでした。同時に父も母も、私のことを「明日も学校には行かないのだろう。」と決めつけていました。あの頃、私は不信感にまみれて生活していたのです。しかし、「この人は信じられない」などと決めつけるのではなく、人を信じてみようとする態度こそが大事なのだと、この先生が教えてくれました。
人に対して無理な期待を押し付けることが不信につながる。しかし、期待はするかもしれないけれど、ほんの少し我慢して、その人を待ってあげることが、人を信じる第一歩になる。
父が居なくなった実家に久しぶりに戻ったとき、明るくそして優しく出迎えてくれた母の顔を忘れることができません。私の合格を祝ってくれる母と話しながら、母も私も、前に進んでいることを実感していました。
これでいいんだ、よかった。と。