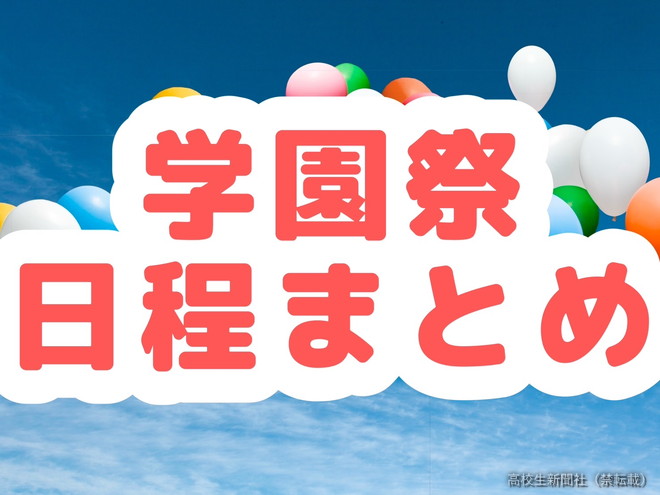データネット実行委員会(ベネッセコーポレーション・駿台予備学校共催)による2023年度大学入学共通テストの「生物基礎」の問題分析は次の通り。
― グラフや実験の解釈を通して思考力を問う設問が数多く出題された。難易は昨年並 ―
実験結果を論理的に考える力、グラフを読む力、計算力など、多様な科学的思考が問われ、分野融合形式もみられた。知識が必要な問題も、そのまま問うのではなく、知識を活用して判断する必要があった。昨年と比べ、全体のページ数は減少したものの、解答数・設問数・選択肢の数などは同程度であり、難易は昨年並。
大問数・解答数
大問数3は、昨年から変更なし。昨年17個であった解答数は18個に増加した。
出題形式
文章選択問題を中心に出題された。
出題分野
昨年と同様、特定の分野に偏ることなく、幅広く出題された。
問題量
昨年と比べて減少。昨年18ページであったページ数は14ページになった。
難易
昨年並。
大問別分析
第1問「生物と遺伝子」 (16点・やや難)
「生物と遺伝子」の分野から、細胞の特徴と細胞周期の内容を中心に出題された。Aでは、原核細胞と真核細胞に関する知識問題と、細胞内共生における宿主細胞と取り込まれた細胞の変化を予想する問題が出題された。Bでは、DNA複製開始点の数を求める計算問題、特定の時期に発現するタンパク質から細胞周期の時期を考察する問題、DNAの複製における基質の取り込みに関して考察する問題が出題された。細胞周期に関して新しい切り口で考察させる問題で、受験生には目新しかったと考えられる。
第2問「生物の体内環境の維持」 (17点・やや難)
「生物の体内環境の維持」の分野から、肝臓と免疫の内容を中心に出題された。Aは、胆汁と酵素の働きに関する実験を題材にしており、問2では得られた結論がどの実験の組合せから導き出されたかが問われた。Bは、免疫に関する知識と考察力が問われた。問3は基本的な知識を問う問題であり、答えやすかったであろう。問5は、予防接種に関して多方面から考える問題であった。三つの実験それぞれをすべて検討する必要があり、時間を要したであろう。
第3問「生物の多様性と生態系」 (17点・標準)
「生物の多様性と生態系」の分野から、物質循環とバイオームの内容を中心に出題された。Aは、光合成、窒素循環について知識をもとに推論および判断する問題が出題された。問3は、設問文をもとに水槽の生態系から窒素を除く操作が問われたが、判断に迷った受験生がいたかもしれない。Bは、バイオームの特徴に関する知識が求められた。問5は、人工衛星でとらえた地表の反射光のデータから植生の様子を推定する技術を題材に、バイオームの特徴の知識をもとに考えることが求められた。
過去5年の平均点(大学入試センター公表値)
- 2022年度 23.90点
- 2021年度 29.17点
- 2020年度 32.10点
- 2019年度 30.99点
- 2018年度 35.62点