勉強法についての悩みに、多くの受験生を合格へと導いてきた各教科の先生が、大学受験突破のためにアドバイス。駿台予備学校の生物科講師の山下翠先生に東京大学の生物を解くためのポイントについて答えてもらった。(構成・山口佳子)
圧倒的な量のデータを読み解き考察
リード文、複数の論文データや表など、数多くの資料を読み込み、比較、分析した上で考察等を記述することが求められる。
リード文や提示されるデータは圧倒的な量だ。これらの情報からさまざまな物質の複雑な相互関係を短時間で読み解き、事実を導いて的確にまとめる能力が問われる。
過去問に目を通して問題の傾向を体感しよう
君が1・2年生なら、試験で提示される膨大な情報を短時間で読み込む訓練をしておこう。
おすすめは新聞。毎日、一定時間、長い文章を読むことを習慣づけることで、読解力のアップ、短時間で長文を読む力などが養える。
君が3年生なら、4月すぐに2~3年分の過去問に目を通そう。
目的は、「相手を知る」こと。過去問には監修者などが東大の問題傾向をまとめている項もあるが、自分自身で体感することが大切だ。
どのような出題形式か、どれくらいの情報量を読み解かなくてはいけないのか、どれほどの記述をどれくらの時間でまとめなくてはいけないのか等を最初に知っておくことで、今後の目標が明確になる。
大問の一つだけ挑戦することから
また、いろいろなデータを比較する問題が多い、単純な知識を問う問題はない、といった傾向を知ることもできるだろう。知識が十分に入っていない段階だから、たとえ解けなくても気にする必要はない。問題に取り組む場合は大問のうちの一つだけを、制限時間を設けずに挑戦するなどで十分だ。
がっつりと過去問に向き合うのは、10月以降。理想は、「新テスト6:二次4」の配分だが、12月に入ると新テスト対策に追われる人もいるかもしれない。そういう人も、論述対策だけは早めに進めておこう。
山下翠先生(駿台予備学校 生物科講師)
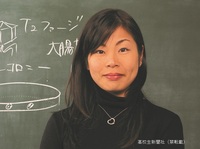
やました・みどり 高1から高3までの授業を多数担当し、熱意にあふれた分かりやすい授業は生徒から多くの支持を得ている。模試の出題や教材の執筆も担当。


















