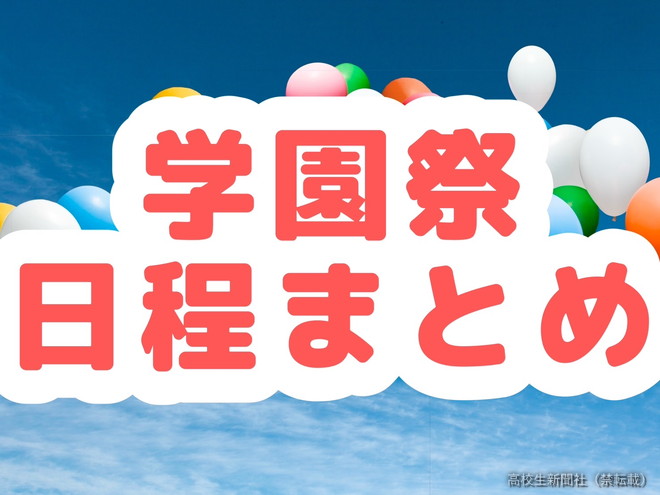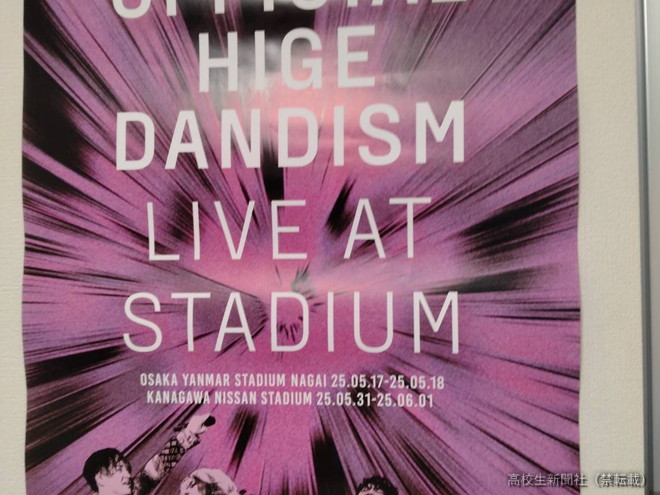【第1問】【第2問】【第3問】【第4問】【第5問】【正解】【分析】
データネット実行委員会(ベネッセコーポレーション・駿台予備学校共催)による2023年度大学入学共通テストの「現代社会」の問題分析は次の通り。
― 国際経済からの出題が増加。多様な資料を読み解き考察する力が求められた。難易は昨年並 ―
すべての大問で生徒の活動場面が題材となり、学習した事項を具体的な事象に関連づけて考察することが求められた。基本的な知識を中心とした出題であったが、文献や統計、模式図など様々な資料が扱われ、多くの情報を効率よく読み解く必要があった。国際経済分野からの出題が増加した。難易は昨年並。
大問数・解答数
大問数5、解答数30個は、昨年から変更なし。
出題形式
文章選択の問題が増加したが、昨年と同様に組合せ問題が過半数を占めた。文章中や表中の空欄に入るものの組合せを選択する問題が増加した。
出題分野
経済分野からの出題が減少し、国際経済分野からの出題が増加した。例年同様、「現代社会」の幅広い範囲から出題された。「現代社会」の学習内容を身近なテーマに置き換えて考える問題や、具体的な事象を一般化して整理する問題は特定の分野にとらわれず出題された。
問題量
昨年並。
難易
昨年並。
大問別分析
第1問「海外研修の体験から考える国際問題」 (25点・標準)
海外研修に参加した高校生の体験を切り口とし、国際経済分野を中心として出題された。問5では、輸入関税の有無を比較して解答を導くことが必要であった。問7は、先進国と開発途上国の医療資源の格差問題について、異なる複数の意見と具体的な政策を結びつけて考察する問題であった。
第2問「演劇を見た高校生が話し合う将来の目標」 (22点・標準)
演劇を見た高校生の会話文や劇団の主宰者のインタビュー資料をもとに、青年期や思想、経済の分野から出題された。問4では、日本経済の動向についての知識と、資料に示される1963年以降の有効求人倍率の推移とを結びつけて考察することが求められた。
第3問「大学の体験講義から考える現代の社会」 (20点・標準)
大学の体験講義に参加した高校生の学習をもとに、経済・国際経済分野を中心に出題された。問1は、GDPの名目と実質の違いについての正確な知識が求められた。問5では、「プラットフォーム」をキーワードとする会話文から、利用者の行動に対するプラットフォームどうしの競争について問われた。
第4問「裁判の傍聴を通して考える日本の政治と人権」 (22点・標準)
裁判を傍聴した高校生の感想文などをもとに、司法制度や基本的人権などの政治分野を中心に出題された。問2では、近代西欧の思想家の考えと、現実の刑罰の目的や性質を関連づけることが求められた。問7は、地方自治に関して、具体的な事例における政治参加の方法について会話文を読んで考察する問題であった。
第5問「『子どもの貧困』をテーマとした探究学習」 (11点・標準)
「子どもの貧困」についての探究学習という場面設定で、経済分野を中心に出題された。問1では、子どもの相対的貧困に関わる日本の状況や国際比較について、複数の資料を丁寧に読み取りながら解答することが求められた。問2は、子どもの相対的貧困の解決に向けた官民の取り組みについて、具体的に生じている問題と結びつけて考察する問題であった。
過去5年の平均点(大学入試センター公表値)
- 2022年度 60.84点
- 2021年度 58.40点
- 2020年度 57.30点
- 2019年度 56.76点
- 2018年度 58.22点