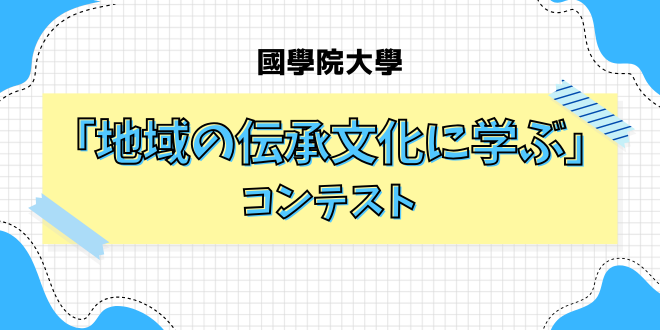【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
地域民話研究部門(団体)
- 最優秀賞
- 「松山平野南部の伝承調査 ~河童・大森彦七・落武者の里の謎を解く~」
- 愛媛県立松山北高等学校 郷土研究部
- 優秀賞
- 「和泉地区発・青葉の笛をつなぐ2~義平と おみつ 乱世に咲いた恋~」
- 福井県立大野高等学校 JRC「結」
- 佳作
- 「続・紀南地域における河童伝承~河童の正体に迫る~」
- 和歌山県立田辺高等学校 河童倶楽部
■審査員講評も参考にしよう!【 地域民話研究部門 講評 】
【 最優秀賞 】
「松山平野南部の伝承調査
~河童・大森彦七・落武者の里の謎を解く~」
愛媛県立松山北高等学校 郷土研究部
応募の動機
私たちは、これまで松山市小野谷地区を中心に地区の方々の協力を得ながら、現地調査を実施し研究を進めてきました。今年度は、伝承の調査地域を松山平野南部の、砥部町・松前町・東温市にまで広げ、民衆の信仰や戦乱の様子について調査していきました。地域での聞き取り調査や、文献をもとに、地域の伝承に含まれる謎に疑問を持ち解明することに挑戦しました。
研究レポート内容紹介・今後の課題
1.小野地区の河童(エンコ)伝承
小野地区の溜池に伝わっている河童(エンコ)伝承の調査を進めると、伝承が伝わっている背景に江戸時代の民衆の絶え間ない「水」との闘いの歴史や、天の恵みである「水」への祈りが隠されていることが分かりました。私たちは伝承の背景にある歴史的事象を追っていき、江戸時代の農村の生活や、自然災害との闘いについて解明することができました。
2.砥部・松前地区の大森彦七伝承
砥部・松前地区に伝わる大森彦七伝承は、南北朝期の合戦の様子を描いた『太平記』に記されています。砥部の住人大森彦七が、摂津湊川の合戦で楠木正成を切腹に追い込んだ後、砥部矢取川のあたりで美女に化けた楠木正成の亡霊に襲われたという伝承で、大森彦七供養塔の他、多くの伝承地が各地に残っています。しかし、同時代の『梅松論』等の資料を精査した結果、楠木正成を切腹に追い込んだのは高師泰の家臣であったと結論付け、
なぜ、太平記の作者が、大森彦七の物語を創り上げたのかについて推論していきました。
3.滑川地区の落武者伝承
松山平野南東部の山間にある東温市滑川地区には落武者伝承が数多く伝わっています。その要因として、一つ目は、滑川上流の独特の地形が落武者の隠れ里として適していたこと。二つ目は、滑川地区の人々は、山の民として行商して生計を立てており、他村に入る場合の家由緒として平家の落武者伝承を必要としたこと。三つ目は、他村から流入してきた人々が、滑川地区住民の持つ平家の家由緒に対抗するため、平家以外の落武者伝承をつくりあげていったこと。四つ目は、修験者等の「拝み屋」が、祈祷の際に村人が知っているであろう歴史上の有名人を祀るように告げたこと。以上の4点が滑川地区に数多くの落
武者伝承が伝わっている理由であるという結論に達しました。
4.今後の課題
今回の作品は文献資料に頼りすぎ、現地調査が希薄になった点が反省点になりました。フィールドに赴いて現地の方々からお話を聞くことで、私たち自身の伝承に対する理解度が深まり、よりよい研究ができると考えています。また、山間部の滑川地区の調査では、集落の過疎化等により、伝承はもとより、集落自体が消滅していく危機感を強く感じました。私たちは若い世代としてできることを尽くし、伝承の復活や記録に貢献していきたいと考えています。


最優秀賞の受賞者コメントは近日公開!
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 優秀賞 】
「和泉地区発・青葉の笛をつなぐ2~義平と おみつ 乱世に咲いた恋~」
福井県立大野高等学校 JRC「結」
応募の動機
私たちの市には源義平が遺した「青葉の笛」伝説がある。全国唯一の「笛資料館」もあったが、この3月に廃止された。篠笛演奏の継承者も少なくなり、この美しい民話の伝承が途絶えてしまうのでは、と昨年研究を始めた。今年は退職された先生に「義平38代目の子孫、朝日義治さん」を紹介いただき、夏休みに訪問できるという好機に恵まれた。「平治物語」も参照し近県に伝わる義平伝説も調べた。
研究レポート内容紹介・今後の課題
〈青葉の笛伝説〉
平安末期、源義朝の長男である義平は、平治の乱(1159年)で敗走する際、福井県足羽の奥、朝日の里(和泉)に落ち延びた。義平は村長「朝日助左衛門」の娘「おみつ」と恋に落ち、おみつは子を宿した。しかし父・義朝の死を知り、義平は京に上り仇を討つことにした。別れ際、身重のおみつに形見を託した。「もし生まれて来る子が男ならば、いずれ源氏の嫡男として京に上り旗揚げさせよ」と刀と白旗を。「もし女子であったら、この里で静かに暮らし、時々この笛を吹いて自分を偲んでほしい」と、一管の横笛を残して去った。義平は、永暦元年(1160年)京で捕えられ処刑された。村に残ったおみつが生んだのは、女の子だった。義平の死を知り、形見の笛を吹いて過ごし、子孫に笛を伝えた。この笛が現存しており、民謡「質調衣ちょい」に伝説が歌われている。
Ⅰ.「笛伝説はどのように伝承してきたのか」
① 平安~江戸:朝日家の「笛」や家系図、古文書により朝日村の狭い範囲で語り伝えられた。
② 江戸末期~昭和:伝説を歌った民謡「質調衣ちょい」が作られ、穴馬(和泉村)の民が歌い踊ることで他集落にも広まった。
③ 昭和の終わりに東洋音楽学会の研究者が和泉村を訪れ「笛伝説は真実であろう」と結論づけ発表した。平成初期に和泉村を「歴史と文化のまち」として活性化し観光客を呼び込もうと村役場が「笛資料館」を作った他、若年層へのふるさと教育として踊りや笛作り、祭での演奏活動を始めた。
Ⅱ.「義平が和泉を訪れた時期はいつか」
「平治物語」では、義平が隠れ住んだのは平治元年末から翌年始めの「数日間」であるが、これでは笛伝説と矛盾する。義平の館跡「御所ケ平」や弓の鍛錬所「的石・的坂」などの地名が多数残っていることと朝日家古文書から、滞在期間は「少なくとも2~3年」と言える。
Ⅲ.「義平の足跡は。他の伝説は存在するのか」
近県にも義平が通過した伝説が残されている。美濃「狒々退治・祖師野八幡宮での募兵」、越中「蟹江の渡し」、飛騨「久津八幡宮、朝裏八幡宮での募兵」などだ。しかし、「青葉の笛」を含めこれら5つの出来事が同時多発的に「平治物語」と同じ数日の間に起こっている。各場所間の移動も考えると、物理的にこれらが雪深い地で短期間に起こるはずがない。このことから、各民話や八幡宮勧進は「平治物語」の仇討ちの場面と時期が混同され、誤って伝えられたと考える。唯一「久津八幡宮の棟札」のみが「義平が保元年間に勧進」と書かれており、朝日家の資料と合わると「義平がおみつと恋に落ち、子を宿したことを知り、形見を遺した」が、創作ではない説に近付くことができた。
Ⅳ.「笛以外の形見は存在するのか」
最後に、義平が遺した「刀」を捜した。古文書には「太刀」や「脇差」「守刀」と様々であった。歴史博物館が保管する大戦中の「金属類回収令」をすり抜けて残った「朝日家伝来の刀」にたどり着いたが、ずっと後の室町時代(1436年)の「備州長船師景作の脇差」(小刀)であった。天正2年(1574年)に太刀や馬具が盗まれた、という文書もあるが、1730年以降の文書は「脇差」となっていることから、何かの縁でこの脇差が朝日家にやってきて、以降「青葉の笛」と同じく家宝として大切に子孫代々伝えられたのだろう。
笛以外の形見にはたどり着けなかったが、研究から、私たちは昨年より一歩進んだ仮説を立てることができた。「源義平は保元年間に和泉の御所ケ平に数年間住み、子を遺した」これはおそらく史実である、と。
笛資料館は廃止になったが、青葉の笛関連の資料が市街地の歴史博物館に移転された。町の中心部に展示が移ったことで、特別展、企画展、郷土史ミュージアムコンサートなど、高校生の企画展も行えるのではと期待している。また、市が地域活性化ビジネスプランを募集しており、私たちは「笛とほたる鑑賞会」や「観月と講談 青葉の笛」など、歴史と自然を楽しむイベントを提案している。今後はさらに若い世代向けに、ゆるキャラや観光系V-Tuber の開発など、青葉の笛を広く知ってもらえるように発信できる策を考案したい。



受賞者コメント
この度は、優秀賞をいただき光栄に思います。昨年度の先輩の研究に引き続き、このような素晴らしい賞をいただけてとてもうれしいです。地域民話ということでフィールドワークなどの活動を通して地元のことをより深く知ることができました。地域の歴史を後世にも伝えていくために、この活動をつなげていきたいです。本当にありがとうございました。
人口減少が進む地域の歴史を後世に伝えていきたいと思ったため、コンテストに応募しました。先輩の研究を引き継いで調査を進めましたが、笛資料館が閉館したため、昨年のような演奏体験などができなかったことが苦労しました。
探究活動を通じて、地域に伝わる民話と、地域的特色とのつながりを知ることができました。また、私が住んでいる地区の伝説について知ることができたし、他の地域のことについても学ぶことができました。
地域イベントでよく紹介や劇が行われているため、伝承文化を身近に感じています。伝承文化の継承は、とても大切なことだと思います。地域の歴史をつなぐために、もっと若者の行動も重要になると思います。また、様々な世代の交流の架け橋になることも魅力の一つだと思います。地域のことをより深く知ることができ、地元への誇りや地元愛にもつながります。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 佳作 】
「続・紀南地域における河童伝承~河童の正体に迫る~」
和歌山県立田辺高等学校 河童俱楽部
応募の動機
昨年行った、紀南地域の河童伝承に関する調査・研究に引き続いて河童伝承について調べるなかで、河童の正体に興味を抱いたこと。また、昨年学校の先生から聞いた「河童の正体は落ち武者である」という旨の話をきっかけに、いずれも紀南地域に多く伝わるものである河童伝承と落人伝説の関連性を探ってみたいと考えたこと。
研究レポート内容紹介・今後の課題
〇仮説
「紀南地域の民話における河童の正体は落人である」という仮説を立てた。それに基づき、私達の住む紀南地域における河童伝承と落人伝説の関連について調査することとした。
〇方法
図書館およびインターネットでの下調べ、地域のボランティアガイドの方々への河童伝承・落人伝説についての聞き取り調査を行った。その際にお借りした地域の民話に関する書籍の著者である宮本惠司氏に対し、地域の河童伝承・落人伝説、両者の関連について教えていただきたいという旨の手紙を送り、返答を得た。また、大塔行政局大塔教育事務所の職員の方々、龍蔵寺の住職の方への聞き取り調査を行った。
〇紀南地域に伝わる河童伝承
「出合いの淵の河童」「笠松の淵の河童」の二つの伝承を紹介している。
〇紀南地域に伝わる落人伝説
「餅つかぬ里(大塔町)」「鯉のぼりを出さぬ里」「平維盛の熊野落」の三つの伝説を紹介している。
〇結果と考察
河童伝承と落人伝説の関連性を見出すべく、 得られた情報を元に「空間的な重なり」、「時間的な重なり」、「河童と水死体の共通点」の三つの観点から考察した。
〇結論
結果・考察から、今回の調査では根拠となるものが不十分であり、「紀南地域の民話における河童の正体は落人である」と断定することは難しいと結論付けた。
〇研究を通して
・書物として現存しているのではなく、人々に語り継がれる形で残ってきたものである。
・時代背景と照らし合わせて深めることが出来なかった。
という点に民話ならではの研究の難しさを実感した。
また、時代が進むにつれて自然現象などの脅威を呼びかける教訓から人々の娯楽として語られるように変化していることから、これからの時代を生きる私たちは民話を一つの文化として語り継いでいくべきなのか、また、仮に語り継ぐとすればどのような形で語り継いでいくべきなのか、民話との向き合い方や語り継ぐことの意義について改めて考えさせられた。
河童の正体をとらえることはできなかったが、河童伝承および河童の存在は水神信仰や清流を守ることの重要性の訴えから生まれ、のちの時代に水難事故から人々を守るための教訓へと転じていったのではないか、実体はなくともそれらの民話としてのあり方が正体と言えるのではないか、と考える。
さらに、今回研究した民話は誰によっていつから語られ始めたのかという新たな疑問が出てきた。
受賞者コメント
私たちの探求活動を評価していただきありがとうございます。今回の活動では地域にまつわる河童の民話に着目し、なぜこのような民話が今日まで伝えられてきたのか掘り下げました。今回の受賞を励みに今後も伝承文化について調べていきたいと思いました。本当にありがとうございました。
学校の探求の授業で紹介されていたため、コンテストに応募しました。本やインターネットだけでなく、実際に現地に赴いて調査を行うことを大切にしました。グループでのコミュニケーションを通して、相手にわかりやすく自分の意見を伝えることや相手と意見を共有することの大切さを学びました。
家に地元の民話をまとめた絵本があり、小さい頃からそのお話が好きだったため、伝承文化に興味を持ちました。熊野古道が身近にあり、それにまつわる歴史や伝説にふれることが多かったので伝承文化を身近に感じています。
伝承文化は昔から人から人に繋がれていったものであり、そこにはたくさんの人の思いや考えがつまっていると思います。そこが伝承文化の魅力であり、伝承文化を継承していくことは地域について知る上で重要な役割があると思います。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
■審査員講評も参考にしよう!【 地域民話研究部門 講評 】