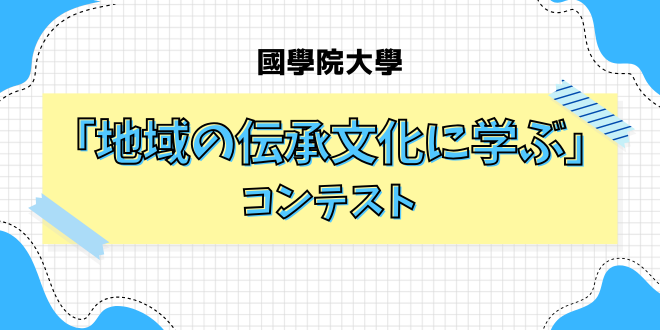【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
地域文化研究部門(個人)
- 最優秀賞・折口信夫賞
- 「千葉県大網白里市山辺地区における講の現状」
- 千葉県立長生高等学校 2年 戸田 武瑠
- 優秀賞
- 「上三原田の歌舞伎舞台~上三原田の天才が造りだした日の本一の廻り舞台~」
- 群馬・東京農業大学第二高等学校 3年 嶋原 瑠泉
- 「学生のボランティアと運営参画から見た湘南ひらつか七夕まつりの継承」
- 東京・渋谷教育学園渋谷高等学校 2年 石原 深生
- 佳作
- 「伝統芸能祭りから紐解くジェンダー平等への明るい未来」
- 長崎県立長崎東高等学校 1年 南部 夏步
- 「糸満ハーレーの歴史的背景と文化的意義」
- 沖縄・昭和薬科大学附属高等学校 3年 大城 佳珠帆
■審査員講評も参考にしよう!【 地域文化研究部門 講評 】
【 最優秀賞・折口信夫賞 】
「千葉県大網白里市山辺地区における講の現状」
千葉県立長生高等学校 2年 戸田 武瑠
応募の動機
自分が住む地域の路傍に「諸畜犬…」と書かれた卒塔婆が立っていることに気づき、疑問に思い調べたところ、子安講の女性たちが行う「犬供養」という行事であることがわかった。自分の住む地域で現在も講が活動していると知り、その現状に興味を持った中で、学校の先生から本コンテストの紹介があり、応募に至った。
研究レポート内容紹介・今後の課題
講は農村社会において、村民の相互扶助や共同体の維持を目的に結成された集団であり、かつては、民間信仰に基づき結成された講や、金融や労働、社交や娯楽を目的として結成された講など、様々な講が存在し、農村社会と強い結びつきを持っていた。しかし、近年の農村社会では少子化や過疎化などを背景に講が縮小、廃止される傾向が強まっている。
本研究の調査対象地である大網白里市山辺地区は千葉県中部に位置し、谷津などの里山の景観が残る一方で、近年では大規模な宅地造成や集落の過疎化・少子高齢化が進み、地区内の環境は変化している。このような山辺地区における講の文献資料は乏しく、その詳細や現状について文献資料から窺うことはできなかった。そのため、現地を訪れて聞き取り調査を行った。
聞き取り調査では各集落を訪れて屋外で出会った住民の方に聞き取りを行った。また、より詳細なお話を伺うために、お寺の住職の方や元区長の方など地元の事情に詳しい方に連絡を取った。酷暑の中での調査であり、集落を訪れても屋外に住民の方がいないことが多く、調査は難航したが、出会った住民の方に、別の集落の方を紹介してもらうなど住民の方のご厚意により山辺地区の全ての地区で聞き取りを行うことができた。
結果として、山辺地区では民間信仰で結ばれた5種類の講、子安講や二十三夜講(三夜講)、題目講や甲子講、三峯講の計20団体が現在も活動していることが明らかとなった。しかし、それらの講は既に民間信仰として結ばれた本来の目的は失われ、住民同士の歓談や飲食の場として存続されていた。中には高齢者福祉事業で組織された高齢者団体に再編された講も見られた。また、集落の過疎化により講の高齢化が進み、講行事が縮小・廃止される傾向が強いこと、特に講の中心層が70代であり、親から子への世代間の継承がされていないことから近い将来に多くの講が消滅すると思われる。このような講の縮小・消滅を避けることが難しい現状において、今のうちに講の活動を記録することが急務である。加えて、講で用いた道具なども記録し、保存環境を整備することが必要である。
今後の課題として、現状が不明瞭である他地域の調査を進め、現代の農村社会における講のあり方について調査していきたい。


最優秀賞の受賞者コメントは近日公開!
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 優秀賞 】
「上三原田の歌舞伎舞台
~上三原田の天才が造りだした日の本一の廻り舞台~」
群馬・東京農業大学第二高等学校 3年 嶋原 瑠泉
応募の動機
元々、國學院大學が私の志望校であった為、担任の先生に勧められたことがきっかけでした。今回のテーマである「上三原田の歌舞伎舞台」は幼い頃からいつも行く歯医者の近くにある古い建物・他校の小学校の友達がこども歌舞伎に出演していたという印象がありました。長い歴史と世界に誇れる技術をもつ上三原田の歌舞伎舞台を沢山の方に知ってもらいたいと思い、本コンテストに応募しました。
研究レポート内容紹介・今後の課題
私の暮らす地域の隣に「上三原田」という地域があり、「上三原田の歌舞伎舞台」という国の指定重要有形民俗文化財があります。上三原田の歌舞伎舞台は、1819年に「永井長治郎」という水車大工によって造られました。ガンドウ返し・遠見・回転舞台・二重セリの4つからできており、「この地方に類例をみない」と言われる程唯一無二の舞台です。ガンドウ返しは、横の板壁を倒して舞台面を広く見せる機構・遠見とは、後ろのガンドウを倒すことによって造られる機構です。特に回転舞台(柱立廻式廻転機構)、二重セリ(セリヒキ機構)の2つは国内・世界でも例を見ない特殊な造りとなっています。二重セリは公演時には屋根裏25人・平舞台15人・奈落35人の3部門の操作員により、操作をしています。その他にも客席や舞台小屋にも様々な工夫と配慮がされています。研究レポートには、歌舞伎舞台の構造の他にも、上三原田の歌舞伎舞台が地元の住民達と共に歩んできた205年間の歴史が書かれています。
上三原田の歌舞伎舞台は昔からあくまでも農村歌舞伎を披露する場だった為、観客に鑑賞料はとっておらず、観客は良いが地元の方から見ると大きな負担になっていること・舞台を守り続けていくこと・操作を伝えていくことが1番の課題としてあげられます。今回のレポートを書くにあたって取材させていただいた上三原田歌舞伎舞台操作伝承委員会の
方も舞台を守り続けることが大変だと語っていました。昔から地元の人たちに愛され、日本でも唯一無二の構造をもつ舞台を1人でも多くの人に知って、文化を伝承してもらうことが解決策に繋がるのではないかと考えています。



受賞者コメント
入選したという驚きと、上三原田の歌舞伎舞台を知ってもらえたという嬉しい気持ちです。この作品を完成させるのには私1人の力ではなく、沢山の方にお世話になったので、感謝を伝えたいです。
國學院大學が志望校だった事と、担任の先生に勧められた事がきっかけでコンテストに応募しました。私の住む地域にはいくつか有名な伝承文化があり、その中でも特に魅力を感じた、世界に誇れる唯一無二の文化がある上三原田の歌舞伎舞台にしました。また、特に上三原田の歌舞伎舞台には、小学生が参加できる子供歌舞伎があり、私の友達も出演していたこともあったので研究してみようと思いました。
実際に現地へ行き、伝承委員会の方に直接お話を伺い、自分でも舞台のセリに上がってみたりと、体験したことを書くことを重要視しました。工夫した点は見やすくするために、写真には番号を振ったり自分でイラストも描いたところです。苦労したことは、歌舞伎舞台が当時は重要視されておらず、資料が少なくて村誌や現地の取材等からの情報のみでまとめるのが難しかったところです。研究を通して、自分の周りにはまだまだ知られていない文化財が沢山あるのだということを学ぶことができました。
小学生の頃、総合の時間で自分の住む地域の歴史について勉強したことがきっかけで伝承文化に興味をもつようになりました。自分の見える景色でも、昔は無かったものやあったものというのを学ぶことが楽しかったからです。
今回のコンテストを経て、伝承文化をより一層身近に感じました。テーマの上三原田の歌舞伎舞台は私が幼い頃から通っていた歯医者の近くにあり、横を通っていました。何気なく通り過ぎている建物でも貴重な文化財や古くからの伝承があったりするのだということを身を持って実感しました。
私がテーマにした上三原田の歌舞伎舞台も当てはまるのですが、伝承文化を継承していくことが難しい課題となっていると思います。やはり、伝えていく人がいなければ文化は繋がれていきません。いかに若い人たちに伝承文化を知ってもらう・興味をもってもらうか。それが継承していくという面で一番大切だと考えています。
伝承文化の魅力は歴史の空白があるという点だと思います。民話でもそれは本当にあった出来事なのか、私の書いた上三原田の歌舞伎舞台を造ったと言われる永井長治郎は本当に実在した人物なのか。それは現代に生きる私たちでは推測や想像でしか考えることができません。ですが、当時の人の気持ちを想像したり、調査をする中で話を伺ったり、文化財に触れることで、自分なりの答えを出すことができると思います。歴史の空白があるからこそできることであり、真実を多面的な見方から探し出せることに魅力を感じています。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 優秀賞 】
「学生のボランティアと運営参画から見た湘南ひらつか七夕まつりの継承」
東京・渋谷教育学園渋谷高等学校 2年 石原 深生
応募の動機
学校の課題として論文を書いた後、応募できるコンクールの紹介をいただいた。その中で最も私のテーマに沿ったコンクールを探しているうちに、このコンテストを見つけた。テーマがピッタリなこともあったが、去年の講評やコンテストの概要を確認した際に私の伝統文化に対する考え方に通ずる所を感じたので、応募を決めた。
研究レポート内容紹介・今後の課題
若者のまつりへの参加意欲は減少傾向にある。多くの人がまつりの継承を重要視する一方で、参加意欲については低い傾向にある。このような背景を踏まえ、本研究は、湘南ひらつか七夕まつりに焦点を当て、特に小学生から高校生の若者のボランティアや運営参画の現状と課題を明らかにした。
調査では、まず、「学生の運営参画」が実際にどれだけの課題として重要視されているか、湘南ひらつか七夕まつりの実行委員会を構成する市役所や団体、委員会の方々に取材をした。次に、明らかにした運営側の想いに対し、小学生98名・高校生60名に七夕まつりの参加実態と参加意欲についてアンケート調査を行った。
以下に調査結果と考察をまとめる。
《運営側としての若者の参加・参画に対する取り組み》
数年間、平塚青年会議所(JC)が中高生向けの運営参画プログラムを行っている。平塚JC は、この活動を通して地域の若者が長期的に祭りに関わり、将来的な担い手になることを期待している。しかし、現状では自発性や学生の告知の範囲の狭さが課題とされている。
《学生のまつりへの参加実態と意欲》
小学生は学校活動を通じて七夕まつりに参加する一方、高校生の参加率は低く、ボランティアや運営参画に対する関心も薄いことが明らかになった。祭りへの意識は、高校生の多くが祭りの存続を望むものの、伝統継承の役割を担う意識は低く、積極的な参画は少ない。さらに、小学生は過去の参加経験があると今後も参加意欲が高まる傾向があるが、高校生は参加意欲が低く、告知不足も影響している。学生が友人と参加できるような活動が
望まれている。
《考察》
調査を通して、湘南ひらつか七夕まつりの継承のために目指す若者に関する目標は、「学生が主体性をもって七夕まつりの運営参画をする」ことであるべきだと考えた。しかし、現状では学生参画に多くの課題がある。運営側や地域行政は、まつりを通じて地域を活性化し、若者に地域文化の担い手となってほしいと期待しているが、特に高校生は参加意欲が低く、まつりに関わる意義を感じていない傾向が見られる。これは運営側と学生の意識にズレがあることが一因であり、学生が自ら発信したり友人を誘ったりといった広がりも生まれていないため、参加者が増加しにくい状況にある。また、告知範囲が市内の一部に限られていることから、特に市外から通学する学生に情報が届かず、さらに学生の運営参画が広まりにくくなっている。
小・中学生の段階でまつりに親しむ機会を増やし、学校との連携を進めることで、学生の長期的な関わりを促す必要性が示唆される。

受賞者コメント
まさか優秀賞をいただけるとは思っていなかったので、素直に嬉しいです。この研究を続けて良かったし、途中で挫けずに最後まで書ききってよかったです。努力の結果が出た嬉しさもありますが、自分が楽しいと思って続けた調査が認められたことが非常に感慨深いです。そして何より、協力してくださった方々に心からのお礼を伝えたいです。指導をしてくださった担当の先生方、インタビュー調査を快く引き受けてくださった平塚市役所や平塚青年会議所の方々、夏休み目前や夏休み中にも関わらずアンケートへの協力を承諾してくださった先生方、さらに回答してくださった生徒の皆様も、本当にありがとうございました。
学校の課題として論文を書いた後、応募できるコンクールの紹介をいただきました。その中で最も私のテーマに沿ったコンクールを探していたところ、このコンテストを見つけました。テーマがピッタリなこともですが、去年の講評やコンテストの概要を確認した際に私の伝統文化に対する考え方に通ずる所を感じたので、応募を決めました。
昔から、地元の七夕まつりは大好きでした。小学校時代に3年半シンガポールに住んでいた経験があるのですが、毎年夏の一時帰国で七夕まつりのじゃがバターを食べるのが一番の楽しみでした。その頃から祭りにより深く関わりたいと思っていたものの、新型コロナウイルスの流行で中止された時期があったことと、中学から都内の学校に通い始めたことで、少し遠い存在になってしまっていました。
調査をする直接のきっかけとなったのは、2023年の夏、運営に携わってみたいと思い立ったことでした。いくらネットを漁っても、運営手伝いの募集のようなページは見つからなかったのです。そのような活動を行っていないのか、或いは見つからないだけなのか、当時はわかりませんでした。しかし、祭りを続けるために若者の参加が欠かせないことは確かだと思い、七夕まつりへの学生の運営参画を広めるためにどうすればいいか考え始めました。
学校で、一年間をかけて調査するテーマを決めなさいと言われたとき、七夕まつりでの学生の運営参画について研究することを決めました。探究活動を進めるにあたり、拘りを忘れないこと、調査において妥協をしないということを常に忘れないようにしていました。私は元々、アンケート調査を小・中・高校の全てで行いたいと考えていましたが、夏休み直前になってしまったことで初めは小学校にしか了承を得る事ができませんでした。しかし、調査内容で妥協したくなかったため、粘って夏休み中に他の高校にもご協力をお願いした結果、やっとOKを出してくれる高校を見つけることができたのです。ギリギリになってでも調査に拘る意思を貫いたお陰で、自分自身も満足のいく研究ができたと思います。
また、調査の対象である「平塚市の学校に通う生徒」「運営側に立つ方々」の気持ちを全力で汲み取ることも重要視していました。どのような調査方法で、どのような質問をすればよりストレートな意見が聞けるか、模索しながらの調査でした。行動が一番だな、という気づきが大きかったです。自分から連絡することと、コミュニケーションをとること、これらがあってはじめて活動に協力してくださる方々がいるのだ、と改めて実感しました。
小学校時代に海外に住んでいた中で、日本の文化のユニークさを感じる場面がすごく多かったことです。特に、比較的新しい国であるシンガポールの、さまざまな文化が入り混じっている様子をみて、伝統や文化の面白さを感じていました。また、先述したように、地元のまつりも昔から好きだったため、元から気になる分野ではありました。改めて考えると、伝承文化は昔より遠い存在になっている気がします。現代を生きる多くの方がそうだと思いますが、特に学生時代の忙しさから、身近であるはずの伝承文化に関わる機会少なくなり、参加意欲も低くなっているような感じがします。より多くの学生・若者が伝承文化を身近に感じられるようになることを願っています。
伝承文化を楽しみ、大切に思う人々がいる限り、それを継承していく重要性は変わりません。しかし、現代の価値観に合わせて変化を続けることも伝承文化の一つの在り方だと思うので、バランスを取りながら、それでも変わらず様々なひとに受け継がれ愛され続けることがこれからの伝承文化の理想の形だと思っています。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 佳作 】
「伝統芸能祭りから紐解くジェンダー平等への明るい未来」
長崎県立長崎東高等学校 1年 南部 夏步
応募の動機
生まれた時から住んでいる長崎市の伝統芸能祭りである長崎くんちが大好きであり、家族共々出演したこともあるため親しみを持っているが、伝統であるがゆえに女性が出演出来ないケースがあると知って疑問を持った。世界では「ジェンダー平等」が多く問われている中でこのような現状を詳しく知り、解決策を見つけるために調べようと考えた。
研究レポート内容紹介・今後の課題
日本や世界には多くの伝統的な祭りや文化がある。それらには伝統故の今日問われているSDGs にも含まれるジェンダー不平等問題が存在する。
私が住む長崎市の秋の大祭、長崎くんちも例に漏れず古くから守られてきたジェンダー不平等問題がある。それに疑問を持った私は長崎くんちに造詣が深い方と以前女性の出演が認められていなかった町に女性として参加した方にインタビューをした。その結果、長
崎くんちは発祥当初神事の面が強かったが、現在では価値観の変化などから神事と行事の面に分かれてきており、行事面においては各町の状況や時代の流れに合わせてケースバイケースで変わらないように変わりながら少しずつ女性の出演者が増えていることが分かっ
た。これには町の後継者不足問題や高齢化・若者不足問題も関係しており、それらの問題解決のためにも女性の存在は欠かせない。実際に女性の出演が認められ出演した女性の方は、くんち出演を通して成長でき、この経験は今後大いに活かせると語っていた。また今
後も関わっていきたいと話されていた。
これらを踏まえると、今後は女性出演者の増加が考えられる。一方で長崎くんちに出演する女性を性的な目で見る方も少なからずいるため、女性が出演するための環境を整えたり、衣装を女性用のものにしたりするなど今後適切な配慮をし、そして出演希望の女性は
積極的に声をあげ、自ら行動する必要があると考える。
女性を理由に諦めるのではなく、共に生きる明るい未来が待っている。
今後の課題
長崎くんちは口伝えや記憶で受け継がれている内容が多いこと、そして各踊町の情報は各町内で保有していることが多いため、情報収集に苦労した。インターネットと文献や面会によるインタビュー、踊町の自治会長をしている祖父や出演経験のある父から多く情報を得た。結果的に鮮度が高く信頼性のある情報になったと思うが、今回はインタビュイーが2名だったため、長崎くんちに関わる色々な立場の方からより多くのインタビューを集
めることができれば、更なる解決策を提示できたと思う。
また女性出演者数や内容など、もっと詳しく調査できることもあったと思う。
今後はジェンダーのみならず、もっと広い視点で長崎くんちのこれまでとこれからを調査することも可能とも考えるし、私は7年に1度、担当が巡って来る踊町に住んでいるため、いつか出演し私の見識も広げていきたい。これらをふまえて今後の研究に活かしたい。


受賞者コメント
まさか私の作品が選ばれると思っていなかったため、驚きでいっぱいです。また、私の研究は全国にも通用するのだと自信になりました。もともと地域の伝統芸能や文化に興味があったため、コンテストに応募しました。
初めて論文を書いたため、書き方や伝え方、様々な面で苦労しました。探究活動を通じて、文章力はもちろん、地域の伝承文化の理解度や愛が深まりました。私の住んでいる町が精力的に伝承文化に取り組んでおり、自然と好きになりました。伝承文化を継承していくことは難しい問題だとは思いますが、まずは好きになってもらうことが重要だと思います。伝承文化の魅力は言葉や理屈ではなくて、祭り囃しの音を聞いただけで血が騒ぎ出すくらい大好きで、本能的に好きというような感じです。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
【 佳作 】
「糸満ハーレーの歴史的背景と文化的意義」
沖縄・昭和薬科大学附属高等学校 3年 大城 佳珠帆
応募の動機
私は高校2年生のとき、今回指導教諭をしていただいた内間先生が受け持つクラスの生徒だったのだが、当時先生が課外活動の案内をしていらしたときにこのコンテストの存在を知り、高3になって受験勉強が忙しくなる中、息抜きも兼ねて私がなんとなく親しんでいる地域の文化についてをこの機会に調べることが出来たらいいなと思い、応募することにした。
研究レポート内容紹介・今後の課題
沖縄は、15世紀に尚巴志が三山を統一し琉球王朝が始まる前から、その気候や立地を生かした文化を持ち、現在でも様々な地域文化が県内各地で行われている。私が生まれ育った地である糸満市も、特有の文化行事を持っており、今回は「糸満ハーレー」について研究した。
沖縄の昔からの俗諺に「ハーレー鐘が鳴ると梅雨が明ける」というものがある。ハーレー(ハーリー)とは、沖縄県各地で旧暦5月4日に、爬竜船(はりゅうせん)やサバニに乗り、「豊漁」や「航海安全」を祈願して競漕する海での行事のことである。糸満ハーレーは毎年旧暦5月4日に行われるのだが、この日は「ユッカヌヒー(4日の日)」と言い、沖縄で言うこどもの日にあたるため、子どもたちの健やかな成長を祈願しもてなす風習があった。元々旧暦の5月4日は沖縄最大の厄日とされていたことから、厄除けの意味で子どもたちの世話をしたりハーレー鐘を鳴らしたりしていたのだという。
糸満ハーレーの歴史はとても古く、13世紀末に第3代南山王である汪応祖が中国で見た競漕行事を持ち帰ったという説が有力とされている。また、本ハーレー行事の一つであるウグヮンバーレー(祈願競漕)も中国の競渡文化が元だと考えられている。
糸満ハーレーの特徴に、競漕前の祭祀行事がある。糸満には昔から聖域とされている場所があり、ハーレー行事の前にノロが祈願を行うミチンサンチンもそのうちの一つだ。ここでノロや神職者たちはハーレーの無事を祈願する。
旧暦5月4日の当日に一番最初に行われる競技が、ウグヮンバーレーである。ウグヮンバーレーは、ミチンサンチンでの祭祀を海に受け継ぎ、その後の白銀堂への祈願のための競漕である。行事終盤に行われるクンヌカセー(転覆競漕)では、レースの途中で一斉に舟を転覆させ、泳ぎながら舟を元通りにし、再び乗り込んで競漕する。ハーレー祭祀の最後に行われる競漕が、アガイスーブ(上り勝負)である。各村から選抜される最強の漕ぎ手によって争われる。
糸満ハーレーでは、その起源から行われてきた祭祀を現在も引き継ぎ行ったり、行事もそのまま旧暦の日程で行ったりなど、伝統を大事にしていることが分かる。ハーレー行事を行うには多額な費用と多くの協力が必要になるが、戦後もウミンチュたちの伝統として固守されてきている。
糸満ハーレーの儀礼や競漕は、糸満の人々にとってのアイデンティティや誇りの象徴となっていることが分かった。
本研究では文献調査を主に行ったが、糸満ハーレーは、起源から600年ほど経った現在まで長い間継承され続けている“生きた” 行事なので、もっとフィールドワークを行い行事の生き生きとした様子を伝えられると良かったというのが今後の課題として残った。



受賞者コメント
この度は、このような素敵な賞をいただくことが出来て、とても嬉しく思っております。実は作品を提出したときは、自分なりに頑張ったものの、たくさん課題の残る作品であったなと感じていて、このコンテストに応募したことをいい経験と考えてこれからに活かすことが出来るといいなと思っていた程度だったので、先日先生から入賞の知らせを聞いた時は驚きました。この探究活動は受験勉強の合間に行っていたものだったので、それがこのように形に残る思い出に出来て良かったなと感じています。
私は高校2年生のとき、今回指導教諭をしていただいた内間先生が受け持つクラスの生徒だったのですが、当時先生が課外活動の案内をしていらしたときにこのコンテストの存在を知り、高3になって受験勉強が忙しくなる中、息抜きも兼ねて私がなんとなく親しんでいる地域の文化についてをこの機会に調べることが出来たらいいなと思い、応募することにしました。
私は沖縄本島の最南部に位置する糸満市で生まれ育ち、この地域で長く継承されている様々な行事や文化にたくさん触れてきました。伝統行事は有名なものでいうと、「糸満大綱引」や「糸満ハーレー」があります。私はこれらの行事に幼い頃からたくさん参加してきたのですが、私の母と父はこちらの生まれではなく、この糸満という地域やここに暮らす人々との地縁的な繋がりが少ないため、私はそれらの行事に直接携わるような立場ではなく、主に「観客」として楽しむことが多かったです。
地域内での関わりや文化継承についての興味はあっても、自分自身に直接的な関係がないため、それらについての歴史や本質を知る機会も少なく、実際に経験することも難しいものでした。そのため、私はこの機会に数多くの地域の伝承文化の中でも幼い頃から長い間触れてきて、私自身にとって特に馴染みのある糸満ハーレーに焦点を当てて調べてみることにしました。
私は糸満ハーレーとは何かということを1番知りたかったので、まず市立図書館に通い、市の歴史が書かれた本や、ハーレーやそれに関する行事や祭祀について書かれた雑誌などを調べていき、ハーレーという行事が行われることになった経緯や歴史、それが持つ意味などを詳しく調べることを重要視しました。
ハーレーは、現在の沖縄が、琉球王国であった時代のそれよりも前のまだ三山に分かれていた頃から、600年ほど経った現在まで長い間継承され続けている生きた"行事なので、この行事の生き生きとした様を伝えられたらいいと思い、実際に今ハーレーシンカとして活動されている漁師の方や、ハーレー行事を執り行っている委員会の委員長に話を聞き、それを踏まえてもう一度文献で確認をするという工夫をしました。苦労したことは、色々調べていく中で、結局自分がこの研究を通してどのようなことを達成したいのか、どのように論文としてまとめたら良いのかが分からなくなってしまい、テーマ設定にものすごく時間がかかってしまったことです。この点に関しては、今回のこの研究の大きな課題点であったなと感じています。
今回の探究活動をする中で、文献調査を通じて、様々な情報源からデータを集め分析するという作業をすることで、情報の信頼性を見極める力が養えたように思います。また、課外活動という点では、主導的に学ぶ姿勢が身に付き、自分の興味関心のある分野について深く掘り下げて考えることができるようになりました。また、高校までの学生生活の中で、論文を書くということは中々無いことなので、論文の構成や書き方、言葉の使い方や文章の組み立て方などを考えながら書いていくことは、私にとってとても良い経験であったと思います。
今回私が研究した「糸満ハーレー」は、私にとってとても思い出深いものであると心得ています。「糸満ハーレー」行事の前日に、糸満ハーレーの次世代への継承を目的とした「少年少女ハーレー・門中ハーレー」というものが開催されます。これはタイトルの通り、糸満ハーレーの行われる字糸満地域やその周辺の地域の子どもたちや同じ門中の人々でチームを組み、船の速さを競う競技です。私は小学生の頃に、この「少年少女ハーレー」に住んでいる地域の子ども会のチームで毎年参加し、ハーレー行事を観戦するだけでなく、自らも体験しながら楽しんでいました。
また、私は小学4年生の頃に学校の音楽部に所属しており、部活動として糸満市で行われている「糸満ハーレー歌大会」に出場した事があります。この大会も先程の「少年少女ハーレー・門中ハーレー」と同じように、糸満ハーレーの継承を目標としたものなのですが、私はそれまで何度か経験したことのあるハーレーにここまでちゃんとした歌があることをこの際に初めて知り、驚いたことを覚えています。私はこの時、何度も見て経験してきたことなのに行事の本質はあまり分かっていないということに気づきました。考えてみると、この頃から少しずつ糸満ハーレーに対して興味を持ち始めたような気がします。
それぞれの地域の文化には、それぞれが持つ歴史や信仰などが密接に関わりあっていると思います。伝承文化を知り継承するということは、その地域について知ることや、それを踏まえてこれから発展していくためにどうすればいいかなど、ただ過去を振り返り歴史を知るだけでなく、よりよい未来を作っていくことにも繋がることだと考えているので、このような姿勢はこれからも大切にしていきたく、そうすべきであると思っています。
【目次(TOP)】【地域文化研究部門(団体)】【地域文化研究部門(個人)】【地域民話研究部門(団体)】【地域民話研究部門(個人)】【学校活動部門】
■審査員講評も参考にしよう!【 地域文化研究部門 講評 】