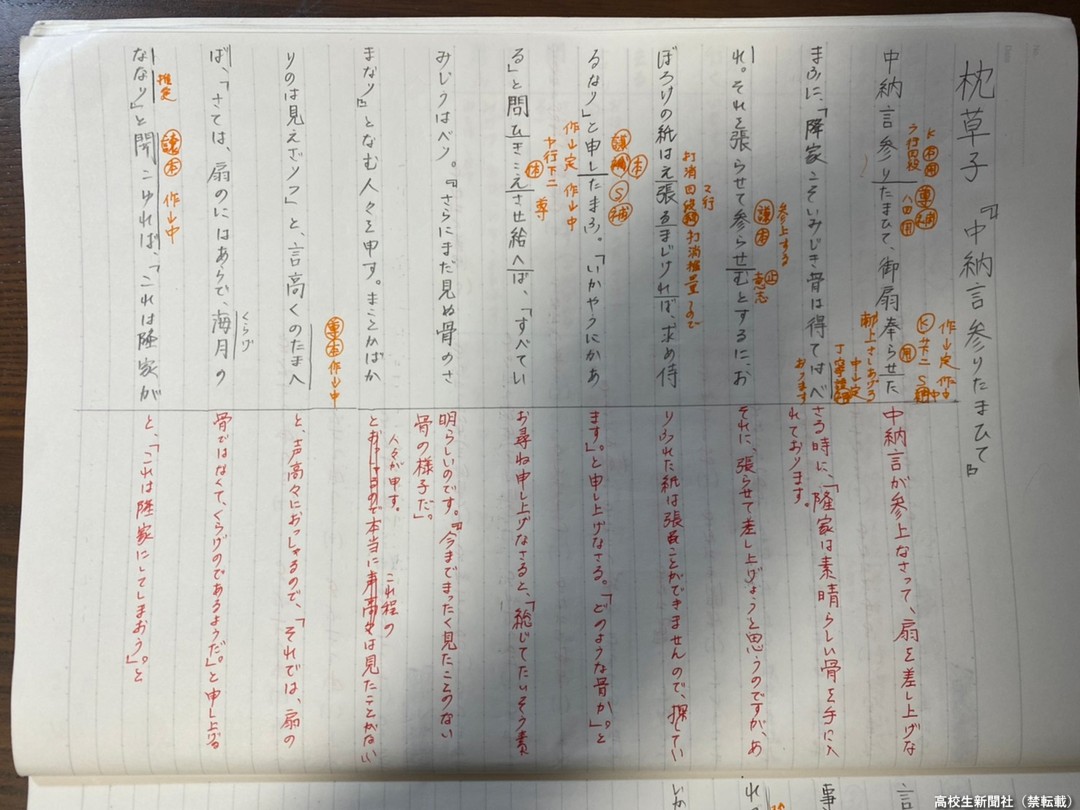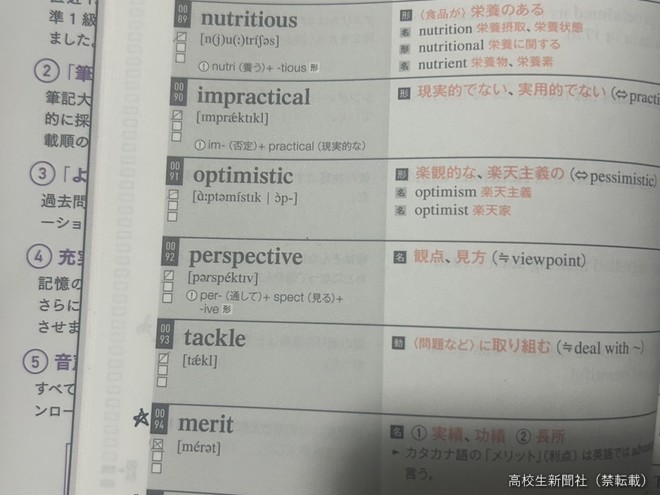佐野さんの読書体験記
ハンチバックの私達
静岡県立掛川東高校 2年 佐野夢果
そのニュースを知った時、身体中の臓器を全て体内から取り出されたような。そんな感覚だった。そして読了した今。一度取り出された臓器は、膨大な何かを詰め込まれ、私の体内に戻ってきた。その臓器から送り出される血液はあまりに速く、身体が張り裂けそうな感覚に陥った。「重度障害者の市川沙央さん、芥川賞受賞」。このニュースを知った瞬間全身の震えが止まらなかった。思えば私は、この瞬間から何か運命的なものを感じていたのかもしれない。そしてこの本を読まなければ、そう強く思った。
私もこの本の著者である市川さん、そして主人公である釈華(しゃか)と同じく、重度障害者だ。そして私の解釈が間違っていなければおそらく私も「せむし(ハンチバック)」である。当事者という言葉に該当するであろう私にとっても、著者が紡ぐ当事者性はあまりに衝撃的なものだった。それと同時に、私は当事者でありながら、著者が作中物語を通して糾弾する一人なのだということを、物語の冒頭から突きつけられた。きっと私は潜在的意識の中で思っていたのだろう。当事者性やリアルを描きつつも、前向きに清く明るく健気な、無理だと分かりきっていることは最初から望まない。そんな女性重度障害者が、この本の中では描かれているのだろうと。
だからページを開き、作中の言葉に触れた瞬間、鈍器で頭を殴られたみたいな衝撃だった。そして私が一生懸命築き、自身を守るために使ってきた障害者像を、その瞬間引き剝(は)がされた気がした。社会から求められる障害者像や同情をも寄せ付けない、力強さがこの本にはあったのだ。私は多分いつも考えていた。自分の立ち位置や周りから求められているものを。当事者や障害者として括(くく)られることを嫌がりながら、自分が一番当事者、そして障害者であるということを意識していたのだろう。思えば昔から私には障害がいつも付き纏(まと)っていたように思う。賞を取れば、「障害があるのにすごいね」と称賛され、車椅子に乗って一歩外に出れば、「可哀想に」と同情的な言葉を投げかけられることも少なくなかった。幼い私はそんな言葉を受け取るたびにモヤモヤし、悩んでいたように思う。私自身ではなく、障害者である私が評価されることや、悲劇のヒロイン的立ち位置に自分が位置付けられることに、違和感を感じ、いつしかその違和感は強烈な嫌悪感に変わった。しかしそんな言葉を投げかけてくる人達には悪意がないことも、自分自身痛い程分かっていた。だから次第にぶつけ先がないこの想いに、押し潰されそうになり、ある時抱えきれなくなったのだと今は思う。そして私は受け入れた。本質的に受け入れたのかは分からないが、フリだとしても受け入れると楽だった。可哀想な障害者の女の子がひたむきに頑張る前向きな姿がみんな好きだったし、もちろん前向きではない私を受け入れてくれる人もいただろうけど。そんな私を出すのには、あまりに勇気が必要だったから。だからいつしか自然と、苦しくても楽な方を自分から選んでいた。
「障害があるのに頑張っていて勇気づけられました」
みたいな言葉をもらうたびに、一番憎く「せむし(ハンチバック)」で「怪物」な自分が生きていい気がしたからだ。この本の主人公である釈華がもつ自己否定的な部分や世間からの疎外感は、100%ではないかもしれないが、あまりに自分と重なり、読んでいて心臓が握り潰されるみたいだった。そしてこの釈華や私の中で蠢(うごめ)く感情は外に出たとしても、どうにも周りからは理解されない、理解しようもない感情だという現実を突きつけられてしまう。そしてどんな言葉をかけられても、ルサンチマン的な感情を抱いてしまう鏡に映る私が嫌で、鏡に映るハンチバックの怪物がどうしても憎いのだ。しかし釈華がいうように、汚い泥がなければ私達は生きていけない。それを吐き出すことは私には出来ないが。だから前向きできれいなものとはまた別の、ぐちゃぐちゃしたものが、『ハンチバック』という形で世間に存在することが私はとてつもなく恐ろしくそして嬉しいのかもしれない。
障害者に限らず、様々な事柄に縛り付けられ、生きづらさを抱えている人は社会に一定数いるのではないだろうか。きっとそんな人達は、強烈な恐怖と共にこの本に救われるかもしれない。この本を読んで欲しくないという感情と共に、淡い期待を抱かずにはいられない。この本が社会全体に広まり、括られない社会になることを。生きづらさを抱える人に届くことを。
体験書籍『ハンチバック』(市川沙央著、文藝春秋)