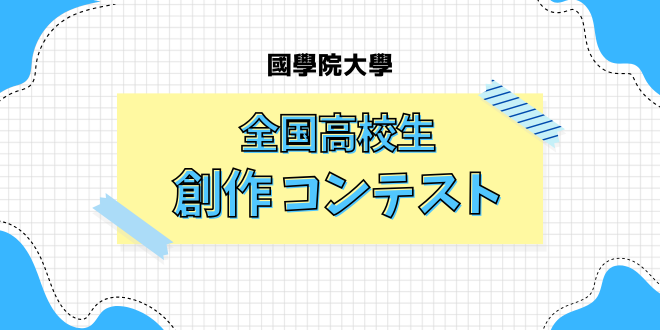【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
- 佳作
- 「魔法の指」藤井 あかり (島根県立松江南高等学校 2年生)
- 「だいだらぼっち」兪 鐔欣 (千葉・渋谷教育学園幕張高等学校 1年生)
- 「星々と漫才」山田 ひなの (愛知県立時習館高等学校 2年生)
- 「100ひく7」吉田 翔梧 (神奈川・慶應義塾高等学校 3年生)
- 「アクアリウムという星の下で眠る」香川 陽菜
(横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 3年生)
佳作 「魔法の指」 藤井 あかり (島根県立松江南高等学校 2年生)
『継続は力なり』それが先生の好きな言葉だった。
そろばん教室の見学に行くと、大柄な女の人が凛子を出迎えた。服装が地味で洒落っ気が少しもない。小学一年生のくせに性格がひん曲がっている凛子は、その人のことをウソ臭い笑顔で、信用ならないと思った。営業スマイルという言葉は知らなかったが、自分をそろばん教室に入学させて儲けたいだけだろうと考えたのだ。凛子は何事にも疑ってかかるような子どもで、知らない人を信用しないので人見知りが激しかった。
「凛子ちゃんっていうの?よろしくね」
その大柄な女の人というのが、どうやらそろばんの先生らしい。会ったばかりの人に、ちゃん付けで馴れ馴れしく呼ばれたので凛子は身構えた。先生はそんなこと露知らず、練習プリントを配ると、凛子にそろばんの一円玉や五円玉のことを教えはじめる。
「そろばんは大事に扱ってね。雨なんかで濡れたら珠の動きが悪くなってしまうから」
そろばんの珠は木でできているので、水に濡れると膨張して使い物にならなくなる。
「いい?たすときは親指、ひくときは人差し指だからね」
厳密に言うと、数字によってはたすときに人差し指を使うこともあるが、習いたての凛子がそんなことを知るわけもなく、先生もまたそのようなことは問題にしていなかった。
「じゃあ、私がたすって言ったら親指だして、ひくって言ったら人差し指だしてね」
先生はそろばんの珠を入れるように親指で空気を押し上げると、今度は人差し指を下に動かして先ほど押し上げた空気を切り裂き、空中のそろばんの珠を払った。
凛子はたすという概念を小学校で習ったばかりだ。そろばんに関しても計算する道具だということを漠然と知っているだけ。そもそもそろばんを習わせたがったのは凛子の母であり、凛子が習いたいと言い出したわけではない。……だから興味はあまりなかった。
「たす」親指
「ひく」人差し指
先生の言う通りに宙で指を動かす。滑り出しは順調だった。
「ひく」人差し指
「ひく」人差し指
「ひく」人差し指
「たす」人差し指
あっしまったと思って、人差し指を急いで引っ込めて親指をだす。凛子の口元が一瞬緩んだ。それから凛子ははっとして、自分が半笑いになっているところを、このよく知りもしない先生に見られてしまったかと思って先生を見上げた。すると先生も笑っていた。
それはある種のゲームだった。先生と凛子の対決なのだ。先生の仕掛けてくるワナを、凛子はすべてかわしてやり過ごさなくてはいけない。
「たす」親指
「ひく」人差し指
二度とは騙されないぞと思って、必死に指を動かした。
先生は子どもの心を掴む天才だったのだ。
ややあって凛子はそろばんの級の問題をするようになった。凛子がどうそろばんを弾けばよいかわからず途方に暮れていると、先生はしばらくそんな凛子の様子を観察していた。ようやく凛子の指がぎこちなく動き出すと、そのたびにうんうんと言って凛子を励ました。
割り切れるはずのわり算の問題がなぜか割り切れないと、先生は「あれ?どこが違ったかなあ。もう一回やってみて」と首を傾げた。凛子がもう一度その問題に取り組んで、今回も答えに余りがでて、しかも凛子がどこで間違えたのかを先生も気がつけなかったとなると、先生は凛子のそろばんを自ら弾いた。
先生のそれぞれの指にはいつも指ぬきがはまっていた。そしてよどみなく、無駄のないきれいな動きをする。凛子の知っているどんなものより緻密でなめらかで美しい。そろばんの音がパチパチパチパチと迷いなく次から次へと生み出され、そろばんの盤面の様子は目まぐるしく変わっていく。パチパチパチパチとただそれだけが、あたかも音楽のように凛子の鼓膜をくすぐる。鳥肌が立つ。
ドクンドクンドクン
ああどうして先生はこんなにも速く弾けるのだろうか。凛子は半ば信じられない気持ちで、もはや芸術の域にまで高められたそれに、見惚れた。
同時に凛子は悔しかった。自分も先生のようにそろばんを弾きたいと渇望し、それなのに凛子の指は思うように動かない。凛子は先生の指の動き一瞬一瞬を決して見逃したくなかった。
「子どもとそろばんが大好きで、ずっとそろばんの先生をやってきました。でも、今日で本当に私が先生をやるのは最後です」
先生は涙ながらに話す。凛子は小学五年生になっていた。先生は本当は先生をやめたくないんだと思った。子どもにはわからない大人の事情など聞きたくもない。
「みんなひとりひとりに、最後にメッセージを一言ずつ、言おうと思うから」
先生はみんなの机のところまで来ては、その大きな手でひとりひとりの手を握った。凛子の順番が来ると、やはり先生の手は凛子の手を包み込んだ。あたたかい。先生の目は潤んでいた。
「凛子ちゃん、凛子ちゃんは暗算のほうが珠算よりも進んでいるけど、珠算も暗算に追いつけるようになるよ。がんばってね」
凛子は大きく目を開けて、涙がこぼれないようにした。先生なら私の気持ちをわかってほしいと、矛盾したことを思う。
「私がいなくなっても、みんなはそろばんを続けて、もっともっと上手になってね」
先生との約束だと凛子は重く受け止めた。続けるよ、絶対続けるよ、きっと上手になるよ、先生みたいになるから……。
そろばん教室が終わってから、凛子は闇夜にまぎれて泣いた。先生、なんでいなくなったりするの?私はもっと先生に教えてもらいたかったんだよ。ねえ先生、先生は先生だよね?先生をやめたとしても、私の先生だよね?涙が凛子の頬を伝って、そろばんを入れているバッグにぽたぽたと落ちる。あ……と思って、凛子はバッグを脇へ避けた。そうするとさらにさらに涙が溢れた。先生とはもう、会えないんだ……。唐突に理解したとき、殺しきれなかった凛子の嗚咽が闇夜に静かに響いた。
そろばんの大会ははじめに長々とお偉いさんの挨拶が続く。退屈ではあるけれど、競技が始まる前にすでに疲れてしまって、選手たちに緊張する余裕を与えないという点ではよい働きをしている。
「よーいっ」
かけ算の問題用紙をみんなが一斉にひっくり返す音がする。
「はじめっ」
凛子は没頭していく。
天性の負けず嫌いはうねるように膨れ上がっていた。
もう、ほかのものは何ひとつ、凛子には見えない。聞こえない。夢中でイコール記号の横に数字を書き込んでいく。
509,824×6,619=3,374,525,056
1,902×239,911=456,310,722
68,540×943,563=64,671,808,020
パチパチパチパチ
そろばんよ、思いのままになれ。もっと、もっと……。
「やめえ」
大会役員の人の声が会場全体の空気を震わせる。
誰もがはっと顔を上げる。
すべての競技が終了すると、凛子は労うように自分のそろばんを撫でた。そろばんは凛子の相棒だった。
凛子が荷物をまとめて会場から出たときだった。あ、と思わず凛子の口から呆けた声が漏れた。今まさに、向かって左奥の下りのエスカレーターに乗った人物……薄手の長そで白シャツも、ペンを引っかけられるようになっている実用的なスカートも、凛子には見覚えがあった。凛子は立ち尽くしていた。
先生は今でもそろばんの大会の丸付けを手伝いに来ているのだと、いつか聞いたことがある。凛子はゆるゆると記憶を辿った。「先生、まったく変わらなかったよ。ちょっと痩せたけど」前にそんな風に教えてくれた子がいた。「昔が老けとったんか、今が若いんか、どっちかわからんけどね」楽しそうな響きを含んだ先生の声が今にも聞こえてきそうだと思った。ああ懐かしい。とてつもなく。あれから一体、何年が経っただろう。
凛子は思わず駆け出していた。人混みをかき分け、追いかけ続けてきたその背中に迫った。まぎれもない、先生の背中に。
「先生っ!」
ついに、凛子の指先がわずかに先生に触れた。
先生が振り向く。先生は一瞬、あっけにとられたように固まった。
「まだ私が小学生だったときはっ……」
ありがとう、とは続かなかった。凛子の唇は震えて機能しなくなった。
「凛子……ちゃん……?」
先生ならわかってほしかった。凛子が今、どんな気持ちか。伝えきれないほどのありがとうを。先生のおかげでここまでがんばってこられたということを。
凛子が、どんなにこのときを待ちわびていたか――。
受賞コメント
うれしかったです。
応募したのは、書いてしまったものを出さなきゃいけなかったから。
そろばんが好きなので、そろばんの話を書きたかったです。
作品の創作で工夫したことは伝わるように書くこと。苦労したことは文字数制限でした。また、文章を削っていくことは楽しかったです。
創作活動に興味がある人や、これから始めようとしている人は、書きたいことを書く。が良いと思います。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
佳 作 「だいだらぼっち」 兪 鐔欣 (千葉・渋谷教育学園幕張高等学校 1年生)
それは、衝撃というより悟りに近かった。
『だいだらぼっちが怒ったらしい。』
母さんと夕飯の準備をしていたときに、リビングでテレビを見ていた父さんが叫んだ。画面の中には、揺れる町が映っていた。建物も地面も海も何もかもがいっしょくたになって震えていた。必死に「避難してください。身の安全を確保してください。」と繰り返すアナウンサー。『だいだらぼっち 15年ぶりの怒り』のテロップ。やがて津波警報も出された。母さんと父さんは黙って画面を見つめている。部屋の空気が止まっていた。
―今から1000年ほど前、人類は「自由」と「進歩」の渇望に目覚めた。
「人は神より強し。」
そう言って神を無視し、軽蔑し、傷めた。その神の屍の上に、傲慢と自尊の旗を立て、我らは最強なのだと、砲口した。神の死と引き換えに人類は形式的豊かさを得た。
「人は最強だ。」
だれもがそう信じていた。しばらくして神の怨念はだいだらぼっちに姿を変えた。山々を踏み倒し、河川を壊し、口から雲を吐いては固く絞って大雨を降らせた。
「人は間違っていた。」―
これは私たちが小学校の歴史の授業で、だいだらぼっちについて習ったことだ。
「確実な周期や前兆はわからないが、定期的に暴れる存在で、その行動は、まるで、今まで好き勝手してきた人類を戒めている様である。ただし、写真や動画にその姿が収まったことはなく、目撃例も極めて少数である。」その説明書きは、何もかもが数値化され、科学的に説明されるようになった今の世の中では異様におとぎ話チックだった。
そんなだいだらぼっちが怒ったのは、これから始まる1年に期待を膨らませる元日の夕暮れだった。私は13歳、中学1年生だった。だいだらぼっちの起源や伝説になんて興味はなかった。正直、だいだらぼっちの恐ろしさを語る大人たちは、子供の私たちを脅しているのだと思っていた。
揺れる町、迫る波、燃え盛る炎。その所業をはじめて目の当たりにして何を思ったか。
人の力ではどうしようもない、たった一瞬で、今まで築き上げてきたものが手をすり抜けるのだ、と、ただただ空しくて恐ろしかった。そして、私たちは何のために一生懸命生きるのか、分からなくなった。私はその日から何にも執着しない、つまらない子供になった。別にそうなろうと意識したわけではない。気づけばそうなっていただけだ。
ミーンミンミンミンミーン、ミーンミン
じっとりと汗ばむ日の昼休みだった。
「里実、図書室に本返しに行こう。」
クラスメイトの朋美に誘われた私は、「いいよー。」と快く返事をした。二人で一緒に歩き出す。
「ありがと、早紀がさ、委員会の集まりでいなくて。」
そう言ってから彼女は少し気まずそうに顔を強張らせた。いい意味でも悪い意味でも表に出てしまう子なのだ。わかっている。私は別に彼女ととても仲がいいわけではない。一番の仲良しの早紀ちゃんがいなくて、渋々一人で図書室に行こうとしていた時に、たまたま教室を覗いてみたら、いたのが私だったのだろう。だけど、それを顔に出すくらいなら一人で行けばいいのに、と心のどこかで毒づく私がいる。「あの日」からなのか、私は人と壁を作るようになった。決して口には出さないけど、はっきりと線引きがされている。そのことに気づいた人はその一線を超えないように私と仲良くするのがほとんどだった。自分でもよくわからないが、必要以上に踏み込まれるのが嫌だった。朋美にとっても、私は何か用事に誘うくらいの仲ではあるのだが、休日にわざわざ遊びに出かけるような友達ではないのだろう。
「ねーね、そう言えばさ、入江君がだいだらぼっち見たんだってー。」
図書室まで他愛のない話をしていたら、朋美が突然思い出したように言った。
「へー、どんなだったって?」
声が裏返りそうだった。「あの日」から2年と少し、だいだらぼっちは怒っていない。私は高校生になった。
「なんか、睨んだら逃げた、みたいな?面白いよね。そんなんで逃げるわけないじゃん。」
朋美はけらけらと笑った。私も笑顔で「それなー。」と返す。あははは――
本当はちっとも面白くなかった。うまく笑えていたかもわからない。
ミーンミンミンミンミーン――――
セミはすごいなと思う。羽化して2週間しか時間は残されていないのに、最期まで鳴きとおす。私にはきっとできない。
冷房の効きが悪い教室で宿題をしながら、私はふとそんなことを思った。暑くて暑くて、もう水筒の中身を飲み干してしまった。もう帰ろうか。こんなに暑くては勉強に集中できない。シャープペンシルを筆箱にしまおうとしていたら、「あっちい。」といいながら入ってくる人がいた。入江奏太。だいだらぼっちを睨んで逃げさせたというポンコツ。部活終わりらしく、首や額に大粒の汗が浮かんでいる。
彼は、「こいつ効いてんのか?」と一人で呟きながら、腹立たしそうに冷房の「温度下」ボタンを連打してから、やっと私に気づいたように「よお。」と声をかけてきた。
「どうも。」とだけ返してそそくさと帰り支度を始めようとすると、「なあ、」と彼はまた声をかけてくる。入江君はよく言えばフレンドリーで、悪く言えば馴れ馴れしい人だ。あまり関わりたくはない。何というか、馬が合わない。
「俺さ、だいだらぼっち見たんよ。すごくね?」
「そうなんだ。」
素気なく返しても、彼は気にせず、隣の席に座ってきた。
「なんかさ、『なんだこいつ』って思って睨んだらさ、あいつ消えやがった。」
「へー。」
腹立たしかった。特段仲良くもない私にそんな話をする必要があるのだろうか。嘘の武勇伝は仲間内で語ればいいのに。それでも入江君はやめない。
「にしても、冷や冷やしたぜー。」
私は乱暴に鞄に筆箱を突っ込むと、彼と目も合わせずに言った。
「入江君らしいね。だいだらぼっち、退治できたんだ。すごいじゃん。」
しばらく返事がなかった。懲りたのかと思って、入江君のほうを見ると、刺すような目で私を睨んでいた。
「やっぱり。」
彼は低い声で呟いた。いつものお調子者の声ではない。
「お前さ、馬鹿にしてんだろ。」
「...え?」
「なんで否定しないわけ?『退治できるわけないだろ。』ってさ。」
ミーンミンミンミンミーン―――
もう意味が分からなかった。さっき入江君がボタンを連打したせいか、冷え切った教室にセミの声だけが響いていた。
「お前さ、見下してんだろ、他の人のこと。言い当ててあげようか、お前の心中。」
私が返事をする前に入江君はまくし立てた。
「私は他の人と違ってだいだらぼっちの恐ろしさを実感しています。人間はだいだらぼっちには勝てません。私はそれを知っています。だから、大切なものは作らないで来ました。どうせ、いつか突然死んでしまうかもしれないのなら、作らないほうがいいと思ったんです。友情も愛も捨ててきました。壁を作ってきました。」
はあ、と入江君は大げさに溜息をついてから「そうだろ?」と呆れた顔で聞いてきた。
入江君の言葉が、すとんと音を立てて心に下りた気がした。そうだったのかもしれない。私は、どれほど大事で愛おしいものを作っても、だいだらぼっちが怒ってしまうのなら、それは意味のないものだと思っていた。それを、クラスのお調子者でポンコツの入江君に見透かされていたなんて。
「そうだよ、その通りだよ、だって…いつ壊れるか知らないのに、守る方法もないのに、大事にする意味なんてないじゃないか。」
これで黙ってくれるかと思っていたら、入江君はお腹を抱えて笑い出した。下の階の職員室まで届きそうな豪快な笑い声だった。ひとしきり笑ったあと、入江君は目じりの涙を拭いながら私と向き合った。
「お前、頭良さそうなのにアホだな。いつまで悲劇のヒロインぶってんだ?アハハ!死ぬときは独りでいいっていうのか?どうせ守れねえなら、孤独と寂しさの中で死んでやる的な?おもしれえ。かっこつけすぎだよ。」
その時私は豆鉄砲を食らった鳩の気持ちを知った。そっか、ポンコツなのは私の方なのか。何にもわかっていなかった。情けなくて、胸がつまるように痛かった。自分はこの世界の悲運を知っているのだと、何をしてもだいだらぼっちには逆らえないのだと、勝手に空しくなって自分の殻に閉じこもっていた。もうやめよう。うん、やめよう。抗ってみよう。明日、自分から朋美に話しかけに行こう。
「だいだらぼっちが怖いなら、この世界が憎いなら、睨め。運命とか宿命?っていうのか?そういうのは悟らなくていい。頑張って生きてみようや。」
入江君はそう言ってまた笑った。
「うん。」
私は静かにうなずいて、雲の影がかかる夕暮れの空を思いっきり睨んだ。
受賞コメント
初めての応募でこのような賞をいただき、嬉しく思います、今回の作品は能登半島地震の様子をテレビで見ていた際に急に押し寄せていた感情や今の学校生活の中でたまに感じる哀愁のような気持ちをもとに、一人で一気に書き上げました。世の中に出してみようという勢いで応募しました。それが審査員の方々の目に止まったこと大きな幸いです。ありがとうございました。
学校の国語科研究室の前にポスターが貼ってあって面白そうだと思ったので応募しました。
この作品を思いついたのは夏休みに入ってからすぐでした。「とにかく書いてみよう」と思って1日で書きました。
創作の際、起承転結には気を配りました。セミの「ミーンミーン」の声が場面切り替えの効果になるようにしました。
この作品創作を通して、より小説を書くことに自信が持てるようになった気がします。
創作するにあたっては、自分で書きたいと思ったことを書きました。
技法ももちろん大事だけど、それより自分の書きたいことを自分だけの表現で書けるように文章を磨きましょう。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
佳 作 「星々と漫才」 山田 ひなの (愛知県立時習館高等学校 2年生)
「お客さんはポテトサラダ、お客さんはポテトサラダ、お客さんはポテトサラダ……」
「普通、ジャガイモちゃう⁈ お前、ポテトサラダって、加工しとるやんけ」
高三の夏。杣田と矢沢は文化祭のオーディション会場である体育館のステージの上で漫才をしていた。審査の邪魔にならないように、と先生が巨大扇風機の電源を切り、体育館には蝉時雨と漫才の声がより一層響いた。
***
「杣田ってやり残したことないん?」
春の夕焼けを背にしながら自転車を漕ぐ坂道。杣田の幼馴染の矢沢は突然話を切り出した。
「急に言われても」
杣田は自身の取るに足らない人生を振り返る。小さなころから必死に勉強をした結果、片田舎だけれども地域のトップ校である宮川西高校に矢沢と一緒に進学できて、高二の夏には――今はもう別れたが――人生で初めて彼女ができ、いい友人たちにも恵まれ、生徒会の会計として働き、高三になってからは何不自由なく受験勉強に励む日々。
しかし、杣田には一つだけ心残りがあった。
「漫才かな」
杣田は昔から漫才が好きだった。エンタの神様が放送されるときはテレビの前に引っ付き、休日に暇があれば、録画したM―1グランプリをぶっ通しで見続けるような子供だった。そしていつしか漫才への熱は自分が漫才をする側になるという夢へと変わった。けれども、感染症の流行によって人前で披露する機会がことごとく失われ、あっという間に高三になってしまった。
一回ぐらい全校生徒の前でやってみたかったんだけどな、と杣田は生暖かい風に混じって溶けてしまいそうな声で本音を漏らす。
「じゃあやればいいじゃん」
杣田はそんな無責任なこと言うなよと言わんばかりの顔をした。今からコンビを結成するとしても相方は、漫才のネタは、受験勉強はどうするのか、と杣田の頭の中には瞬時に漫才をやれない逃げ道が浮かんできた。
「どうせお前のことだからやるの躊躇してるんだろ? 漫才やったら人生が急激に変わるわけじゃない。でも、やらなかったらお前の心の中には一生後悔が残るぞ」
さすが幼馴染、俺のことわかっているな、と杣田は妙に冷静になりながらも呆れた声で矢沢に言い返す。
「だとしてもよ、相方はどうすんの。根本的なところからつまずいてるんだよ」
矢沢のかすれた笑い声が聞こえた。杣田は笑うところなかっただろ、と思いながらやれない言い訳を盾にして新たな反論をしようとした瞬間――
「杣田忘れたのか? 俺も漫才好きなんだけどな」
そう言われて、杣田の脳内には小学校のころからの矢沢との何気ない日常がフィルム映画のように流れた。
次の瞬間、杣田の前を走る矢沢が急に自転車を止めて降りた。つられて杣田も自転車から降りる。
「杣田、俺と組もう」
夕焼けの柔らかい光が二人を包む。杣田はプロポーズかよ、とはにかみながらも真昼のような声で返事をした。
***
それからは忙しい毎日だった。
登下校、休み時間、お風呂やご飯の時間も絶えずネタを考えていた。寝かけていたときにふとネタが思い浮かぶ時もあった。杣田はその度にスマホのメモに打ち込んで、気が付けばネタの数は百を優に超えていた。昼食の時には矢沢のクラスに赴き、先生にばれないようにこっそりスマホを出してお互いのネタを見て打ち合わせをしたり、漫才の動画を見て身振り手振りを学んだりしていた。
梅雨だというのに紫陽花を枯らしてしまうほどの日差しが降り注いでいたある日、杣田は窓辺の席でいつも通り矢沢と漫才の話をしていたところ、そういえば、と矢沢は急に話を中断して、コンビ名の話を切り出した。
「俺、そういうのセンスないから杣田決めていいよ」
俺の一存かよ、と思いながらも杣田はオムライスを口いっぱいに頬張り、口をもごもごさせながらコンビ名について考える。その時、突然、新歓の日の記憶がよみがえってきた。
***
生徒会最後の大仕事である新入生歓迎会自体は無事に終わった。大変だったけど楽しかったな、と杣田は電車に揺られながら振り返る。しかし、沿線で火事が起きた影響で、電車は杣田の最寄り駅の一つ前で止まってしまった。親を呼ぼうと思ったが、たまには歩いて帰るのも悪くないな、とも思い、最終的に二キロメートルの道のりを徒歩で帰ることにした。
しばらく歩いていると、杣田が小さい頃よく遊んでいた公園にたどり着いた。そのまますぐに去ろうとしたが、昼間とは真逆の公園の様子がやけに魅力的に見えて、杣田はどうしようもなく夜の公園で遊んでみたくなってしまった。誰かに見られたら間違いなく不審者って思われるだろうな、と思いながらもブランコを漕いでみる。そして、ブランコの角度が四十五度を超えたあたりで杣田は気が付いた。
「星だ」
杣田は風に吹かれて桜の花びらと舞い散ってしまいそうな声でつぶやく。杣田の視界一面にはこぼれそうなほど星たちが輝いていた。
***
「星色オムライスなんてどう? 特に意味はないけど」
矢沢はええやん、ええやんと言いながらサンドウィッチを食べていた。
「杣田のおかげですぐに決まったことだし、令和ロマンのM―1決勝ネタ見返すか」
ネタの方針もある程度は決まった、コンビ名もぱっと思い付きのやつになった、今のところは順調だな、と安堵した杣田はオムライスの最後の一口を頬張った。
けれどもやはり杣田と矢沢は高校三年生。杣田は放課後に学校の物理と化学の補講、塾の難関国公立対策の英語、数学の授業があり、思うように練習ができなかった。それでも二人はお互いの補講が被らない日の放課後に中庭のベンチで脳に叩き込むように練習を繰り返し、休みの日には夜更かしをしてLINE上で漫才のネタの再構成について語り合った。
「うーん、これじゃだめだな」
もはや日常となった矢沢のクラスでの昼食時、購買のタコライスを食べていた矢沢が急に言い出す。杣田たちは議論の末、ネタの一部を変更することになった。それはオーディション一週間前のことだった。
***
オーディション当日。一学期終業式は熱中症対策として放送で行われている。同じクラスの人も担任も机に突っ伏して寝ている中、杣田は、頼む、ウケろ!! と本当はずっと声に出ているのではないかと思えるほどの熱量で必死に祈っていた。もちろん、校長先生の話も生徒指導の先生の話もみんな上の空だ。
普段なら長く感じていた終業式も終わり、時刻は十二時半。オーディション開始まで残り一時間となった。矢沢と一緒に昼食をとり、最後の通し練習を体育館の舞台袖で行う。あと三十分、あと十五分、校長先生の話よりも時がずっと早く進む。オーディション開始まで残り五分、杣田たちは先生にピンマイクをつけてもらった。もちろん緊張はしている、しかしそれ以上に心の奥底からのわくわくで杣田は満たされていた。やれることはやりつくした。あとは全力で審査員を楽しませるだけ、杣田は心の中で自分自身に言い聞かせる。
「それでは一組目、星色オムライスの皆さん、お願いします」
***
「杣田、やり残したことある?」
眼前に広がる夏の星空を見ながら自転車を漕ぐ坂道。星は一つ一つ掬い上げられそうなほど白く輝いていた。
「全くないね」
杣田はソーダのように澄んだ声で答える。オーディションは不合格だった。けれども杣田の心はこの上ない達成感で満たされていた。
まだ家に帰りたくないから、と理由を付けて二人は杣田の家の近くの公園に寄り、自販機で缶コーラを買う。
「矢沢いなかったら俺、多分ずっと後悔してた。ほんとにありがとう」
ベンチに座り、杣田は矢沢の目を見つめて言う。少しして恥ずかしくなってしまった杣田は、缶コーラを一気に飲み干した。今日という日の余韻に浸るような沈黙が二人の間を流れる。しばらくして杣田の唇はゆっくりと言葉を紡ぎ出した。
「せっかくだし、夏休みにさ、オーキャンも兼ねて東京に遊びに行かん? 徒歩で」
「え、徒歩⁈」
瞬時のボケとツッコミに顔を見合わせて笑う二人を星はスポットライトのように照らしていた。
受賞コメント
今回、この作品を佳作に選んでいただいたことをとても光栄に思います。私は文学部に所属していますが、普段は短歌や俳句などの韻文を中心に創作活動を行っているので、散文を書くのはこれが初めてでした。顧問から受賞の連絡を聞いた時は驚きでいっぱいでした。
夏休みの課題として小論文や読書感想文などが設定されていて、このコンクールはその中の一つでした。
一学期終業式の日、私は文化祭のオーディションの審査をしていました。作品中の杣田と矢沢のモデルとなったおふたりの漫才を見て、私は強く感動し、このことを文学として残したいと思ったので、オーディション翌日に許可取りをし、私の夏休みをかけてこの小説を作り上げました。
杣田のモデルになった人に、漫才をやろうと思ったきっかけ、ネタのこと、コンビ名の命名秘話など様々なことを質問して、この小説作りの参考にしました。また、公園のシーンは実際に私が塾帰りに歩いて公園に行き、生きた言葉で表現するようにしました。この場面の情景描写が一番のこだわりポイントです。
俳句や短歌とは違い、小説はたくさんの文字数で自分の思いを表現できるので、登場人物の気持ちを丁寧に描く力が身につきました。また小説を書く楽しさがわかったので、今後も小説を書いていきたいです。
自分の世界の見方を表現するツールが文学だと思っています。他者の作品から得られる新たな価値観は自分自身の成長につながっています。ぜひ、自分の好きなものを好きなように表現する楽しさを味わってほしいです。
外出した時に色々な景色を見ますが、後々そこから創作のきっかけを得ることがあるので、心が引かれた景色と写真を撮るようにしています。
一朝一夕で成長するものではありません。最初は下手でも普段の努力で少しずつ成長していきます。すぐに結果が得られなくても諦めないでください。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
佳 作 「100ひく7」 吉田 翔梧(神奈川・慶應義塾高等学校3年生)
「100から7を引けますか?」
「きゅうじゅう…さん」
「合ってますよ。ではそこから更に7を引けますか?」
「はちじゅう……」
「ちょっと難しいかな?じゃあ知っている野菜の名前を出来るだけ多く教えてください。」…
見慣れない景色の中、意味不明なやり取りが聞こえてきて篤は目を覚ました。(後に調べたところ、認知症かどうかを判断するためのテストだったらしい。)真っ白なベッドの周りをぐるりと囲っている薄ピンクのカーテン。寝転がったままでも見やすい位置にある小さなテレビ。
ああ、そうだ。手術したんだ。
一般的にサッカーは冬に開催される全国高校サッカー選手権が最も盛り上がる。公立高校に通っている学生は受験が控えているため3年生は夏には引退してしまうけれど、大学付属の高校に通っている学生は選手権まで部に残ることができる。篤は3年生になってもBチームだったけれど、時々Aチームの練習に参加できていた。だから選手権ではベンチ入りできる、そう思っていた。そうなるはずだった。
「あっっづ~~い。」
夏もまだ序盤、7月上旬とは思えないほど強烈な日差しがじりじりと肌を灼く中、楓は家族に引っ張られて郊外にある運動公園に来ていた。なんでもここは野球からサッカー、バスケまで様々なスポーツのコートがそろっているらしい。今日は10年来の幼なじみである篤がサッカーの試合をするということで、共働きで多忙な篤の両親の代わりに家族で応援しに来たという次第だ。特に引退がかかってるとかいう大事な試合ではないらしいけど。じゃあべつに私連れてこられなくてもよかったんじゃない?
「篤がサッカーをするとこなんて後で係の人が撮ってるビデオもらって見ればいいじゃん。あんたあの係の1年の友達なんでしょ?」
楓の不満は弟に向いた。
「こっちに不満ぶつけてくんなよ。てか、動画で見ればいいとかそーゆーことじゃないんだよ。」
と、スポーツ観戦が好きな弟。
「じゃあどーゆーことよ。」
「やっぱ生で見ると画面越しじゃ伝わらない何かがさ、こう、ぐわって来るんだよね。わかんないかなぁ。」
「…何かってなんだ、何かって。」
「どっちにしろもう来ちゃってるんだから文句ばかり言ってないでちゃんと応援しなさいよ。あんた引退しちゃってるんだからどうせ暇なんだし。」
とあきれたように諭してきた母はサーティワンを買いに行くと嘘をついてまで楓を連れ出してきた張本人である。楓が帰りには絶対にダブルサイズのアイスを買ってもらおうと決意を固めているのは言うまでもない。楓が食い意地の垣間見える決心をしている間に選手がピッチに入場してきた。
「来た!」
「やっぱユニフォーム姿はかっこいいわねぇ。」
さすがに母のようにあけすけに褒められるほど素直にはなれないが、篤がサッカーをする姿は普段の3割増しでかっこよく見えるのは分かる。いつもはふざけてばっかりのくせに。
コートサイドを決めるコイントスも終わり、いよいよ試合が始まった。
篤とのいわゆる幼なじみとしての関係が始まったのは小学校3年生の時からだ。そのころ既にサッカーに憑りつかれていた篤は、ことあるごとに楓にその熱を共有しようとしてきた。そのおかげで一応そこそこサッカーを楽しんで見られるくらいにはなっている。今ではもう自覚している天邪鬼な性格は幼い頃から健在だったようで、素直にサッカーにのめりこむことこそしなかったけれど。まあワールドカップなどおおきなイベントで盛り上がれるのは得だろうからその点に関しては感謝してやらんでもない。本人には口が裂けても言わないけど。
「…そのお礼に少しくらい応援してやるか。」
ようやく楓が本腰をいれて見始めた試合は開始直後にも関わらず白熱した展開をしていた。プレーが繰り広げられるフィールドでは、ボールが選手たちの間を縫って動き、まるで小さな命が跳ね回っているようだ。サイドラインの近くにボールが行くと、選手たちは必死に駆け寄り、体をぶつけあう。
うわー。痛そう。
滴る汗を気にも留めず走り回ってパスを受け、空いているスペースに絶妙なパスを出したと思ったらまた走り出す。相手も負けじとくらいついていき、体を果敢にぶつける。かと思ったらボールとはまったくの逆サイドにいる選手でさえよりいい位置でパスを呼ぼうと相手との駆け引きを続けて前後左右に動き回っている。
ボールのないところにも視野を広げてるとアピールすることで玄人感を演出できる。こんな高等テクニックはもちろん篤から伝授されたものだ。普段テレビで見るような日本代表の試合と比べればさすがにテクニックやスピード感は劣る。しかしその1試合、1本のパス、1回のディフェンスに懸ける必死さや、その一瞬一瞬の情熱はダイレクトに伝わってくる。この体験は画面越しだけでなく、プロのようにスタンドとピッチに距離がある状態でもできないだろう。たしかに、
「生で試合見るのおもしろいかも。」
「でしょ?」
弟と顔を見合わせてクスクス笑った。その一瞬に「事件」は起こった。
あれほど熱のこもっていたフィールドが静寂に包まれ、何事かと見ると試合は一時中断し、選手が1人足を抱えて倒れこんでいた。
「篤くんが…」
どうやら起き上がれなくなっているのは篤らしい。サッカーにおいてファールをもらおうと少し大げさなリアクション、いわゆるシミュレーションをするのはままあることだ。だが、母の不安そうな顔から察するにかなり激しい接触をしたらしい。
「…ほら、篤怪我なんてぜんぜんしたことないし、大丈夫じゃない?」
重い空気をどうにか変えようと楽観的なことを言ってみるが、空元気であることが分かりやすすぎたのか母の顔は暗さを増すばかりだ。そんな顔をされるとこっちまでどんどん不安になってくる。大丈夫だよね、篤?
大丈夫に決まってると、とりあえず周りを安心させたいのに、自分の口から呻き声しか出てこないのがもどかしい。
いつもと少し違うことは試合開始直後から気づいていた。
一週間前から睡眠時間や食事にはいつもの何倍も気を遣ったし、試合直前のウォーミングアップも入念にして試合に対する気持ちもしっかりと作り上げた。幼なじみの楓が応援に来てくれたことに気付いた時は多少驚いたけれど、プレーに影響が出る要因にはならない。つまり、準備は完璧だった。
篤は試合の中で自分が最初にボールを触る瞬間を一番丁寧にこなす。ファーストプレーがその後の自分のプレーすべてに繋がると考えているからだ。今日のファーストプレーは悪くはなかった。悪くはなかったけどなんかふわふわしていた。大丈夫。落ち着け。と思っていたことが既に焦っていた証拠だ、と後から思う。ふわふわしたまま試合が進み、前半も中盤に差し掛かってきたころ、明らかに度を超えた強さでぶつかられた。普段なら相手の力をいなすように倒れ、怪我なんかしなかったと思う。けれど今日はなぜか倒れまいと踏ん張ろうとしてしまった。
なんとか立ち上がったが、今までで経験したことのない感覚がした。心配性の母や楓に言ったことはないが、痣を作ったり、軽い捻挫をすることはしょっちゅうある。だが今回はその比ではないと直感でわかった。右足に全く力が入らない。サッカー人生で初めての負傷退場をした。
「前十字靭帯損傷ですねぇ。手術して、競技復帰には8か月くらいかかっちゃうかなぁ。」
聞こえてはいる。だけどその言葉の意味が脳に届くまでひどく時間がかかったような気がした。
話し方はおっとりだけど医者としては敏腕だという評判の先生はとくだん大ごとでもなさそうに言った。同じような患者を何人も診てきているのだろう。いやいや、大ごとだよ。手術?8か月?小2から続けてきたサッカー人生の終わり際も自分で決められないのかよ。
あまり怒りが持続するタイプでもないので、家に帰って夜になると少し冷静になっていた。もうサッカーに本気で打ち込むことができないのに涙もでない自分に「あぁ、その程度だったんだ。」と思えるほどに。
「100から7を引けますか?」…
今になってもつい昨日のように思い出せる高校生だった頃の記憶。そこからおよそ60年が経った今、楓は認知症の診断テストを受けている。庭の池に分厚い氷が張る季節のことである。結果は、軽度の認知症だった。今は少し物忘れが多い程度だが、やがて篤のことも忘れてしまうだろう。出会ったのは9歳だからそこから約70年。その頃は永遠に思えたほど長い時間を共に過ごした人が、自分のことを忘れてしまうのはとても恐ろしい。けれど、もう逃げない。辛いことから逃げても辛いままだと楓が教えてくれたから。
怪我をした後の篤はまるで魂が抜かれたようだった。言われるがままに手術を受け、言われるがままにリハビリをした。歩けるようになってからも部活は休みがちになった。なんのやる気もでないし、あれだけ好きだったサッカーのことは考えたくもない。一日中ぼーっと過ごす日々が続いた。
「サッカーができなくなって辛いのはわかる。でも、だからって全部から目を逸らしてどうするの。」「「痛みを伴わない教訓には意義がない。人は何かの犠牲なしには、何も得ることができないのだから」って荒山先生言ってたじゃん!こっからは前進できるってことだよ。」「疲れたなら休んでもいい。でも、もう一度立ち上がるって約束して。」
楓は時に厳しく、時におどけて、また、優しく声をかけ続けてくれた。今度は篤の番だ。自分には楓の病気を治す力もない。昔楓がしてくれたみたいに前を向かせることができるかもわからない。けれど、そばにいることはできる。
篤は楓の隣に座り、そっと手を握った。2人で庭の池をながめていると、楓がゆっくりと口を開いた。
「篤さん見てごらん。きれいだねえ。」
池の氷の表面には無数のひび割れができ、夕焼けの光がその隙間から染み込むように差し込んでいる。氷は薄く透明になりつつあり、所々で水が姿を現し、波紋を広げていた。
受賞コメント
まさか受賞するとは思っていなかったので驚きました。
怪我で手術をしなければいけなくなり、サッカーができなくなってしまったのでその思いを込めて書きました。
創作にあたっては、入院中に創作したので、思い出して書くのは精神的に辛かったです。
今回の創作を通して、自分が小説を書けることがわかったので、これからもそれに関係することをやりたいと思えるようになりました。
元から小説はよく読んでいるので、好きな作家さんの表現の方法を真似しました。
とりあえず書いてみると書けるかもしれないです。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
佳 作 「アクアリウムという星の下で眠る」 香川 陽菜(横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校3年生)
天井で揺らめく海。
プロジェクションマッピングとかいう無粋なものではなくて、きっとここは海底神殿だった。海の中に沈没したアクアリウム。迷い人であり、旅人でもある私は、水の中でも呼吸ができるという不思議な飴を一つ舐めて、好奇心を身体に詰め込んで海に飛び込んだ。
あるいは、海と空が逆転してしまった世界だった。私たちは皆羽を持っていて、空に溺れないように生きていた。触れられない海からは時折溢れるように雨が降り注いだ。
もしくは、水族館という水の惑星だった。私はただの女子高校生で、機械で光が投影されたコンクリートに閉じ込められている。
手には「入場券 高校生」と書かれたチケット。それと想像力に侵された脳味噌一つさえ持っていれば、私はどこにだって行けた。
水族館の神は太陽をどこかに隠してしまったから、ここは何時でも夜に包まれていた。漂う寂寞の匂いは私の体内の水分と混ざって、涙になった。子供だから眠たくなってしまうのだと、誤魔化すように浮かんだ涙を拭う。目尻には指先の冷たさが残った。
ここには地球を小さく、四角くしたいくつかの世界が展示されている。すべてが海に沈んでしまった世界。蒼々とした水草にほんのりと青みがかったように見える水が、発光ダイオードで照らされている。丁寧に模作された世界は、整えられすぎていて、矛盾を抱えたこの世界とは似ても似つかなかった。これが神々の遊びなら、私は天使見習いで、哀れな魚たちは人間だった。私は出来損ないだから、人間に同情してはよく神に叱られて、翼から羽根を一つぷちりと抜かれてしまうのだ。
けれど、その世界たちは同時に液晶の向こう側にあった。水で歪んで、光を放って、触れた冷たさは、水のように柔らかくはなかった。硝子越しに彼らの目に映った私は、気色の悪い色をした化け物なのだろう。
世界の上には透明な管があり、そこから流し込まれる泡沫という透明な雨を、魚たちは飲み込んで生きていた。人工物であることを主張する透明な管に腹を立てるけれど、結局はそれも汚い同情でしかなかった。
魚たちは色鮮やかで一等柔らかかった。鰭で水を僅かに揺らし、光に透けさせるように翻す。その様子は花に譬えてしまえるほどで、けれどそれは、散った花弁が何時までも風に攫われて舞い続けているということだった。それほど哀れで悲しいことなんてないのに。それなら、彼らは一体何処に還ればいいんだろうか。
どこにも行けないのは、空にも消えられずに光を遮るだけのものに成り下がってしまうのは、一体誰だったか。
向こう側が透けて見える魚は沢山の水を抱えて、全ての水の記憶を抱えていた。その叡智は閉塞感を諦念に変えて、どうにか彼らを生き永らえさせていた。私の臓器もすべて透明になったら、この世界という水槽で泳げるようになるだろうか。
歩みを進めた先にいた海月は海を一身に湛えて、ドレスの裾を揺らしていた。純真を纏って揺れるその姿は人間すべてを魅了し、そしてただの芸術品と化した。半透明が重なり合い、複雑怪奇な模様を生み出すその様は現代アートにも勝る生命の神秘だった。
ふい、と目線を逸らした先にも海月はいた。くだらない文字列と共に、ホルマリン漬けのようにも見える小さな水槽に閉じ込められた海月は先のものよりも幾分か小さかった。それは、忙しなく体を揺らしていて、その呼吸の速さに、道端に寝る野良猫の心臓が余りにも生き急いでいることを思い出した。
「心臓が一生に鼓動する回数はどの生き物も同じである」
というのは何処で聞いたんだろうか。それならどうか君の心臓が止まってほしいと、矛盾したことを思ったのは何時だろうか。ただ、この世界で、ごく普通の感情で大切だと思える人がいて、正しく大切に思えることが、唯一の救いだった。心臓の鼓動を分けたいと思えたことに、酷く歓喜した。
白色光を反射して浮かび上がる海月は月のようだった。胃腔は月の海で、満ち欠けはなく、ただこの世界にある大量の月が一つ一つ死んでいく。そして、月が一つもなくなったとき、この世界は終わりを告げるのだ。なんて、もしそうなら私は今すぐにでも水槽を割ってしまうだろう。
薄い海月の水槽は上から覗けるようになっていた。坂を登って、私は目を瞑って水槽に飛び込んだ。
目を開けると、そこは空だった。私は純白のワンピースを纏った白髪の少女と手を繋いでいた。夜と朝の狭間を落ちる私はただ見惚れていた。繋いだ手に少し力を入れる。
「でもやっぱり少しだけ怖いよ」
それを聞いた少女は僅かに微笑んだ。
薄い海月の水槽は上から覗けるようになっていた。私は坂を登らずに水槽を通り過ぎた。
海月の惑星を抜けると、大きな水槽があった。その前にはいくつかの椅子が置かれている。ここはどうやら二階の様で、水槽は下まで続いていた。置いてある椅子に座り、足を組み、水槽を見下ろす想像上の人間は突き落としておいた。そこに椅子を配置するのは、間違いなく人間の傲慢だった。
水槽の中心には水泡が蜘蛛の糸のように垂らされている。正面から見ればそれは、計算された動きで美しさを醸し出すのだろう。けれど、彼らにとっては蜘蛛の糸にすらなり得ないものでしかない。そう思うと、途端にそれが酸素と窒素の混合物にしか見えなくなった。
しばらく水槽を眺めていた私を、影で喰らうように大きな魚が通った。もし、私が水槽で揺蕩うなら、彼はもう一度喰らってくれるだろうか。肉も、骨も、血液の一滴ですら残さずに喰らい尽くしてくれるなら、漸く私は海に還れる気がした。
目の前を泳いでいた魚がはくりと口を動かす。もし私が読唇術を使えたなら、彼らのエイチイーエルピーも受け取れるかもしれない。
どれだけ見つめても、私は読唇術が使えないから、硝子に口付けを一つ落とした。彼らから目を逸らして、階段を降りる。
歩いていけば、小さな水槽を赤い魚が青に染まらずに泳いでいた。青い反射光に囲まれた赤は、凛とした強さを持ってそこに佇んでいた。
燃えていた。のかもしれない。手で掬いあげてみれば、冷たさの先に僅かな温度を感じた。ぼうぼうと手の上で燃え上がり、私の瞳の色すら侵食していく。闇夜の迷子を導くように光り続けたあと、拍動をゆっくりとやめるように炎は小さくなっていった。僅かな温度さえ感じられなくなったとき、私の掌には赤い魚の死骸が横たわっていた。
それが一番の美しさで、美しさの全てだった。
人間の傲慢で作られたこの星はそれでも美しかった。
私たちの世界はこんな縛られた小さな世界ではなくて、果てしなく広がっていた。けれど、私はこの美しい世界の下で死にたかった。憐れみも、悲しみも、閉塞感も、全能感も、全部持って。自由を愛して、不自由に溺れる。その苦しさの中で垣間見た光に懐かしさを見出して、静寂を抱きしめてただ眠る。そうやって、一つの命を終わらせたかった。
私は一人、アクアリウムという星の下で眠る。
受賞コメント
この度は佳作にご選出いただき誠にありがとうございます。受賞するとは夢にも思いませんでしたので、驚愕いたしました。けれど、自分の作品がこうして認められたことは非常に嬉しく、かけがえのない経験でした。このような機会を頂けたことは私だけの力ではございません。この場を借りて、関わってくださった全ての方に感謝申し上げます。
私の中にある「よい小説」を自分が書けるようになるためには独りよがりでは良くない、そう思ったのがきっかけでした。独りよがりにならないためには、自分の書いた小説が他人にどのような評価を受けるのか、ということを知らなければならない。そのような考えから様々なコンテストを探していたところ、このコンテストを見つけました。様々な方向性の作品を受け入れる姿勢に感銘を受け、作品を応募したいと思いました。
この小説は、水族館に苦手意識のあった私が久方ぶりに水族館に行った際に感銘を受けたことをきっかけに誕生しました。水族館の素晴らしさを文章で表現するために、ユーモアのあるフィルターを通して水族館を見る、ということを試みました。この小説を通して私が感じた水族館の良さが皆さんにも伝わると嬉しいです。
創作にあたっては、何よりも言葉選びに気をつけました。水族館特有の空気感を表現できるよう言葉を慎重に選びながら執筆しましたので、それが一番の苦労でもありました。雰囲気を崩してしまうと読者が小説に没入することの妨げになってしまいます。そのため、どのような言葉がこの場において適当か、一語一語考え抜きました。楽しかったこともまた言葉選びであり、秀逸だと思える表現が見つかったときの喜びはひとしおでした。また、自分のフィルターを通した水族館が出来上がっていくこともまた執筆の際の楽しみでした。
今回の創作を通して、文章に最適な言葉を選ぶ力を向上させることができたのではないかと感じています。また、自分の感じたことにフォーカスした話でしたので、自分の内面について考えること、そして表現することの練習になったのではないかと思います。
創作活動の魅力は、自分の世界を表現することができる、そして形にならないものに形を持たせることができるところです。創作活動とは曖昧なものを世界に留めておける一つの方法だと思っています。
とりあえず興味があるのなら創作活動をしてみてください。そして一つの作品を完成させてみてください。その経験がいったい自分がどこへ向かいたいのかを明確にしてくれると思います。そして一人じゃどうしようもないときが絶対に来るので、頼れる人を作りましょう。褒めてくれる人、アドバイスをくれる人、何でもいいです。誰かの視点を借りることもまた創作活動において重要なことだと思います。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】