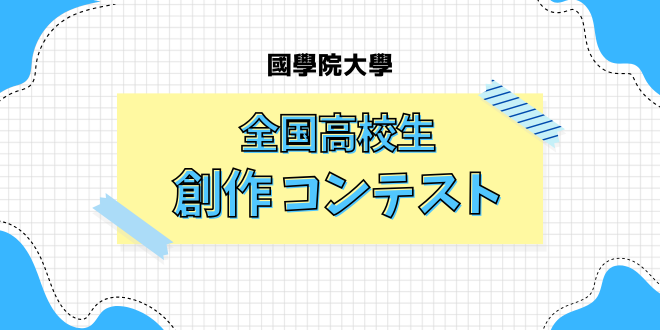【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
優秀賞 「正しい線の引き方」 佐々木 由宇 (東京都立南多摩中等教育学校 1年生)
「由利ちゃん、左利きなのに絵下手だねー」
関係ない、と思いながら由利は画用紙に線を引いていく。それを言うなら恵麻だって、右利きのくせに論理的思考ができていない、と由利は思う。
「私もう描き終わっちゃったよ。先生どこだろ」
恵麻の画用紙には、ダイナミックな動きをしている虎が描かれている。二時間連続で美術の時間があるのだが、一時間目のうちに描き終わってしまったために、由利にちょっかいをかけているのだ。
美術の授業は他の科目に比べて楽なため、生徒からの人気も高い。しかし、由利は嫌いだった。
『創作』という感性を必要とされる分野で成績をつけるなんて馬鹿げている。美術史なんて、将来の自分にはかかわりのないものに脳のスペックを割り当てなければならないことも、苦痛で仕方なかった。
心の中で恵麻に舌打ちをしながら、線を重ねる。どれだけやっても思い通りにならない。正しい線が引けない。思わず力んでしまい、鉛筆の芯が折れる。
「あ、先生! できましたー」
準備室から出てきた尾形先生に恵麻が駆け寄る。「相変わらずうまいな」と褒められ、恵麻の照れ笑いが教室に響く。
先生は何もわかっていない。恵麻の絵が上手いことなんて、みんな知ってるんです。恵麻の笑い声なんて、さんざん聞いてもう飽きてるんです。あたしが聞きたいのは。
画用紙と向き合うのがつらくなり、顔を上げる。黒板には「動きやしぐさを観察する―動物を描く―」と書かれている。尾形先生の字は相変わらず汚い。だけど、優しい。誰にも説明できない感情が、由利の心の中で渦巻いていた。
「先生、ちょっとアドバイスもらえますか」
足音が近づく。空気が揺れている。
「おう、どうした」
正しい線を引ける人の手が、私の視界に入る。
放課後の教室では、数人の女子が集まって話をしていた。帰るタイミングを逃してしまった由利は、退屈という感情を表に出さないように顔に力を入れて話を聞いていた。
「私はー、……井上くん」「えー‼」「なんか、男らしいっていうか、首筋がかっこいいんだよね」「うわ、性癖だー!」「いやでも全然お似合いだと思う」「ね。二人とも運動できるし」「絶対長続きすると思うよ」「えーホント?」「マジ」お互いが自分の好みを発表し合い、それに反応していく。恋バナを通して、話し手を格付けしているみたいだ、と由利は思う。
「でもさ、」
先ほど好きな男子を発表した女子が口を開く。
「井上君、ENFJらしいんだよね。私ISTPだから。これってやっぱ良くないかな」
えー、と周りが声を上げる。「MBTIに引き裂かれる―」「大丈夫! 相性良くて首筋かっこいい男ほかにもいるから!」
くだらない。あまりのバカバカしさに、由利は頭がくらくらした。話に夢中になっていた彼女たちから逃げ出すのは思ったより簡単で、もっと早くに出ればよかったと後悔した。
階段を下りて、靴箱へと向かう。廊下には吹奏楽部の演奏や、卓球部が球を打つ音が充満していた。
つまずく。突然、尾形先生の姿が見えたから。体が小さくなっていくような感覚になる。
「ああ、どうも」
先生が由利の横を通り過ぎようとする。風が起こる。思わず、体を翻す。
「あの!」
天井の蛍光灯の点滅が、やけに気になりだす。
「あの、絵描いてもいいですか。その、ここで」
先生が出てきたばかりの美術室を指差す。
「次の授業でも描くよ?」
首を思いっきり横に振る。「ちょっと、話したいことがあるんです」
ほとんど何も描かれていない画用紙を机に置く。椅子を引いて腰を下ろす。由利の一つ一つの動作がぎこちなかった。
「分からないんです」
先生が隣に座る。手が見える。
「なにが?」
「……なにを描けばいいか、分からないんです」
「なんでもいいんだよ。自分の好きな動物とか。あ、篠原さんは虎でしょ、ぴったりだよねえ」
そうだなあ、と先生が上を仰ぐ。
「飼ってる、とか飼ってたペットはいない?」
「きんぎょ、が、います」
「いいじゃん。みんな哺乳類ばっかり描くからさ。じゃあ、描いてみよう」
先生が美術用の鉛筆を渡してくれる。だが、由利の手は動かない。
「線が、引けません」
「なるほどね」先生も鉛筆を持ち、裏紙に絵を描き始める。
「まずはこう、下書きから描く。最初は薄い色ね。輪郭とかざっくりと」
やっぱり、先生の線は正しい。まるで魔法みたいだと、由利は思う。そしてそれが同時に、怖くもある。
鉛筆の先端で、慎重に線を引いていく。できた線は細く、まるで生まれたばかりの小鹿のように弱々しい。だけど先生は褒めてくれる。授業時間でも何でもないのに。先生を独り占めしているのだという事実が、由利の手のスピードを上げていく。
「うん、良いんじゃないかな」先生が立ち上がった。「じゃあこれの続きは授業ね」
まだ紙には下書きしか描かれていない。細かい描き込みも色塗りも、なにもされていない。
「まだ、まだあります」
ごめんなさい、と小さく頭を下げる。
「どうしたの?」
先生の声は優しい。
先生しか知らないこと。正しい線を引ける人だから知っていること。
「先生は、線を引くことが怖くないんですか」
先生の頭の上に、クエスチョンマークが浮かんでいた。
「あたし、線を引くことがずっと怖いんです。消しても跡が残るし、消えない時もあります。なのにどうして、そんなまっすぐに引けるんですか」
違う。ずれている。やっぱりあたしは線をうまく引けない。
「みんな線を引きながら会話してます。それで、線の左と右で分けるんです。左利きは芸術が得意で右利きは論理的思考が得意とか、占いで相性を調べたりとか。先生もそうです。恵麻の絵が上手いのを誉めて、ほかの人のを誉めないのも、恵麻が虎を描くのをぴったりだと言ったのも」
合っているのだろうか。自分のほうが、先生との間に線を引いているのではないか。
「そんなに悪いことなのかな。線を引くこと」
先生がまっすぐ由利のことを見ていた。
「美術の線は何本もの線が集まって一つの作品になる。会話で引かれる線も、同じじゃないかな」
口調は優しい。だが由利は、ナイフのような鋭さを感じた。
「人間が言葉を使い始めた時から、きっとすでに何かを二分してたよ。男性はこうとか、女性はどうとか。分かりやすくて、はっきりした線を引いてた」
でもね、と先生が続ける。
「ほんとは多分、下書きが必要なんだ。そんな線を引く前に」
由利の目には、先生は自問自答しているように見えた。
それくらい、先生も悩んでる。
「もっと、本質的なこと。俺らはただ個々の生物で、やがて死んでくそんなかで区切ってるんだってこと」
先生が由利のほうを向く。
「ごめん、うまくまとめられなかった」
大きく首を振る。
「先生は下書き、描けてますか」
先生の口元が少し緩む。
「どうだろ。俺だって勢いに任せて線を引いちゃうときもある。でも……だからこそ、美術をするのかもしれない。『創作』は一人で向き合うものだから」
先生が俯きながら頭を描く。
「だからもし言葉の線が恐ろしくなったら、鉛筆を持って、何本でも描きなおしな」
由利は大きく頷いた。
「あれ、先生じゃん!」
恵麻の声が美術室に入る。「由利ちゃんもいる、一緒に帰ろー」と由利の手を取った。
この子は、どうして絵を描いてきたのだろう。きっかけは何だったのだろう。
頭の中で何回も下書きを描いて、正しい線になるかどうか確認する。
「じゃあ、さようなら」
先生の顔がいつもよりはっきり見えた。
「ありがとうございました」
深々とお礼し、二人は教室を後にする。
「なに話してたの?」
なんでもない、と答えながら、少し笑顔になる。今度、恵麻に絵の描き方を教えてもらおうと思う。
左利きでも右利きでも、あたしたちは先生のことが大好きだ。
受賞コメント
嬉しいです!ありがとうございます!
小説をどこかに送りたかったことと、審査員が知っている人だったため応募しましした。賞金があるのも魅力です。
締め切りギリギリに書き終わって、送れないかも~と思っていましたが、無事送れました。
今回の創作にあたり、はじめて三人称で書きました。あんまり上手くいってないような気がします。自分では作品を通しての成長はあんまり分かりません。
なんでもいいよ!書けたら送ってみて!っていう言葉を思い出すと書き続けられます。
【目次(TOP)】【最優秀賞】【優秀賞】【佳作】
優秀賞 「いさしかぶり!」 瀬戸 ことね (神奈川・聖園女学院高等学校 1年生)
「円香姉ちゃん!早く片付けないと、兄ちゃん達きちゃうよ!」
そんな忙しない弟の声に、不貞腐れた様子で円香は本を読んでいる手を止めた。カラリ、とローテーブルに置かれたグラスの中の氷が溶けて崩れた音がする。円香は本を本棚へと押し込んだ後、ジュースの入っているグラスを持って台所へと向かった。
台所の大きなテーブルの上には、大量の料理が所狭しと並んでいた。きゅうりの漬物、肉じゃが、牛の角煮、いわしの梅煮。旬のものが並ぶ食卓には、何膳ものお箸がともに並べられている。その上には、それらの料理を覆ってしまうほど大きな蝿帳が被されていた。円香の弟の敬太は、先程から落ち着かない様子で窓の外を見ている。茹で上がったばかりの素麺を母がテーブルに置きながら、窓にへばりつくようにして外を眺めている敬太を見て笑った。「もうすぐ来るんだから、もう少しお片付けしてちょうだい」
そんな母の一声に、敬太はハッとした顔をしてリビングに広げていたゲーム機を片付け始める。自分もまだ片付けていなかったわ、と内心ツッコミを入れながら、円香も自分の私物を片付け始めた。
円香達は、祖母の家で暮らしている。両親に母方の祖母、兄の真太、弟の敬太という、六人家族だ。そして今日、そんな円香達の家に、とある客が来る予定になっていた。
「コロナ禍も明けて、受験も終わって、やっとみんなで集まれるねぇ」
廊下から、ジャラジャラと音を立てながら玉暖簾をくぐって祖母が台所へとやってきた。仏壇に供えていたスイカを冷やそうと持ってきたらしい。円香は冷蔵庫の一番下の段を開けて、祖母から受け取ったスイカを中へと押し込んだ。すると、後ろから敬太の嬉しそうな声が聞こえる。
「来た!春樹達だ!」
片付け途中のゲーム機を床に置いたまま、母の静止の声も聞かずに、敬太は玄関へと駆け出す。そんな弟の後ろ姿を、円香は一瞥してため息をついた。
今日は、八月十三日。世間ではいわゆる月遅れの盆が始まる日である。そして、そんなお盆に合わせたお盆休みに、久しぶりに祖母の家へ集まろうと円香達のいとこがやって来るのであった。玄関へ駆け出して行った敬太に手を引かれて、まだゲーム機の散らかるリビングへと入ってきたのは、兄の真太と同い年の春樹。それから、春樹の後ろをぴったりとくっついて入ってきたのが、いとこの中では最年少の麻衣である。久しぶりのいとこの登場に、祖母と母が口許に笑みを浮かべた。
「暑いのによく来たねぇ」
「たくさんお料理作ったから、よかったら食べてね」
春樹はありがとうございます、と呟いてから席についた。それに習うように、春樹の妹の麻衣も隣に腰を下ろす。その麻衣の様子に円香は驚いて目を見開いた。少し前まで叔母の手を決して離さず、歩く姿も覚束なかったというのに。今回は兄の春樹と二人だけで円香の家へとやってきた。そして、今ではこうして席について、一人で、盛られたご飯を食べている。じっと麻衣を凝視する円香を見て、母がくすくすと笑った。
「そうよね、だって最後にあったのはもう、四年前だものね」
その言葉に、その場にいた全員がこくこく、と頷いた。四年前の新型ウイルス、コロナの流行から、親戚同士の関わり合いは少なくなってしまった。ようやく制限が緩和されてきた去年は、円香の高校受験、真太と春樹の大学受験が被り、こうして集まるのは、実に四年ぶりであった。その四年の月日は、流れてしまえばあっという間ではあるものの、こうして麻衣の成長を見ていると、どれだけ長い期間だったのかを思い知る。
「それじゃあ、すんげえいさしかぶり、ってことだねぇ」
「すんげえいさしかぶり?」
祖母が呟いた言葉を、麻衣がオウムのように繰り返しながら首を傾げた。隣で素麺を啜っていた春樹も、考え込むように箸を止めた。
「すんげえは、すごくって意味だってわかるけど、いさしかぶりは聞いたことないなぁ」
春樹の言葉に、うんうん、と円香と敬太は深く頷いた。
「ふふ、いさしかぶりはね、久しぶりって意味なんだよ」
神奈川の方言なの、と悪戯っ子のように口角をニヤリと上げた祖母に、敬太と麻衣は目を輝かせた。
訛りのない地域で育った祖母は、普段の会話には訛りはない。どうしてそんな言葉を使ったのかと疑問に思っていると、祖母は湯呑みに緑茶をトクトクと注ぎながら答えた。
「昔ね、ここに嫁いできたときに、色んな人から神奈川弁を教えてもらったんだよ。使うことはあんまり無かったけど、最近じゃあ、周りでも聞かなくなっちゃったから。少し、話してみたくなってね」
窓の外の、庭先よりもずっと遠くを見据えるような祖母の瞳には、きっと昔のこの家の周りの風景が広がっているのだろう。懐古するような、寂しいだとか悲しいだとかの感情が綯い交ぜになったその横顔に、円香の心臓は大きく、どくん、と跳ねた。それと同時に、円香は少しだけ、昔のことについて興味が湧いた。そしてそれは、春樹や麻衣、敬太も同じようで、四人は祖母の話に前のめりになって尋ねる。
「他に神奈川弁って、どんなのがあるの?」
「俺も!もっと知りたい!」
教えて、教えて、と飛びつくような勢いで尋ねてくる孫たちを見ながら、祖母と母は、顔を見合わせて微笑んだ。
日が沈みかけ、空の色が茜色に染まった頃。玄関のガチャ、という開く音に、敬太は再び駆け出す。ただいま、という声が響く前に、敬太が大きな声で言った。
「いさしかぶり!」
円香が玄関向かうと、そこには敬太に大声で挨拶をされて、ぱちぱち、と目を何度か瞬きをしている兄の真太の姿があった。敬太に続くように、リビングからひょっこり顔を出した麻衣と春樹が、同じように、いさしかぶり!と叫ぶ。未だに、弟といとこの発言が理解できずに固まったままの真太に、円香もいさしかぶり、と呟いてみる。後ろで祖母と母の笑い声が聞こえた。
「いさしかぶりはね、久しぶりって意味なんだよ!」
そう嬉しそうに言う麻衣の頭を、真太がわしわしと撫でる。頭を撫でられた麻衣は、きゃあ、と小さく歓喜の声を上げた。真太は上がり框に腰を下ろし、靴を脱ぎながら呟く。
「じゃあみんな、いさしかぶりってことか」
「うん、みんな、いさしかぶりだよ!」
他にもね、と指を一つずつ折りながら説明し始めた麻衣と敬太の話を、真太は頷きながら聞いている。なんだか、不思議な感じだ。日本語で話しているはずなのに、魔法の呪文を唱えているように、胸の奥が温まるような気がする。昔と今を繋ぐ言葉、方言。もしかすれば、身近にも、方言というものは溢れているのかもしれない。
どこか浮足立つような心地で、円香はリビングへと戻った。
夏の夜といえど、十九時は辺りがほの暗くなる。そんな時間に、円香達は玄関先の庭へ出て、輪を描くように座り込んだ。祖母が火をつけたおがらが、輪の中心でぱちぱちと音を立てて燃えていく。ゆらゆらと揺れながら空高く昇っていく迎え火を、みんなで眺めていた。焙烙の上で踊るように爆ぜていた火を、父がそっと蝋燭に移し、盆提灯の中に入れた。
「ご先祖様が喜んでいるから、こんなに火の勢いがいいんだよ」
盆提灯を持ち上げて、祖母が言う。
「じゃあ、ご先祖様にも、いさしかぶり?」
円香の手を握りながら、そう尋ねた麻衣に、ゆっくりと頷く。色鮮やかな花柄が、ぼんやりと蝋燭の灯りに照らされて淡く光を放つ。盆提灯の光に照らされながら、円香達は静かに目を瞑って手を合わせた。やがて火の音はなくなり、夏の鳴き虫達の声が庭の草むらから聞こえてくる。こうしてみんなでお盆を過ごすのは、とても久しぶりだった。また来年も、こうして集まれたら良いと願いながら、円香は盆提灯の灯りを眺める。盆提灯から放たれる、橙色の灯りだけが、辺り一面を照らし出していた。
お盆が終われば、いとこたちはそれぞれの家へと帰っていく。また次に会うとき、笑顔でいさしかぶり、と言い合ういとこたちの姿を想像すれば、不思議と見送りに寂しい気持ちは感じなかった。あれだけ聞こえていた蝉の声も、今ではもうほとんど聞こえない。蚊取り線香の匂いも、もうしなくなった。そうして、あっという間に長かったはずの夏休みが終わる。新学期が始まり、毎日の学校生活が戻ってくる。
カラカラに乾いた快晴の空の下、円香はいつも通りの通学路を、前よりも軽い足取りで歩く。ふと、前方にこちらに向かって大きく手を左右に振る友人の姿を見つけて駆け寄った。おはよう、と声をかけていた友人に、円香は満面の笑みで応えた。
「いさしかぶり!」
なにそれ、と首を傾げる友人たちに、円香は得意げにしてやったり顔をする。円香の家で、祖母がくしゃみをしたような気がした。
受賞コメント
この度は、数ある作品の中から、「いさしかぶり!」を優秀賞にご選出いただき、誠にありがとうございます。先生から受賞した、というお話をいただいたとき、驚き半分、嬉しさ半分で、しばらくは浮わついた心のままで過ごしていました。しかし、日が経つにつれ、受賞したことをひしひしと実感しています。
私は、以前から創作活動をするのが好きで、高校の授業で習った芥川龍之介の「羅生門」の続きを書き、それを先生に提出しました。そこで、先生からこのコンテストをお勧めしていただいたことがきっかけでした。ちょうど、夏休みで時間もあったので、挑戦してみたいと思い、今回、応募させていただきました。
私は幼い頃から、日本の文化や歴史に触れることが多く、気がつけば日本文化が大好きな高校生になっていました。その中で、今回のお話のテーマである「いさしかぶり」の言葉を知り、コロナ明けの夏休みに久しぶりに会った親戚一同の様子を見て、どうにかこの方言と温かな親戚の雰囲気を繋げるお話を創れないか、と考えて思いついたのがこの作品です。
この作品を書くにあたって、お盆や方言のことについて念入りに調べました。私の住んでいる地域では、あまり方言が残っておらず、お盆の時期も少しずつ違っているので、自分の家の方法と、調べた情報を混ぜ合わせて書きました。調べることは大変でしたが、それを組み合わせてお話を作っていくのは、とても楽しかったです。
今回の作品は、私の地元が主な舞台となっているので、地元について改めて知る良い機会となりました。私の地元は、歴史的な町並みが残る素敵な町なので、この方言や歴史などをよく学び、残していきたいと強く思いました。
自分の好きなことを、好きなように、好きなだけ書けるところが創作活動の魅力だと思います。スポーツだったり、お菓子作りだったり、動物だったりと、テーマは同じでも違う人が書けば、全く異なった作品が出来上がるのが、創作活動の面白いところだと思います。
日常の中でパッと思いついた言葉は、どこかにメモをとるように心がけています。その一言からお話を考えたり、書き留めておいた言葉を組み合わせてお話を作ったりするようにしています。
まずは、自分の好きなことや興味のあることから書いてみるのがいいと思います。私は日本の昔話のような雰囲気のお話が好きなので、こんなお話だったらいいな、という想像と願望を詰め込んで書いています。ぜひ、書きたいな、と思うことを、好きなように書いてみてください。