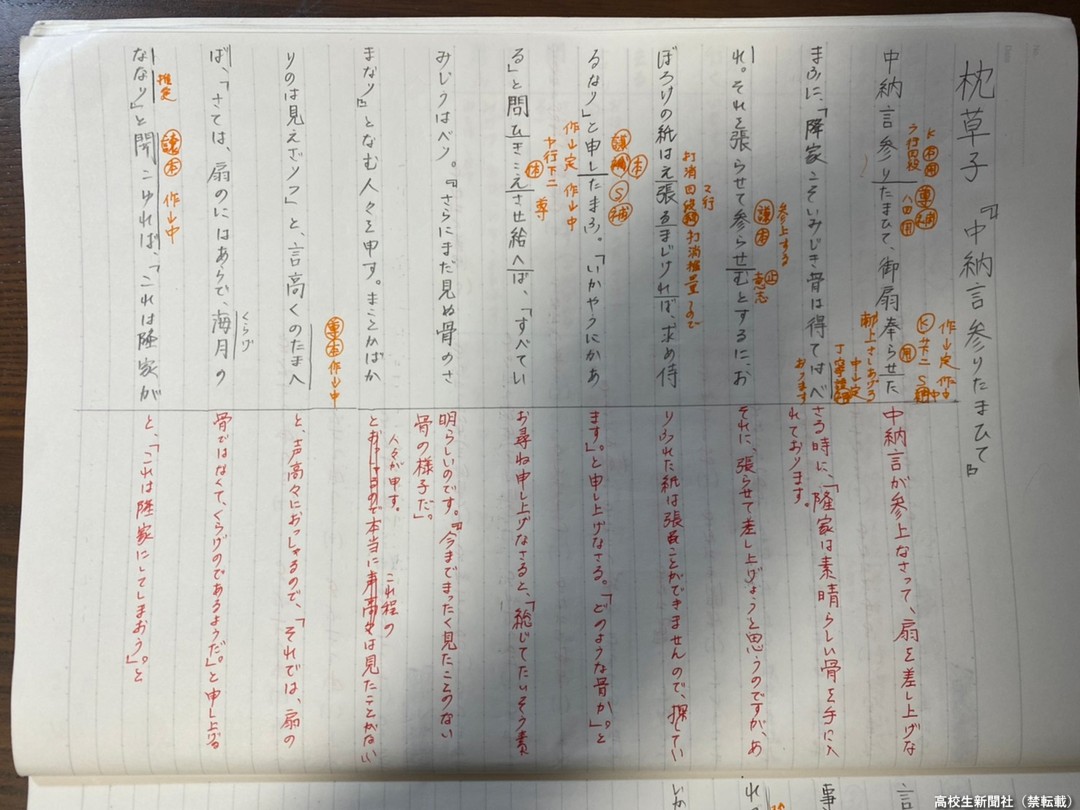科学と社会をつなぐことをテーマにしたイベント「サイエンスアゴラ」(主催・科学技術振興機構)が日本科学未来館など東京・お台場の6会場で11月3日から6日まで開催されている。3日には、東日本大震災や熊本地震を経験した高校生らが科学の面から復興の現状などを語る、メディア向けのトークセッションが開かれた。(西健太郎)
セッションは「海外から見た日本の“震災復興5年”と被災地の若者が描く未来社会」。大浦葉子さん(福島県立福島高校3年)、遠藤瞭君(福島県立ふたば未来学園高校1年)、中武聖(みさと)さん(熊本県立宇土高校2年)、ラッシュ・D・ホルト・米国科学振興協会CEO、浜口道成・科学技術振興機構理事長の5人が語り合った。
「科学技術、一般の人にも分かりやすく説明を」
浜口理事長が「東日本大震災後、科学者が災害を予測できずに『想定外』という言葉を言ったことで、科学技術を信頼する人が減った」と語り、高校生の考えを聞くと、南相馬市で被災した大浦さんは、震災後、放射線量を測る「モニタリングポスト」や「ガラスバッジ」、復興のために地元にできた「野菜工場」など、科学技術の言葉を多く目にすることになったことを紹介。「地元の住民には科学技術について分かっていない人も多く、科学技術とそれを活用する被災地との距離感が大きい。地元向けの説明会が開かれるが、データを信じられない人もいる」と指摘。「出荷される野菜の線量基準を知らない人がいることで、風評被害も生まれる」とも話した。「距離感を埋めること」を課題として挙げ、科学者と地元住民が意見交換をする機会をつくることを求めた。

福島第一原発が立地する大熊町出身の遠藤君も「放射線や原発、廃炉に向けての作業は一般の人には分かりにくいが、将来のために考えないといけない。科学技術を理解しないと故郷のことを考えられない」と大熊町民の状況を説明。原発や廃炉の説明の場に参加する地元の人が少ないといい、「知ると不安になるし、日常生活を送るには知らなくてすむ。距離感が5年たっても埋まらない」と語った。自身は本を読んだり、解説してくれる場に出向いたりして勉強しているが、「科学技術を一般の人にも分かりやすく説明する場をなるべくたくさん用意してほしい。一般の人も積極的に知ろうとしていくことが大切なのかなと考えています」。

「どこにいても地震は起きる、注意喚起を」
熊本出身の中武さんは東日本大震災時に親の仕事の都合で盛岡に住んでいた。その後、親の転勤によって熊本に戻り、今年4月の地震にも遭った。「東日本大震災では、地震の備えをしていなかったことが心残り」と振り返り、熊本でも周りの人は地震が起きるとは思っていなかったという。同世代に向けて伝えたいことを記者が尋ねると、「どこに住んでいても地震への備えは必要。予測ができても、個人の意識がないと(被害は)防げない。自分たちから周りに注意喚起できる高校生が増えてほしい」と話した。

遠藤君は、子どものころに原発の近くの体験施設で遊んだり、社会科見学で原発に行ったりしたが「(原発の説明は)すべて良い面で、自分は震災まで悪い面を考えることはなかった」と振り返る。ホルト氏は「良いことばかりを見せるのはアンフェアだ。科学者は(社会との)コミュニケーションをとろうとしないが、科学者を目指す人には、若いうちから『コミュニケーションをとろう』と言いたい。なぜなら、科学は人々の利益のものだから、関わってもらわないといけない」と話した。
「地域医療担う」「原子力工学を学ぶ」復興へ目標
高校生3人は将来の目標についても語った。中武さんは「震災で、現地で働く看護師や医者に影響された。自分も震災の経験を伝えながら、人を救う仕事に就きたい」と医療関係の仕事を目指す。大浦さんも「減った人口を戻すには教育と医療が大事」と考え、医者になって出身地で地域医療を担いたいという。遠藤君は原子力工学を勉強する考えだ。「(大熊町の)お年寄りは『自分が生きている間は(町に)戻れない』と言うが、町にたくさんの思い入れがあるのに、その状況がすごく悔しい。故郷に町民が戻れるように何かをしたい」。浜口理事長は「危機管理をできる人材が今の社会には必要。しっかり勉強してほしい」と3人に語り掛けた。