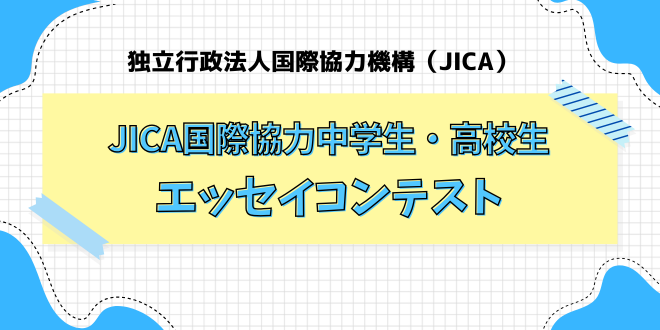国際協力特別賞
たった一足の子供靴
湘南白百合学園中学・高等学校 3年 田岡 和佳奈
「私は小さい頃、ザンビアの子どもたちに靴を寄付した」これだけ聞くとなんだか壮大な話に聞こえるが、私は物心ついてから海外に行ったことはない。私が靴を寄付したのは小学生になる前、五歳の夏だった。年に一度の夏休み。きっかけは母のひとことだった。
「あなたの履けなくなっちゃった靴を必要としている人達がいるんだよ。」まだ小学生にもなっていない私に母は言った。デパートでザンビアの子どもたちに靴を寄付するというイベントをやっているから、そのセレモニーに行こうという話だった。これは、履けなくなった子供靴を公益財団法人ジョイセフを通じてザンビア共和国に届けているという活動で、子どもたちの足を寄生虫病や破傷風から守っているのだ。このとき、ニュースに載るほど大きなセレモニーが行わ れ、私はこのセレモニーに出させていただいた。
私が世界という存在に直接触れたのは、このときが初めてだった。世界には、自分とは全然違う生活を送っている子どもたちがいること。自分がどれほど恵まれた環境にいて、どれほど幸せなのかを考え始めたのは、今思えばこのときだったのかもしれない。それ以降、世界に目を向ける度に、この母の言葉が毎回頭の中をぐるぐる回る。私があげた靴を受け取った子供は、今どこで何をしているのだろう。直接会ったわけでも、顔や名前を知っているわけでもないが、生まれた国が違うだけの同世代の仲間なのだと思うと、なんだか親近感が湧いた。それとともに、なぜ生まれた瞬間から生きていく環境が決められてしまうのかと世の中の不条理に対する怒りの気持ちも溢れてきた。生まれた国、育った環境、性別や身分など、世界の人々がつながるには超えなくてはいけない壁がいくつもあり、受け入れなくてはいけない現実がある。私達が教育を受けることができ、ご飯を三食食べることができている環境は当たり前ではなく、むしろ奇跡なのだ。 そういった環境で暮らせることへの感謝の気持ちと一生懸命学ぶ姿勢を忘れてはいけないのだと改めて強く思った。一人が一足の靴を寄付したところで、世界の人々みんなを救えるわけではないかもしれない。しかし、どんなに小さなボランティアでも、たった一度きりの参加でも、胸を張って「ボランティア活動に参加しました」と言っていいと思う。その小さくても強い勇気がボランティアに対する人々の姿勢を変え、ゆくゆくは世界の困っている人々を救うことになるからだ。この日本には幸いにも、国を超えてつながることのできるボランティア団体がたくさんある。そういった活動に携わる機会があったら、ぜひ自分から進んで参加したいと思う。
建前を気にし、あと一歩の勇気が出せない大人の世代を牽引して、私達の世代が活動を活発化させることができたら、世界の人々みんなが笑い合える未来が訪れるだろうと私は信じている。