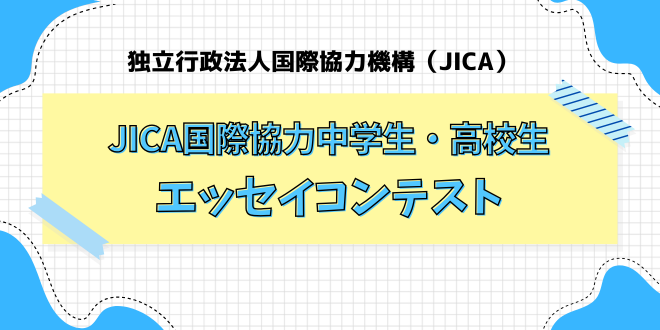高校生の部 審査員特別賞
同じ人間なのだから
鹿児島県立鶴丸高等学校2年 關 祐紀乃
「まぁいっか。誰かが出してくれるよね。」これは私が中学生の時の話だ。私の中学校で は、毎年冬になると書き損じ葉書の回収を行っていた。私は回収期間中、冒頭の言葉のよ うに考えていた。だから、何も行動を起こさぬまま回収期間を終えた。出した方がいいと 分かってはいるが、「出すのがめんどくさい」という気持ちが勝ってしまうのだ。
この書き損じ葉書の回収は、葉書を集めることでカンボジアの地雷を撤去しようという ものだった。三枚集まるごとに一平方メートルの土地の地雷を撤去することができる。地 雷におびえて暮らすカンボジアの人々を救うことができるのだ。私は、もちろん葉書を回収するのはカンボジアの人々のためだと分かっていた。だが、どうしても「人ごと」としてしか捉えることができず、遠い異国、自分には関係ないと考えてしまうのだった。
そんなことがあってから、私は市の派遣事業でマレーシア・インドネシアを訪れる機会 を得た。初めての東南アジアに期待で胸をふくらませていた。正直に言うとその期待の半分以上は、観光地に行くことやショッピングをすることなどで、現地の人との交流は二の次だった。だが研修を通して得たのは、そんな上辺だけの楽しさではなかった。人々との交流を通して得られる国境を越えたつながりの方がよっぽど私を楽しませた。ともに話をし、遊び、ご飯を食べる。何ら普段の日本での学校生活と変わらない一日一日が楽しかった。違うのは自分が今いる場所と話をする言語だけだった。私はその中で気付いたことがあった。それは違う国に住んでいるというだけで自分とは違う人だと思い過ぎていたのかもしれないということだ。国籍は違えど、同じ人間であることに変わりはないのだ。その時から私は、外国に住む人を「外国人」と捉えるのをやめた。「同じ人間」と考えるようにした。
その年の冬、また書き損じ葉書の回収が行われることになった。生徒会役員となってい た私は、今度は呼びかける立場だった。「カンボジアの人々も同じ人間だ。できることをし よう。」という思いを持った去年とは違う自分になっていた。まず、朝の時間をもらい、何 度もねり直した原稿で全校生徒に呼びかけた。しかし集まった葉書はたったの二百数枚。 そのうちの百数枚は私が祖父や親戚にも募って必死に集めたものだった。あまりの少なさ にショックを受けた。だが諦めなかった。今度は一つ一つのクラスを回り、先生方にも尋 ねに回った。すると、少しずつ枚数が増えていき、最終的には当初の枚数を大幅に超える八二九枚の葉書を集めることができた。八二九枚という枚数もそうだが、八二九枚に込められた一人一人のカンボジアに対する思いが何よりうれしかった。
葉書の回収から一つ学年が上がったある日、学校宛てに手紙が届いた。そこには、集め た葉書に対する感謝と、地雷撤去を行うことができた土地の面積が書かれていた。カンボ ジアの子どもの写真もついていた。満面の笑みだった。私には、それが私に「ありがとう」 と言っているように感じられた。その瞬間、いいようのない大きな達成感と喜びを感じた。
私はもう高校生になった。だが今でもこの時のような取り組みを続けている。募金には 積極的に参加するようにしているし、ボトルキャップは捨てずに洗って集めている。着られなくなった洋服を寄付するという取り組みにも参加してきた。世界のために、今の私ができることはこのような小さなことしかないかもしれない。だが、誰かを救う力になると信じて、これからも続けていきたいと思う。だって、国は違えど同じ人間なのだから。