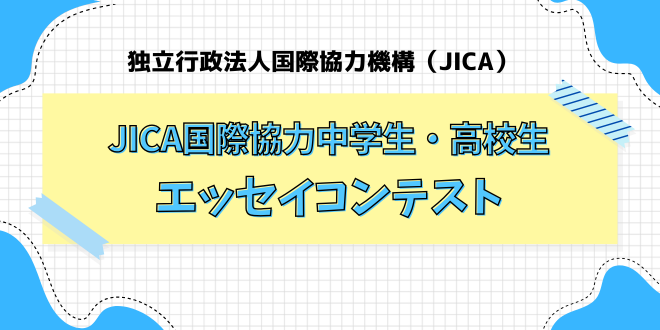審査員特別賞
私を変えた一本の定規
佐賀県立鳥栖高等学校2年 森 咲野花
初めて訪れた外国はフィジーだった。マングローブの植林や怪我をして保護されていた亀を海に放流し、現地の学校で生徒と一緒に授業を受けた。日本と文化や生活が全く違うフィジー。コロトゴ村はフィジーの中でも、伝統的な生活を現在も続けている村だ。村の様子や匂い、村人たちと過ごした日々は、今でも鮮明に覚えている。日本で暮らす私にとって、フィジーでの毎日は、想像以上のことばかりだった。
村の中を犬や猫、にわとりが自由に歩き回り、家の玄関にも入ってきた。私は毎朝午前三時に、にわとりと犬の激しい鳴き声で目を覚ました。また、村人はお互いの家を行き来するのが自由だった。朝起きると、隣に知らない子どもが寝ていたこともあった。家にはガスや電気が通っておらず、料理は薪を使っていた。初日と最終日には、村長の家で儀式が行われた。「ガバ」と呼ばれる乾燥させたコショウ科の木の根を、大きな器の中で水に濡らし、汁を絞り出す。その汁をココナッツの杯についでもらった。茶色で濁った液体。香りも味も土だった。作り方や色を見て、飲むことをためらったが、私は一気に飲み切った。飲み終えたことで、村人の一員になることができた気がして嬉しかった。村に到着した日。私は確かに存在する未知の世界への期待と不安でいっぱいだった。コロトゴ村の生活は、便利な道具に囲まれて生活する日本人の私にとって、物足りなさや不便さを感じることもあった。しかし、そんな感覚は日を重ねていくうちに自然に消えていった。自分たちの手で生活を創っていくという楽しさを味わうことができた。
フィジーの学校で、生徒が一番生き生きしていたのはランチタイムだった。机を寄せて家で作ってもらった弁当や売店で買った物を広げる。中には昼食を持ってきていない子どももいたが、持っている人が一口ずつあげてランチタイムを楽しんでいた。またクラスで定規を持っていたのは、たった一人だった。算数の授業で先生が黒板に定規で線を引いたとき、その子は自分が引き終えるとクラスのみんなに貸し始めた。持っている人が持っていない人に与えることは、彼らにとって日常の一部だったと思う。「かわいそうだから」という気持ちで生まれたものではなく、自然で必然的な行動だった。日本では見られないやりとりにフィジーの子どもたちの心の温かさを感じ、強く印象に残った。私は十分に文房具を持っていないフィジーの現状を目の当たりにし、日本に帰ったらクラスのみんなに定規を送ろうと思った。私なりに何かできることを考え、双方にとって良いアイディアだと感じていた。しかし、帰国後、旅の思い出を振り返るととともに、考え方は変化していた。日本で生まれ育った私が、自分の考えだけでフィジーの子どもたちに定規を送ることは、正しいのだろうか。子どもたちが育んでいるフィジーの精神、これからも続いていく伝統的な相手を思いやる優しさを、私の親切心で送った定規が奪ってしまうのではないだろうか。私は結局、定規を送らなかった。
幸せは、物質的な豊かさだけで決まるものではない。他者を思いやるというような心の豊かさやゆとりこそが、真の幸せであると思う。フィジーに行き、日本と異なる文化を体験したことでその思いは具体化され、確かなものになった。自分の行動を「他人のためにしてあげた」という傲慢な捉え方をするのではなく、当たり前のことだという意識を常に持つ。そんなフィジーの精神を広げることで生活の中でも、政治や外交においても、人々が幸せを感じられる瞬間は増えていくと私は信じている。