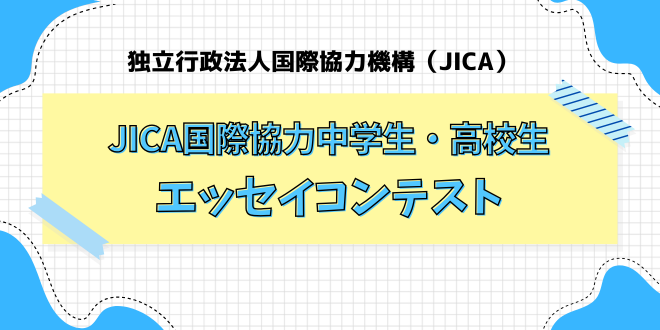- ★JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテストの募集要項はコチラ
開発途上国の現状や、開発途上国と日本との関係について理解を深め、国際社会の中でとるべき行動について考える機会を設けることを目的とし、中学生・高校生を対象にJICAが実施しているエッセイコンテスト。2024年度のテーマは「未来の地球のために~私たちにできること~」でした。これから応募にチャレンジする中高生をはじめ、国際協力に関心のある中高生もぜひ”受賞者の声“に耳を傾けてみてください。
2024年度 国際協力特別賞
鈴木 慶雅さん 山形大学附属中学校 3年

Q. エッセイコンテストに応募されたのはなぜですか? きっかけや経緯を教えてください。
中学2年生の夏、ラオスの孤児院・児童養護施設併設学校でボランティア活動をしたことが直接のきっかけです。そこで出会った子どもたちとの交流や、現地の村での滞在体験を通じて、日本にいるだけでは気づけなかった多くのことを学びました。帰国後、その経験やそれに対して抱いた思いを同世代の仲間たちと共有したいという気持ちが強くなりました。自分なりに感じたこと、考えたことをエッセイとしてまとめることで、国際問題を身近に感じてもらうきっかけを作れるのではないかと思い、応募を決意した次第です。
Q. エッセイで一番表現したかったのはどんなことですか?
日本で暮らす私たちは、テレビやインターネットを通じて世界各地の問題について情報を得ていますが、どこか「遠い世界の出来事」として捉えてしまいがちです。私自身もラオスの子どもたちと一緒に過ごし、現地の村でホームステイをする中で、言葉や文化の違いを超えて、同じ夢や希望を持つ一人ひとりの顔が見えたとき、初めて本当の意味で「同じ地球に生きる仲間」として彼らを理解できました。この実感こそが問題解決への第一歩であり、その大切さを多くの人に伝えたいと思いました。

Q. エッセイ執筆の過程で苦労したことや、工夫したことがあれば教えてください。
ラオスでの体験から得た気づきや感情は非常に多く、それらをすべて文章に込めようとすると焦点がぼやけてしまうことに苦労しました。読み手に最も伝えたいメッセージは何かを見極め、具体的なエピソードを通じてそれを表現することに時間をかけました。また、自分の体験談に終始するのではなく、読者が自分事として捉えられるような構成になるよう、何度も読み返しながら推敲を重ねました。
Q. 執筆してよかったと思うことがあれば、教えてください。
今回入賞したことで、想像以上に多くの方々に私のエッセイを読んでいただく機会を得ることができました。特に嬉しかったのは、同世代の友人たちから「自分も何かできることを探してみたい」という声を聞けたことです。また、文章を書く過程で自分自身の体験を客観視し、言語化することで、当時は漠然としていた思いがより明確になりました。中学生の頃の体験が、高校生になった今でも自分の行動指針となっていることを改めて実感し、あの経験の意味を深く理解することができました。国際協力について改めて考えるきっかけをいただいたコンテストに感謝しています。
Q. 次回のコンテストの応募を考えている生徒に向けて、テーマの決め方や、文章の書き方のアドバイスをお願いします。
日常生活の中で「なぜだろう」「おかしいな」と感じる瞬間を大切にしてほしいと思います。私自身も、実際に現地を訪れるまでは漠然とした問題意識しか持っていませんでしたが、現地の人々と直接関わることで、具体的な問題意識へと変化しました。身の回りの出来事に敏感になり、それについて調べたり考えたりする習慣をつけることが重要です。そして、自分なりの視点で問題を捉え、解決に向けて何ができるかを考える姿勢を持ってください。文章を書く際は、エッセイに書かれた内容を読み手が身近に感じられるよう、具体的なエピソードや体験を交えながら表現することをお勧めします。
Q. あなたのこれからの目標や夢があれば教えてください。国際協力に何らかの形でかかわりたいと思っているようでしたら、そのかかわり方も教えてください。
今年の夏も再びラオスを訪問し、現地の教育環境の変化を自分の目で確かめたいと考えています。また、現在は日本の中高生や大学生が現地でボランティア活動を行うための渡航プログラムを運営するプロジェクトに携わっています。参加者それぞれが異文化理解を深め、自分自身と向き合う機会を提供することで、より多くの人が国際協力に関心を持つきっかけを作りたいと思っています。将来的には、世界の教育格差の是正や貧困問題の解決に貢献できるような仕事に就きたいと考えています。