
埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科の村本良三准教授にお話を伺いました。
臨床検査学科は、国家資格である臨床検査技師を育成する学科だ。臨床検査技師は、医療現場において、血液、尿、組織、便など人の全身から採取することができるあらゆる検体を検査し、異常を見つけて医師による治療につなげる。検査なくして病気の診断や治療効果の判定はできないため、いわば医療の根幹を担う重要な仕事だ。
村本良三准教授は、同学科で臨床化学を担当する。専門は血清アルブミンだ。「アルブミンとは、生体内で栄養源となるタンパク質の一種で、臨床検査項目の中で最も血液中に多く含まれる成分です。この値で、肝硬変やネフローゼなどの病気を発見することができます」
村本准教授によれば、臨床検査の測定試薬は、絶対正しいというものが確立されておらず、常に改善が必要なのだそうだ。「臨床検査では、どうすればより正確な検査データを出せるかが臨床での判断に関わります。患者さんの血液は千差万別で、一人ひとり異なります」と村本准教授。
非特異的な反応が起こり、正確な検査データを出すことができない場合があるというのだ。そのため、臨床検査の測定法の改良・改善もまた臨床検査技師の仕事だという。
「たとえば、患者検体は自動分析装置で多項目同時測定しますが、わずかに試薬の持ち越しが起こります。このため、測定試薬順によっては次項目に影響を与えます。影響が出ない試薬順にするなどの改善を行います」
検査データの数字に疑問を持つことも重要
研究室は3年次から所属し卒業研究を行い、4年次には研究発表をする。4年次は国家試験に向けての対策や長期の臨地実習などで多忙なため、研究は3年次の長期休暇に集中して行うそうだ。研究のためのベース作りは、2年次から行う「基礎臨床化学」だ。実験・実習を通じて器材の扱いなど実験の進め方を学ぶ。とはいえ、最初は知らない専門用語が出てくると学生が理解できないこともあるそうだ。
「そんな時はなるべく丁寧に指導し知識不足を補えるようにしています。疑問は自分で解決できるようになってほしいからです。その積み重ねで、検査データについて疑問を持つ力、考える力を養います」
最後に村本准教授は高校生にこんなアドバイスをくれた。
「本学は、附属病院が3つもあり、実習や見学、就職活動にも優位です。また、臨床検査技師は、まだまだ不足しており、産休・育休をとった後でも復帰しやすい職業です。ただし、理科系の能力が総合的に必要。高校時代から、入試科目に絞らずバランスよく学んでおくと、大学での学びがスムーズです」
-
先輩に聞く
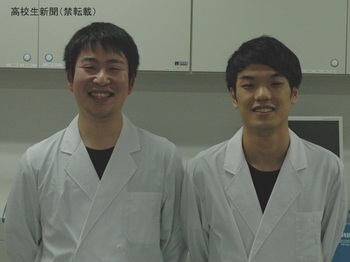 増山雄太さん(左)と鈴木岬さん(右)
増山雄太さん(左)と鈴木岬さん(右)保健医療学部臨床検査学科4年
鈴木 岬さん(静岡・星陵高等学校出身)
増山雄太さん(茨城県立下妻第二高等学校出身) -
̶̶どんな研究をしているのですか?
【増山】2人でビリルビンオキシダーゼという酵素のメカニズムについて、卒業研究を行っています。具体的には、ビリルビンオキシダーゼが他の検査項目にどのような影響を与えているのかを調べていますが、臨床の現場で実際に起きていることを知ることができたので、とても有益でした。ただ、データを見て異常のあることがわかっても、原因究明できるまでの知識が圧倒的に足りないことでは苦労しています。
【鈴木】私もそこに苦労していますが、常に「なぜなのか?」と考えることで成長できたと思います。実験で出たデータが、原因究明に結びついた時は特にやりがいを感じます。̶̶お二人とも病院に内定し、あとは国家資格を取得するだけだそうですね。どんな技師を目指していますか?
【増山】数値を見て「なぜ?」と疑問を持つことを忘れずに、患者さんにとってより良い医療を提供できる技師を目指します。
【鈴木】この人がいるからこの検査室は信頼できると思ってもらえる技師になりたいです。̶̶高校生にメッセージを。
【増山】高校生は、臨床検査技師のことをあまり知らないと思いますが、化学が好きな人にとってはとても興味深い仕事だと思います。一度、オープンキャンパスに来て、臨床検査技師の仕事にふれてみてください。
【鈴木】この学科に入ってあらためて勉強が大事だとわかりました。ただ、勉強以外にも患者さんや医療スタッフとのコミュニケーション能力も問われます。部活などを通じて、集団の中で行動する力を養っておくといいですよ。


